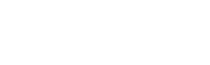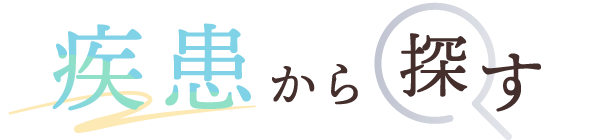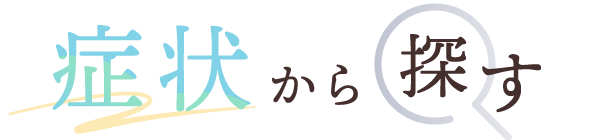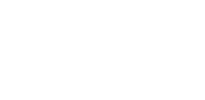- HOME
- ニキビ、ニキビ跡
ニキビ(尋常性ざ瘡)とは
ニキビ(尋常性痤瘡)は、多くの方が経験する身近な皮膚の悩みですが、その歴史は古く、現代に始まったものではありません。古代エジプトでは、蜂蜜や牛乳、サワーミルクなどがスキンケアや治療に用いられていた記録があります 。絶世の美女として知られるクレオパトラも、こうした自然の恵みを利用していたかもしれません 。古代ローマでは、硫黄を含む温泉での入浴がニキビ治療として行われていました 。記録によれば、古代エジプトのファラオ、ツタンカーメン王もニキビ跡に悩まされ、治療のための軟膏と共に埋葬されたという説もあります 。また、古代ローマの将軍ルキウス・コルネリウス・スッラも、成人してからも重度のニキビに苦しんだと伝えられています 。
中世ヨーロッパでは、魔術や呪いが原因と考えられた時代もありましたが 、ルネサンス期を経て科学的な視点が取り入れられるようになり、18世紀には皮膚科医による分類が試みられ、19世紀には皮脂腺の発見など、原因解明が進みました 。20世紀に入ると、抗菌薬やレチノイド(ビタミンA誘導体)などの画期的な治療薬が登場し、ニキビ治療は大きく進歩しました 。このように、人類は長い間ニキビと向き合い、試行錯誤を繰り返してきました。そして今、私たちは科学的根拠に基づいた、より効果的な治療法を手にすることができるようになったのです。
ニキビ(尋常性ざ瘡)概説
ニキビは、医学的には「尋常性痤瘡(じんじょうせいざそう)」と呼ばれ、毛穴とその周りの皮脂腺(毛包脂腺系)に起こる慢性の炎症性疾患です 。多くの場合、「面皰(めんぽう)」(コメドとも呼ばれます。白ニキビや黒ニキビのことです)から始まり、進行すると炎症を起こして赤ニキビ(紅色丘疹)や黄ニキビ膿疱)となり、さらに重症化すると硬いしこり(結節)や膿が溜まった袋(嚢腫)を形成することもあります 。そして、炎症が治まった後に、残念ながら「ニキビ跡」(瘢痕)として残ってしまうことがあるのが、この病気の特徴です。
日本においては、生涯で90%以上、調査によっては95%以上の方がニキビを経験すると言われており、非常にありふれた皮膚疾患です 。発症年齢は平均して男性で13.3歳、女性で12.7歳と、思春期に始まることが多いですが、決して「青春のシンボル」として片付けられるものではありません 。実際、中学生の2年生、3年生では有病率が86~87%とピークを迎えますが、高校3年生でも75%以上に見られます 。さらに重要なのは、20歳を過ぎてもニキビが続いている方が、男性で約40%、女性では50%以上にものぼるという事実です 。これは「大人ニキビ」(思春期後痤瘡)と呼ばれ、多くの方が悩んでいます。
ニキビは単なる見た目の問題だけでなく、特に症状が重くなるにつれて、自信の喪失や対人関係への影響など、生活の質(QOL)を大きく低下させる可能性があります 。不安感や抑うつ気分につながることも指摘されています 。
そして、ニキビがもたらすもう一つの大きな問題が「ニキビ跡」です。炎症が強く、長く続くほど、跡が残りやすくなります 。ニキビ跡には、皮膚がへこんでしまうタイプ(萎縮性瘢痕、いわゆるクレーター)が80~90%と最も多く 、その他に赤みや色素沈着、まれに盛り上がるタイプ(肥厚性瘢痕やケロイド)があります。ニキビ跡を完全に消すことは難しい場合もありますが、適切な治療で目立たなくすることは可能です。何よりも、ニキビ跡を予防するためには、できてしまったニキビを早期に、そして効果的に治療することが最も重要です。
なぜ皮膚科なのか?
「ニキビくらいで病院に行くなんて…」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ニキビは皮膚科で治療を受けるべき立派な皮膚の病気です。なぜ皮膚科専門医の診察が重要なのか、その理由をご説明します。
1. 専門知識と正確な診断
皮膚科医は、皮膚とその病気に関する専門家です。ニキビの診断は一見簡単そうに見えますが、実はニキビとよく似た症状を示す他の皮膚疾患がたくさんあります(「よく似た症状の別の病気」の項を参照)。例えば、酒さ(しゅさ)、毛嚢炎(もうのうえん)、口囲皮膚炎(こういひふえん)などは、見た目がニキビと似ているため、間違った自己判断や不適切なケアで悪化させてしまうことも少なくありません。皮膚科医は、これらの病気とニキビを正確に見分け、正しい診断を下すことができます。
また、ニキビの重症度を客観的に評価することも重要です。日本皮膚科学会のガイドラインでは、炎症を起こしたニキビ(赤ニキビや黄ニキビ)の数によって重症度を分類する方法が定められています 。この評価に基づいて、一人ひとりの状態に合わせた最適な治療法を選択します。
2. ガイドラインに基づいた適切な治療
皮膚科医は、最新の医学的根拠に基づいた「尋常性痤瘡・酒皶治療ガイドライン2023」 などの診療指針に沿って治療を行います。このガイドラインには、効果と安全性が確認されている標準的な治療法(処方箋医薬品の外用薬や内服薬など)が推奨度と共に示されています。市販薬やエステティックサロンでのケアとは異なり、皮膚科では医学的根拠に基づいた、より効果の高い治療を提供できます。
3. 専門的な治療法へのアクセス
皮膚科では、市販では手に入らない強力な効果を持つ処方箋医薬品を使用できます。例えば、毛穴の詰まりに直接作用するアダパレンや過酸化ベンゾイル、特定の抗菌薬(飲み薬・塗り薬)、あるいはそれらを組み合わせた配合剤などです 。さらに、面皰圧出(めんぽうあっしゅつ:毛穴の詰まりを取り除く処置)や、ケミカルピーリング、レーザー治療、光治療といった専門的な処置や施術も、必要に応じて選択肢となります 。
4. ニキビ跡の予防と治療
皮膚科でのニキビ治療の最大の目標の一つは、将来的なニキビ跡を防ぐことです。炎症を早期に抑え、適切な治療を継続することで、跡が残るリスクを最小限に抑えます。もし既にニキビ跡ができてしまっている場合でも、皮膚科医はレーザー治療、ダーマペン(マイクロニードリング)、ケミカルピーリング、サブシジョンなど、様々な専門的な治療法を駆使して、ニキビ跡を目立たなくするための治療を行うことができます。
5. 他の診療科との違い
小児科
お子さんの一般的な皮膚トラブル(あせも、おむつかぶれなど)は小児科でも対応可能ですが、ニキビが長引く場合や重症の場合、あるいはニキビ跡の治療に関しては、皮膚科の専門的な知識と経験がより役立ちます。小児科医は全身を幅広く診ますが、皮膚疾患に関する深さでは皮膚科医に及びません 。
内科・婦人科
特に大人の女性のニキビでは、ホルモンバランスの乱れが関与していることがあります 。多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)などの内科・婦人科系の病気が背景にある場合は、それらの科との連携が必要になることもあります 。しかし、ニキビそのものの診断と治療、特に皮膚に対する治療(塗り薬、レーザーなど)は皮膚科の専門領域です。ホルモン療法(低用量ピルやスピロノラクトンなど)が検討される場合もありますが、日本のニキビ治療ガイドラインではスピロノラクトンは推奨されておらず 、これらの治療は皮膚科医が主導し、必要に応じて他科と連携しながら進めるのが一般的です。
ニキビは、皮膚科で相談し、適切な診断と治療を受けることが、きれいで健康な肌を取り戻すための最も確実な近道です。
当院での治療アプローチ
当院は、県央地域に根ざした地域密着型のクリニックとして、患者様お一人おひとりの満足度を第一に考えた診療を心がけています。ニキビ・ニキビ跡治療においても、その理念に基づき、丁寧なカウンセリングと最新の知見に基づいた治療を提供いたします。
患者様のお悩みやご希望をしっかりと伺い、画一的な治療ではなく、その方のライフスタイルや肌質に合わせたオーダーメイドに近い治療計画をご提案します。特に、お子様から大人の方まで、幅広い年代のニキビに対応できる体制を整えています。
診断と治療方針
まず、丁寧な診察により、ニキビの種類(白ニキビ、黒ニキビ、赤ニキビ、黄ニキビなど)と重症度(軽症~最重症)を正確に診断します 。その上で、「尋常性ざ瘡・酒皶治療ガイドライン2023」 に準拠した保険診療を中心とした治療計画を立てます。
ニキビ治療で重要なのは、目に見える炎症を抑えるだけでなく、ニキビの根本原因である「面皰(めんぽう)」や、その前段階である「微小面皰(びしょうめんぽう)」 を改善し、ニキビができにくい肌状態を維持すること(維持療法)です。この考え方に基づき、治療薬を選択し、継続的なケアの重要性をお伝えします。
また、近年問題となっている薬剤耐性菌(薬が効きにくくなったアクネ菌)の出現を防ぐため、抗菌薬(抗生物質)の使用は必要最低限にとどめ、過酸化ベンゾイル(BPO)製剤などを積極的に活用し、漫然とした長期使用を避けるよう努めています 。
さらに、治療効果を最大限に引き出すためには、患者様ご自身のスキンケアや生活習慣の見直しも欠かせません。当院では、治療だけでなく、日々のケア方法や生活上の注意点についても、分かりやすく丁寧に指導(患者指導)させていただきます。
具体的な治療アプローチ
当院では、保険診療と自費診療(美容皮膚科)の両面から、お肌の状態やご希望に応じた最適な治療を提供します。
1. 保険診療(ガイドラインに基づく標準治療)
外用薬(塗り薬)
アダパレン(ディフェリン®ゲル)
毛穴の詰まり(面皰)を改善し、ニキビの初期段階に作用します。維持療法にも用いられます。
過酸化ベンゾイル(BPO)(ベピオ®ゲル/ローション/ウォッシュゲル)
アクネ菌を殺菌し(耐性菌の報告がありません )、角質を剥がす作用(ピーリング作用 )で毛穴の詰まりも改善します。炎症のあるニキビにも効果的です 。
外用抗菌薬(クリンダマイシン、ナジフロキサシン、オゼノキサシンなど)
アクネ菌を減らし、炎症を抑えます 。耐性菌を防ぐため、BPOやアダパレンとの併用が原則で、使用期間も限定します 。
配合外用薬(デュアック®配合ゲル、エピデュオ®ゲル)
複数の有効成分を組み合わせた薬で、利便性が高く、様々なタイプのニキビに効果が期待できます 。
内服薬(飲み薬)
内服抗菌薬(ドキシサイクリン、ミノサイクリンなど)
中等症以上の炎症が強いニキビに使用します 。ガイドラインでは最大3ヶ月程度の使用が目安とされています 。
ビタミン剤、漢方薬
補助的に用いることがありますが、ガイドライン上の推奨度は高くありません 。
処置
面皰圧出
専用の器具を用いて、毛穴に詰まった皮脂(面皰)を物理的に取り除きます 。
ヒーライト(LED治療)
特定の波長の光を照射し、皮膚の細胞を活性化させ、炎症を抑えたり、傷の治りを早めたりする効果が期待できます。他の治療との併用や、施術後のケアにも用いられます。
2. 自費診療(美容皮膚科的アプローチ)
保険診療で改善が不十分な場合や、ニキビ跡(赤み、色素沈着、クレーター)、より早い改善をご希望の場合には、自費診療の選択肢もご提案します。当院では以下の機器・施術をご用意しています。
ケミカルピーリング
グリコール酸、乳酸、マヌカハニーなどを使用し、古い角質を除去して肌のターンオーバーを促し、毛穴の詰まりや軽度のニキビ跡、くすみを改善します 。
ダーマペン
極細の針で皮膚に微細な穴を開け、肌本来の再生能力(創傷治癒力)を引き出し、コラーゲン生成を促進します。クレーター状のニキビ跡(特にローリング型やボックスカー型)の改善に効果的です 。
サブシジョン
陥凹性瘢痕の原因となっている皮膚と皮下組織の癒着をはがす方法です。CO2レーザーやヒアルロン酸注射を併用することもあります。
キュアジェット
針を使わず高圧ジェットで薬剤を真皮層に広げる治療です。クレーター状の浅〜中等度のニキビ跡や開いた毛穴に対して、コラーゲン産生を促す薬剤(ジュベルック等)を均一に届け、肌の凹凸・ハリ不足を少しずつ改善していきます。ダウンタイムや痛みが比較的軽く、仕事や学校を休みにくい方にもおすすめの治療です。深いニキビ跡はほかの治療と組み合わせることもあります。
エレクトロポレーション
電気の力を利用して、ビタミンCやトラネキサム酸などの有効成分を肌の深層まで浸透させます。ニキビ跡の色素沈着やくすみの改善、美白効果が期待できます 。
レーザー・光治療
Vビーム(色素レーザー)
ニキビ跡の赤み(炎症後紅斑)の原因である毛細血管に作用し、赤みを軽減します 。
ジェントルマックスプロ(アレキサンドライト/Nd:YAGレーザー)
ジェントルマックスプロは脱毛にも使用されるレーザーです。
CO2レーザー(炭酸ガスレーザー、フラクショナル)
皮膚に微細な穴を開けて蒸散させ、強力な皮膚再生とコラーゲン増生を促します。深いクレーター状のニキビ跡(アイスピック型、ボックスカー型)に高い効果を発揮しますが、赤みや色素沈着などのダウンタイムを伴います 。
当院で行っているニキビ跡治療
| ニキビ跡の種類 | 当院での主な治療法(自費診療) | 簡単な説明 |
|---|---|---|
| 赤み (炎症後紅斑 – PIE) |
斑 – PIE)Vビーム、ヒーライト、エレクトロポレーション (ビタミンC導入など) |
炎症後に残った毛細血管の拡張や炎症を抑えます。 |
| 色素沈着 (炎症後色素沈着 -PIH) | Qスイッチルビーレーザー、ジェントルマックスプロ、ケミカルピーリング、エレクトロポレーション (トラネキサム酸導入など) | メラニン色素にアプローチし、シミを薄くします。ターンオーバー促進も有効です。 |
| クレーター (萎縮性瘢痕) – ローリング型 | ダーマペン、CO2レーザー (フラクショナル)、ケミカルピーリング、サブシジョン、キュアジェット | なだらかな凹み。皮膚の再生を促し、コラーゲンを増やして凹みを浅くします。 |
| クレーター (萎縮性瘢痕) – ボックスカー型 | ダーマペン、CO2レーザー (フラクショナル)、サブシジョン、キュアジェット | 垂直な壁を持つ角張った凹み。ダーマペンやレーザーで皮膚の再構築を促します。 |
| クレーター (萎縮性瘢痕) – アイスピック型 | CO2レーザー (フラクショナル)、サブシジョン、キュアジェット | 狭く深い点状の凹み。物理的に皮下の瘢痕を剥離する治療が中心となります。 |
| しこり・ケロイド (肥厚性瘢痕・ケロイド)削る場合) | ステロイド局所注射 、CO2レーザー | 盛り上がった硬い跡。ステロイド注射で盛り上がりを抑えることが一般的です。 |
※上記は一般的な目安であり、実際の治療法は診察の上、個々の状態に合わせて決定します。自費診療の料金については別途お問い合わせください。
このように、当院では保険診療から最新の美容皮膚科治療まで、幅広い選択肢の中から、患者様一人ひとりに最適な治療をご提案することが可能です。
具体的な症状と年齢別の特徴
ニキビは、その見た目や状態によっていくつかの種類に分けられます。また、発症する年齢によっても特徴が異なります。ご自身のニキビがどのタイプに当てはまるかを知ることは、適切なケアや治療への第一歩です。
ニキビの種類
ニキビは、大きく分けて「面皰(めんぽう)」と「炎症性皮疹(えんしょうせいひしん)」の2つの段階があります。
面皰(コメド)
ニキビの始まり
白ニキビ(閉鎖面皰)
毛穴の出口が閉じた状態で、中に皮脂が溜まって白っぽく見える初期のニキビです 。まるで皮膚の下に小さな白い種が埋まっているような状態です。
黒ニキビ(開放面皰)
毛穴の出口が開いており、溜まった皮脂が空気に触れて酸化し、黒く見える状態です 。汚れが詰まっているように見えますが、実際は酸化した皮脂の色です。毛穴に黒い栓が詰まっているようなイメージです。
炎症性皮疹
赤みや膿を伴うニキビ 面皰の中でアクネ菌が増殖し、炎症が起こると、以下のような状態になります。
赤ニキビ(紅色丘疹)
毛穴の周りが炎症を起こし、赤く小さく盛り上がった状態です 。触ると少し痛むこともあります。毛穴の壁が刺激されて炎症を起こしているサインです。
黄ニキビ(膿疱)
赤ニキビがさらに進行し、炎症が強くなって膿が溜まった状態です 。黄色い膿が透けて見えます。ここまでくると、ニキビ跡になるリスクが高まります。
結節・嚢腫
炎症が皮膚の深い部分(真皮)まで及び、大きく硬いしこり(結節)や、膿が溜まった袋(嚢腫)になった状態です 。強い痛みを伴うことが多く、治った後も凹んだり盛り上がったりするニキビ跡になりやすい、最も重症なタイプのニキビです。まるで皮膚の下に大きなおできができたような状態です。
重症度分類
ニキビの治療方針を決める上で、どのくらいの重症度なのかを判断することが重要です。日本皮膚科学会のガイドラインでは、主に顔の片側にある炎症性皮疹(赤ニキビと黄ニキビの合計)の数を目安に、以下のように分類しています 。
ニキビの重症度分類(日本皮膚科学会ガイドラインより)
| 重症度 |
顔の片側の炎症性、皮疹の数 |
主な状態の目安 |
|---|---|---|
| 軽症 | 5個以下 |
面皰が中心で、炎症のあるニキビがポツポツと少しある程度。 |
| 中等症 | 6個~20個 |
炎症のあるニキビがやや目立ち、数も増えてきている状態。 |
| 重症 | 21個~50個 |
炎症のあるニキビが顔の広範囲に見られ、かなり目立つ状態。結節が見られることもある。 |
| 最重症 | 51個以上 |
顔全体に炎症の強いニキビや結節・嚢腫が多発し、皮膚が凹凸しているような状態。 |
ご自身のニキビがどの段階にあるかを知り、重症度に応じた適切な治療を受けることが大切です。
年齢による違い
ニキビは発症する年齢によって、原因やできやすい場所、症状の現れ方に違いが見られます。
思春期ニキビ(10代中心)
原因
主に第二次性徴に伴う性ホルモン(特にアンドロゲン)の分泌増加により、皮脂の分泌が過剰になることが大きな原因です 。
できやすい場所
皮脂腺の多いTゾーン(おでこ、鼻、あご)にできやすい傾向があります。
特徴
白ニキビや黒ニキビといった面皰が多く見られ、炎症性のニキビも混在します。
大人ニキビ(20代以降)
原因
思春期ニキビが長引く場合と、大人になってから新たに発症する場合があります 。原因は一つではなく、ホルモンバランスの乱れ(特に生理周期に伴う変動 )、ストレス、睡眠不足、不規則な食生活、不適切なスキンケア、化粧品、乾燥など、様々な要因が複雑に関与しています 。
できやすい場所
Uゾーン(あご、フェイスライン、首)にできやすい傾向があります。
特徴
炎症を起こした赤ニキビや黄ニキビが主体で、治りにくく、同じ場所に繰り返しできることが多いのが特徴です。乾燥肌なのにニキビができる、という方も少なくありません。
大人ニキビは、思春期ニキビとは異なるアプローチが必要な場合もあります。ご自身の年齢や生活背景を踏まえて、原因を探り、適切な対策をとることが改善への鍵となります。
なぜニキビ、ニキビ跡になるのか?
ニキビやニキビ跡は、なぜできてしまうのでしょうか?そのメカニズムを理解することで、日々のケアや治療への取り組み方が変わってきます。
ニキビができる主な原因
ニキビは、以下の4つの要因が複雑に絡み合って発生します 。
1. 皮脂の過剰分泌
思春期やストレスなどによってホルモン(特に男性ホルモンであるアンドロゲン)のバランスが変化すると、皮脂腺が刺激され、皮脂(皮膚のあぶら)がたくさん作られるようになります 。これがニキビの最初のきっかけとなります。
2. 毛穴の詰まり(角化異常)
通常、毛穴の皮膚(毛包漏斗部)は、古くなると自然に剥がれ落ちていきます(ターンオーバー)。しかし、何らかの原因でこのターンオーバーが乱れると、古い角質がうまく剥がれ落ちずに毛穴の出口付近に溜まり、過剰な皮脂と混ざり合って毛穴を塞いでしまいます 。これが「面皰(コメド)」、つまり白ニキビや黒ニキビの状態です。まるで、排水溝に髪の毛や石鹸カスが詰まってしまうようなイメージです。あるいは、昆虫が掘った巣穴の入り口が土や分泌物で塞がれてしまう様子にも似ているかもしれません。
3. アクネ菌の増殖
アクネ菌(Cutibacterium acnes(以前はPropionibacterium acnesと呼ばれていました))は、誰もが皮膚に持っている常在菌の一種です 。普段は悪さをしませんが、毛穴が詰まって皮脂が溜まった酸素の少ない環境が大好きで、この環境下で急激に増殖します。
4. 炎症
増殖したアクネ菌は、様々な物質を放出して毛穴の周りの組織を刺激します。また、詰まった皮脂やアクネ菌そのものに対して、私たちの体の免疫システムが反応し、炎症が起こります 。この炎症の結果、ニキビは赤く腫れたり(赤ニキビ)、膿を持ったり(黄ニキビ)するのです。
ニキビを悪化させる要因
上記の基本的なメカニズムに加えて、以下のような要因がニキビを悪化させたり、治りにくくしたりすることがあります。
ホルモンバランスの変動
思春期、生理周期、妊娠、ストレスなど 。
遺伝的な要因
ニキビができやすい体質は、ある程度遺伝すると考えられています 。
ストレス
ストレスはホルモンバランスを乱し、炎症を悪化させる可能性があります 。
生活習慣
食事
糖質の多い食品(お菓子、ジュース、白米など)や乳製品の過剰摂取が、一部の人でニキビを悪化させる可能性が指摘されていますが、すべての人に当てはまるわけではありません 。ガイドラインでは、特定の食品を一律に制限することは推奨されていません。バランスの取れた食事が基本です。
睡眠不足
睡眠不足は肌のターンオーバーを乱し、ストレスホルモンを増加させる可能性があります 。
物理的な刺激
摩擦
マスク、ヘルメット、衣類の襟、髪の毛の接触、頬杖をつく癖などが、毛穴を刺激しニキビを悪化させることがあります 。特にアウトドア活動が盛んな地域では、ヘルメットやバックパックのベルトなどによる摩擦や、汗をかいた後のケアが重要になります。
不適切なスキンケア
ゴシゴシ洗顔、洗浄力の強すぎる洗顔料、毛穴を塞ぎやすい油分の多い化粧品の使用など 。
薬剤
ステロイド(塗り薬、飲み薬、吸入薬)、一部の抗てんかん薬などが原因で、ニキビのような発疹(ざ瘡様皮疹)が出ることがあります 。
ニキビ跡ができる仕組み
ニキビ跡は、ニキビの炎症が皮膚の深い部分(真皮層)にまで及んだ結果、その部分の組織がダメージを受けてしまうことで生じます 。特に、無理に潰したり、炎症が強い黄ニキビや結節・嚢腫を放置したりすると、跡になりやすくなります 。
皮膚は、ダメージを受けるとそれを修復しようとします(創傷治癒)。この修復過程で、
コラーゲンが十分に作られない場合
皮膚が凹んでしまい、「萎縮性瘢痕(いしゅくせいはんこん)」、いわゆる「クレーター」になります 。クレーターにも、アイスピックで刺したような点状の「アイスピック型」、角張った凹みの「ボックスカー型」、なだらかな波状の凹みの「ローリング型」などの種類があります 。
コラーゲンが過剰に作られてしまう場合
皮膚が盛り上がってしまい、「肥厚性瘢痕(ひこうせいはんこん)」や「ケロイド」になります 。これらは比較的まれですが、胸や肩、顎などにできやすい傾向があります。
また、炎症が治まった直後には、一時的に赤みが残る「炎症後紅斑(えんしょうごこうはん、PIE)」や、茶色っぽいシミのような色素沈着が残る「炎症後色素沈着(えんしょうごしきそちんちゃく、PIH)」が見られることもよくあります。これらは厳密には瘢痕(傷跡)ではありませんが、見た目の上で気になる問題となります。
ニキビ跡を防ぐ最善の方法は、炎症を早期にコントロールし、ニキビを悪化させないことです。そのためにも、早めの皮膚科受診が推奨されます。
治療法
ニキビ・ニキビ跡の治療は、その原因や症状の段階、重症度、そして患者様ご自身のライフスタイルや希望に合わせて、様々な選択肢の中から最適なものを組み合わせて行います。
基本方針 ニキビ治療の基本的な考え方は、ニキビができる4つの原因(皮脂分泌、毛穴詰まり、アクネ菌、炎症)にアプローチすることです 。多くの場合、複数の治療法を組み合わせることで、より高い効果が期待できます。また、ニキビは慢性的な病気であるため、症状が改善した後も、再発を防ぐための「維持療法」を継続することが非常に重要です 。そして何よりも、ニキビ跡を残さないために、早期に治療を開始することが大切です。
保険診療(ガイドラインに基づく標準治療)
日本の「尋常性痤瘡・酒皶治療ガイドライン2023」で推奨されている、健康保険が適用される標準的な治療法です。
外用薬(塗り薬)
ニキビ治療の基本となります。
レチノイド様作用薬(アダパレン – ディフェリン®ゲル 0.1%)
毛穴の詰まり(面皰)を改善する効果が高く、ニキビの初期段階から炎症のあるニキビ、そして維持療法まで幅広く使われます 。使い始めに乾燥や赤み、ヒリヒリ感が出ることがありますが、保湿ケアを併用しながら継続することで徐々に慣れていくことが多いです。
過酸化ベンゾイル(BPO – ベピオ®ゲル 2.5%, ローション 2.5%,ウォッシュゲル 5%)
強力な酸化作用によりアクネ菌を殺菌します。この薬剤に対してアクネ菌が耐性(薬が効きにくくなること)を獲得したという報告は今のところありません 。また、角質を剥がす作用(ピーリング作用)もあり、毛穴の詰まりにも効果を示します 。炎症のあるニキビや維持療法に適しています 。こちらも乾燥や刺激感が出ることがあります。衣類などを漂白する作用があるため、塗布後はよく手を洗い、寝具などへの付着に注意が必要です。2025年には洗い流すタイプの製剤(ウォッシュゲル)も登場し、刺激感を軽減しながら治療を継続しやすくなっています 。
外用抗菌薬(クリンダマイシン – ダラシン®Tゲル/ローション、ナジフロキサシン – アクアチム®クリーム/ローション、オゼノキサシン – ゼビアックス®ローションなど)
アクネ菌の増殖を抑え、炎症を鎮めます 。主に炎症性の赤ニキビや黄ニキビに使われます。重要な注意点として、抗菌薬の単独使用や長期間の使用は、薬剤耐性菌を増やすリスクがあるため、原則としてBPOやアダパレンと併用し、使用期間も3ヶ月以内を目安とします 。
配合外用薬(アダパレン/BPO – エピデュオ®ゲル、クリンダマイシン/BPO – デュアック®配合ゲル)
作用の異なる成分を組み合わせた塗り薬です。1剤で複数の原因にアプローチでき、治療の効率化や塗り忘れの防止につながります 。エピデュオ®ゲルは維持療法にも推奨されますが、デュアック®配合ゲルは抗菌薬を含むため維持療法には推奨されません 。
その他
アゼライン酸(保険適用外ですが、ガイドラインでは選択肢の一つ )、イオウ製剤 、イブプロフェンピコノール なども、状況に応じて使用されることがあります。
内服薬(飲み薬)
内服抗菌薬
中等症から重症の炎症が強いニキビに対して、塗り薬と併用して用いられます。テトラサイクリン系のドキシサイクリン(ビブラマイシン®錠)やミノサイクリン(ミノマイシン®錠)がよく使われます 。マクロライド系のロキシスロマイシン(ルリッド®錠)やペネム系のファロペネム(ファロム®錠)なども選択肢となります 。塗り薬と同様に、耐性菌の問題から、漫然とした長期使用は避けるべきであり、ガイドラインでは投与期間は3ヶ月以内が目安とされています 。副作用として、胃腸症状や、テトラサイクリン系ではめまい、色素沈着(特にミノマイシン)、光線過敏症(日光で皮膚が赤くなりやすい)などに注意が必要です。
漢方薬
他の治療で効果が不十分な場合や、体質改善を目的として、荊芥連翹湯(けいがいれんぎょうとう)、清上防風湯(せいじょうぼうふうとう)、十味敗毒湯(じゅうみはいどくとう)などが選択肢となることがあります 。
ビタミン剤
ニキビ治療の補助として処方されることもありますが、ガイドラインでは積極的には推奨されていません 。
イソトレチノイン(経口レチノイド – アキュテイン®、ロアキュタン®など)
重症のニキビ(特に結節・嚢腫性痤瘡)に対して海外では標準治療として用いられ、非常に高い効果を発揮します 。皮脂分泌抑制、角化異常正常化、抗炎症作用、アクネ菌減少という、ニキビの4大原因すべてに作用します。しかし、日本では保険適用外であり、胎児への催奇形性(妊娠中の服用による赤ちゃんの奇形リスク)をはじめ、乾燥、肝機能障害、うつ病などの精神症状(ただし、最近の研究では自殺や精神疾患との明確な関連は否定されています )など、重篤な副作用のリスクがあるため、使用にあたっては皮膚科専門医による厳重な管理と、特に女性の場合は確実な避妊が必要です。
処置
面皰圧出
専用の器具を用いて、毛穴に詰まった面皰(白ニキビ、黒ニキビ)を押し出す処置です 。炎症を起こす前の面皰を取り除くことで、赤ニキビへの進行を予防したり、治りを早めたりする効果が期待できます。
ヒーライト(LED治療)
特定の波長のLED(発光ダイオード)光を照射することで、皮膚細胞の活性化、血行促進、抗炎症作用、創傷治癒促進などの効果が期待できます。単独での治療のほか、他のレーザー治療やピーリング後の回復を早める目的などでも用いられます。
自費診療(美容皮膚科的アプローチ)
保険診療だけでは改善が難しいニキビ跡(赤み、色素沈着、クレーター)や、より積極的に美肌を目指したい場合に、自費診療の選択肢があります。当院では以下の治療法を提供しています。
ケミカルピーリング
サリチル酸マクロゴール、グリコール酸、乳酸などの薬剤を皮膚に塗布し、古い角質や毛穴の詰まりを取り除きます。肌のターンオーバーを正常化し、ニキビができにくい肌質へ導きます。軽度のニキビ跡(特に色素沈着や浅い凹み)や、くすみの改善にも効果が期待できます 。ガイドラインでは、炎症性皮疹や面皰に対しては選択肢の一つ(C1)、萎縮性瘢痕(クレーター)に対しては推奨度は低い(C2)とされています 。
ダーマペン(マイクロニードリング)
ペン型の機器に取り付けられた極細の針で、皮膚表面に目に見えないほどの微細な穴を多数開けます。この微細な傷を治そうとする肌本来の創傷治癒力を利用して、コラーゲンやエラスチンの生成を強力に促進します。これにより、クレーター状のニキビ跡(特にローリング型、ボックスカー型)の凹みを改善し、肌のハリや弾力を高める効果が期待できます 。
キュアジェット(マイクロサブシジョン)
キュアジェットは、針を使わず高圧ジェットで薬剤を真皮層に広げる治療です。クレーター状の浅〜中等度のニキビ跡や開いた毛穴に対して、コラーゲン産生を促す薬剤(ジュベルック等)を均一に届け、肌の凹凸・ハリ不足を少しずつ改善していきます。ダウンタイムや痛みが比較的軽く、仕事や学校を休みにくい方にもおすすめです。深いニキビ跡はほかの治療と組み合わせてご提案します。
レーザー・光治療
Vビーム(色素レーザー)
赤い色(血液中のヘモグロビン)によく吸収される波長のレーザーです。ニキビ跡の赤み(炎症後紅斑)の原因となっている拡張した毛細血管を破壊することで、赤みを改善します 。
Qスイッチルビーレーザー / ジェントルマックスプロ(ロングパルスアレキサンドライト/Nd:YAGレーザー)
茶色い色(メラニン色素)によく吸収されるレーザーです。ニキビ跡の色素沈着(シミ)の原因であるメラニンを破壊し、シミを薄くします 。
CO2レーザー(炭酸ガスレーザー、フラクショナル)
皮膚の水分に吸収されるレーザーで、皮膚を微細に蒸散させ(削り取り)、強力な熱エネルギーで深部のコラーゲン再生を促します。深いクレーター状のニキビ跡(アイスピック型、ボックスカー型)に対して最も効果的な治療法の一つとされています 。効果が高い反面、施術後には赤み、腫れ、かさぶた、色素沈着などのダウンタイム(回復期間)が他の治療よりも長くなる傾向があります 。
エレクトロポレーション(電気穿孔導入)
特殊な電気パルスを皮膚に与えることで、一時的に細胞膜に微細な隙間を作り、通常では浸透しにくい高分子の有効成分(ビタミンC、トラネキサム酸、ヒアルロン酸など)を肌の深部まで効率的に導入する治療法です 。ニキビ跡の色素沈着、乾燥、くすみなどの改善に役立ちます。
注入療法
ステロイド注射
盛り上がったニキビ跡である肥厚性瘢痕やケロイドに対して、ステロイド薬を直接注射することで、盛り上がりを平らにする効果があります。ガイドラインでも選択肢の一つとして推奨されています 。
ヒアルロン酸などの充填剤
凹んだニキビ跡(ローリング型やボックスカー型の一部)にヒアルロン酸などを注入して、一時的に凹みを埋めて目立たなくする方法です。効果は永続的ではありません。ガイドラインでは推奨度は低い(C2)とされています 。
注目度の高い最新トピック
ニキビ・ニキビ跡治療は日々進歩しています。ここでは、特に注目されている最新のトピックを3つご紹介します。
1. 腸内環境とニキビ(腸-皮膚相関)
最近の研究で、「腸の健康状態が皮膚に影響を与える」という「腸-皮膚相関 (Gut-Skin Axis)」の考え方が注目されています 。腸内細菌のバランスの乱れ(ディスバイオーシス)や、腸のバリア機能が低下して有害物質が体内に漏れ出す状態(リーキーガット)が、全身の炎症を引き起こし、それが皮膚に現れてニキビを悪化させる可能性があるというのです 。プロバイオティクス(善玉菌)やプレバイオティクス(善玉菌のエサ)の摂取が、一部のニキビ患者で皮脂分泌の減少や炎症の改善につながったという報告もあります 。まだ研究段階の部分も多いですが、食生活や腸内環境を整えることが、ニキビ改善の新たなアプローチになる可能性を秘めています。
2. 新しい外用薬・剤形の開発
より効果的で、かつ副作用を少なく、使いやすいニキビ治療薬の開発が進んでいます。例えば、過酸化ベンゾイル(BPO)の新しい剤形として、洗い流すタイプの「ベピオ®ウォッシュゲル 5%」が登場しました 。これは、塗ったままにするゲルやローションに比べて皮膚への接触時間が短いため、刺激感を軽減しつつ効果を発揮することが期待され、治療の継続しやすさ(アドヒアランス)向上に繋がると考えられています。また、ローションタイプの「ベピオ®ローション」は、独自の製剤技術により、保湿力と薬剤の安定性を両立させています。
3. ニキビ跡治療の進化(コンビネーションセラピーと新技術)
ニキビ跡、特にクレーター状の瘢痕に対する治療も進化しています。単一の治療法だけでなく、複数の治療法を組み合わせる「コンビネーションセラピー」が主流になりつつあります。例えば、マイクロニードリング(ダーマペンなど)とPRP(多血小板血漿:自身の血液から抽出した成長因子)を組み合わせる治療や、レーザー治療とPRPを組み合わせる治療が、単独治療よりも高い効果を示したというメタアナリシス(複数の研究結果を統合した分析)の報告があります 。また、従来のレーザーとは異なる原理で皮膚の再生を促すフラクショナルラジオ波(RF)治療 や、特定の波長(例:1726nm)で皮脂腺に直接作用して皮脂分泌を抑える新しいレーザー など、エネルギーを用いた治療機器の開発も進んでいます。さらに、薬剤を針を使わずに高圧で皮膚内に注入する技術(例:Mirajet, Curejet )なども登場し、ニキビ跡治療の選択肢はますます多様化しています。
これらの新しい情報は、今後のニキビ・ニキビ跡治療をさらに向上させる可能性を示しています。当院でも、常に最新の情報を収集し、安全で効果的な治療法を患者様にご提供できるよう努めてまいります。
日常生活で気をつけるポイント
ニキビやニキビ跡の治療効果を高め、再発を防ぐためには、日々の生活習慣やスキンケアを見直すことも非常に大切です。ここでは、日常生活で気をつけていただきたいポイントをまとめました。
スキンケア
洗顔
- 1日2回、朝と晩に行うのが基本です 。洗いすぎはかえって肌を乾燥させ、バリア機能を低下させる可能性があります。
- 洗顔料はよく泡立て、肌をこすらず、泡で優しくなでるように洗いましょう。ゴシゴシ洗いは絶対に避けてください 。
- すすぎは、ぬるま湯(体温程度)で十分に行い、洗顔料が残らないように注意しましょう。熱いお湯は皮脂を取りすぎてしまうことが
あります。 - タオルで水分を拭き取る際も、こすらずに優しく押さえるようにしましょう。
保湿
- 「ニキビ肌=オイリー肌だから保湿は不要」というのは間違いです。むしろ、ニキビ治療薬(特にアダパレンやBPO)には肌を乾燥させる作用があるため、保湿は非常に重要です 。
- 保湿剤は、油分が少なく、毛穴を詰まらせにくい「ノンコメドジェニックテスト済み」と表示された製品を選びましょう 。化粧水だけでなく、乳液やゲル、クリームなど、ご自身の肌質や季節に合わせて適切な保湿剤を使用することが大切です。
製品選び
- スキンケア製品や化粧品は、「ノンコメドジェニックテスト済み」「オイルフリー」「アクネ(ニキビ)用」などの表示があるもの
を選ぶのがおすすめです 。 - 新しい製品を試すときは、一度に複数試さず、一つずつ様子を見ながら使用しましょう。肌に合わないと感じたら、すぐに使用を中止してください。
メイク
- メイクをする場合は、スキンケア同様、「ノンコメドジェニックテスト済み」のファンデーションやコンシーラーを選びましょう 。
- パフやブラシなどのメイク道具は、雑菌が繁殖しないようにこまめに洗浄し、清潔に保ちましょう。
- 帰宅後は、できるだけ早く、丁寧にメイクを落とすことが重要です 。クレンジング剤も、肌に負担の少ないものを選びましょう。
- 可能であれば、週に数日はメイクをしない日を設けるなど、肌を休ませる時間を作ることも有効です。
物理的な刺激を避ける
触らない・潰さない
気になるニキビをつい触ったり、自分で潰したりしたくなる気持ちは分かりますが、絶対にやめましょう。手についた雑菌が感染を広げたり、炎症を悪化させたりして、ニキビ跡が残る最大の原因となります 。
摩擦を避ける
- マスクの着用が日常的になりましたが、マスクによる摩擦や蒸れはニキビの悪化要因になります。肌触りの良い素材を選んだり、こまめに交換したり、帰宅後はすぐに外して洗顔・保湿するなどの工夫をしましょう。
- 髪の毛が顔にかからないようにする、頬杖をつかない、ヘルメットや帽子の内側を清潔に保つ、スマートフォンの画面を清潔にするなども大切です。
- 県央地域の皆様へ: アウトドア活動がお好きな方は、ヘルメットやバックパックのベルトなどが当たる部分の摩擦にご注意ください。汗をかいた後は、できるだけ早くシャワーを浴びるか、清潔なタオルで優しく汗を拭き取り、保湿ケアを心がけましょう。
生活習慣
食事
- 特定の食品(チョコレート、ナッツ、揚げ物など)が直接ニキビの原因になるという明確な証拠はありません。ガイドラインでも、一
律の食事制限は推奨されていません 。 - ただし、一部の研究では、血糖値を急上昇させやすい食品(高GI食品:お菓子、白米、パンなど)や乳製品の過剰摂取が、一部の人のニキビを悪化させる可能性が示唆されています 。もし、特定の食品を食べるとニキビが悪化すると感じる場合は、記録をつけてみて、医師に相談してみましょう。
- 基本的には、栄養バランスの取れた食事を心がけることが大切です。野菜や果物、食物繊維を多く含む食品を積極的に摂りましょう。
睡眠
質の高い睡眠を十分にとることは、肌のターンオーバーを整え、ホルモンバランスを安定させる上で重要です 。毎日決まった時間に寝起きするなど、規則正しい睡眠習慣を心がけましょう。
ストレス管理
ストレスは、ホルモンバランスを乱し、皮脂分泌を促進したり、炎症を悪化させたりする可能性があります 。自分に合ったストレス解消法(適度な運動、趣味、リラックスできる時間を持つなど)を見つけ、上手にストレスと付き合っていくことが大切です。
紫外線対策
- ニキビ治療薬の中には、アダパレンやドキシサイクリンのように、肌を紫外線に対して敏感にするものがあります 。
- また、紫外線はニキビの炎症を悪化させたり、ニキビ跡の色素沈着PIH)を濃くしたりする原因にもなります 。
- 季節や天候に関わらず、毎日、日焼け止めを使用する習慣をつけましょう。日焼け止めも、油分が少なく、ノンコメドジェニックテスト済みの、肌に優しいタイプを選ぶのがおすすめです。帽子や日傘なども活用しましょう。
これらのポイントを意識して生活することで、ニキビ治療の効果を高め、ニキビができにくい健やかな肌を目指すことができます。
よくある質問
ニキビやニキビ跡について、患者様からよくいただくご質問とその回答をまとめました。
-
- ニキビは自然に治りますか?放置しても大丈夫?
-
軽いニキビ(白ニキビや黒ニキビが中心)であれば、自然に良くなることもあります。しかし、炎症を起こした赤ニキビや黄ニキビ、あるいはそれらが多数ある中等症以上のニキビは、放置すると悪化したり、治っても跡が残ってしまったりする可能性が高いです 。特に、硬いしこり(結節)や膿の袋(嚢腫)ができるような重症のニキビは、高い確率で凹んだり盛り上がったりする瘢痕(はんこん)を残します。ニキビは単なる「若さの象徴」ではなく、治療が必要な皮膚の病気です 。跡を残さないためにも、早めに皮膚科を受診し、適切な治療を開始することをおすすめします 。
-
- 市販薬で治せますか?皮膚科に行くべき?
-
市販薬にも、サリチル酸や低濃度の過酸化ベンゾイルなど、軽いニキビに効果が期待できる成分を含むものがあります 。しかし、市販薬で十分な効果が得られない場合や、炎症が強いニキビ、繰り返しできるニキビ、ニキビ跡が気になる場合は、皮膚科を受診するべきです。皮膚科では、市販薬よりも効果の高い処方箋医薬品(アダパレン、高濃度のBPO、抗菌薬、それらの配合剤、内服薬など)を使用できます。また、医師が正確な診断を行い、一人ひとりの肌質やニキビの状態に合わせた最適な治療計画を立てることができます(「なぜ皮膚科なのか?」の項を参照)。
-
- ニキビ跡のクレーター(凹み)は治せますか?
-
残念ながら、できてしまったクレーターを完全に元の状態に戻す(「治す」)ことは非常に難しいです。しかし、諦める必要はありません。皮膚科の専門的な治療によって、クレーターを目立たなく改善させることは十分に可能です。当院で行っているサブシジョン、ダーマペン(マイクロニードリング)やCO2レーザー(フラクショナルレーザー)、ケミカルピーリング、キュアジェット(マイクロサブシジョン)などの治療は、皮膚の再生を促し、コラーゲンの生成を助けることで、凹みを浅くし、肌の質感を滑らかにする効果が期待できます 。自己流のケアだけでクレーターを改善することはほぼ不可能ですので 、お悩みの方はぜひ一度ご相談ください。
-
- 食生活はニキビに関係ありますか?チョコレートはダメ?
-
現在の医学的なガイドラインでは、特定の食品(チョコレート、ナッツ、揚げ物など)を一律に制限することは、ニキビ治療において推奨されていません。これらの食品がすべての人にとってニキビを悪化させるという明確な証拠はないためです。しかし、一部の研究では、血糖値を急激に上げる食品(高GI食品:甘いお菓子、白米、パンなど)や乳製品を多く摂ることが、一部の人のニキビを悪化させる可能性が指摘されています 。もし、ご自身で「これを食べるとニキビが悪化する気がする」と感じる食品があれば、一時的に控えてみて様子を見るのは良いかもしれません。バランスの取れた食生活を心がけることが基本です。
-
- 治療にはどのくらいの期間がかかりますか?
-
ニキビは慢性的な皮膚疾患であり、治療には根気が必要です。塗り薬の効果が現れ始めるまでには、通常4週間から8週間、場合によってはそれ以上かかることもあります 。飲み薬の抗菌薬は、耐性菌の問題から、通常3ヶ月程度を目安に使用します 。大切なのは、症状が良くなったからといって自己判断で治療をやめないことです。ニキビができにくい状態を維持するためには、多くの場合、長期的な維持療法(アダパレンやBPOなどの塗り薬を継続する )が必要になります。ニキビ跡の治療(レーザーやダーマペンなど)は、効果を実感するまでに複数回の施術が必要となり、数ヶ月単位の期間がかかることが一般的です。焦らず、医師の指示に従って治療を続けることが重要です。
-
- 治療中に気をつける副作用は?
-
ニキビ治療薬には、それぞれ副作用が現れる可能性があります。例えば、アダパレンや過酸化ベンゾイル(BPO)といった塗り薬では、使い始めに肌の乾燥、赤み、皮むけ、ヒリヒリ感などがよく見られますが、多くは治療を続けるうちに軽減します 。保湿剤をしっかり使うことで、これらの刺激感を和らげることができます 。飲み薬の抗菌薬では、胃腸の不快感や、薬の種類によっては日光に対する過敏症(光線過敏症)などが起こることがあります 。重症ニキビに使われることがあるイソトレチノイン(日本では保険適用外)は、より注意が必要な副作用があります。治療を始める際には、予想される副作用とその対処法について医師から説明がありますので、ご安心ください。もし治療中に気になる症状が現れた場合は、自己判断せず、必ず医師や薬剤師に相談してください。
まとめ
ニキビ(尋常性ざ瘡)は、思春期だけでなく大人になってからも多くの方を悩ませる、ありふれた皮膚の病気です 。しかし、決して「治らないもの」「放置するしかないもの」ではありません。現代の皮膚科学の進歩により、ニキビそのものをコントロールし、そして最も避けたい合併症であるニキビ跡を予防・改善するための効果的な治療法が数多く開発されています 。
大切なのは、ニキビを単なる美容上の問題と捉えず、早期に皮膚科専門医に相談することです。皮膚科医は、正確な診断に基づき、最新の医学的知見とガイドラインに沿った最適な治療法をご提案できます。市販薬や自己流のケアでは得られない、専門的なアプローチが可能です。
当院では、地域に根ざしたクリニックとして、患者様一人ひとりの症状、肌質、ライフスタイル、そしてご希望に寄り添った治療を大切にしています。保険診療による標準的な治療はもちろんのこと、ニキビ跡やより積極的な美肌改善を目指す方のために、CO2レーザー、Vビーム、Qスイッチルビーレーザー、ジェントルマックスプロ、ダーマペン、ケミカルピーリング、エレクトロポレーション、ヒーライトといった最新の医療機器 を用いた自費診療(美容皮膚科)の選択肢も豊富にご用意しております。丁寧なカウンセリングと分かりやすい説明を心がけ、患者様にご納得いただいた上で治療を進めてまいります。
長引くニキビ、繰り返しできるニキビ、そして気になるニキビ跡にお悩みの方は、どうか一人で抱え込まず、お気軽に当院にご相談ください。「ニキビは治せる病気」です。私たちが、皆様の健やかで美しい肌を取り戻すためのお手伝いをさせていただきます。一緒に、あなたにとって最善の解決策を見つけていきましょう。
よく似た症状の別の病気(鑑別疾患)
ニキビ(尋常性痤瘡)と似たようなブツブツや赤みが出る皮膚の病気はたくさんあります。自己判断は禁物です。皮膚科専門医による正確な診断が、適切な治療への第一歩となります。以下に、ニキビと間違えやすい代表的な病気を挙げます。
1. 酒さ (Rosacea)
顔(特に頬や鼻)が赤くなり、時にニキビのようなブツブツ(丘疹・膿疱)が出ますが、ニキビの特徴である面皰(白ニキビ・黒ニキビ)は見られません 。
2. 毛嚢炎 (もうのうえん) (Folliculitis – 細菌性、真菌性/マラセチア毛包炎)
毛穴(毛包)に細菌や真菌(カビ)が感染して炎症を起こした状態。ニキビと異なり、かゆみを伴うことが多く、面皰がないことが多いです 。
3.口囲皮膚炎 (こういひふえん) (Perioral Dermatitis)
口の周り、鼻の下、時に目の周りに、細かい赤いブツブツや赤みが出ます。唇のすぐきわには症状が出ないのが特徴です 。
4.ステロイドざ瘡 (Steroid Acne / Acneiform Eruption)
ステロイド薬(塗り薬、飲み薬、吸入薬)の使用によって誘発されるニキビ様の皮疹。同じような大きさの赤いブツブツ(丘疹・膿疱)が、顔だけでなく胸や背中、腕などに急に出現することがあります 。面皰は通常ありません。
5.薬剤性ざ瘡様皮疹 (Drug-induced Acneiform Eruption)
ステロイド以外の薬剤(抗がん剤、抗てんかん薬、抗うつ薬、ビタミンB群など)によって引き起こされるニキビ様の皮疹。原因薬剤の中止で改善することが多いです 。
6. 汗管腫 (かんかんしゅ) (Syringoma)
目の周りなどによくできる、小さくて硬い、肌色〜やや黄色っぽい良性の腫瘍(汗の管の細胞が増えたもの)。ニキビのような炎症はありません 。
7.稗粒腫 (はいりゅうしゅ/ひりゅうしゅ) (Milia)
目の周りなどにできる、白くて硬い小さな粒(角質が溜まったもの)。炎症はなく、ニキビとは異なります 。
8.毛孔性苔癬 (もうこうせいたいせん) (Keratosis Pilaris)
二の腕や太もも、お尻などによくできる、ザラザラとした小さなブツブツ(毛穴に角質が詰まったもの)。かつて「サメ肌」といわれていました。常染色体優性遺伝で、両親のどちらかがこの肌質だと子供に遺伝します。乾燥肌の人に多いです 。
9.鬚毛部仮性毛嚢炎 (しゅもうぶかせいもうのうえん) (PseudofolliculitisBarbae)
主に男性の髭剃り後に見られる、埋没毛による炎症性のブツブツ 。
10.化膿性汗腺炎 (かのうせいかんせんえん) (Hidradenitis Suppurativa)
脇の下、股の付け根、お尻などに、痛みを伴うしこりや膿瘍(おでき)が繰り返しできる慢性の炎症性疾患。ニキビの重症型(集簇性ざ瘡)と似ることがあります 。
11.接触皮膚炎 (せっしょくひふえん) (Contact Dermatitis)
化粧品や金属、植物など、特定の物質に触れることで起こるかぶれ。かゆみを伴う赤みやブツブツ、水ぶくれなどができます 。
12.脂漏性皮膚炎 (しろうせいひふえん) (Seborrheic Dermatitis)
皮脂の分泌が多い場所(Tゾーン、頭皮、胸など)に、フケのようなカサカサや赤みが出る湿疹。ニキビと合併することもあります。
13.Favre-Racouchot症候群 (Favre-Racouchot Syndrome)
高齢者の日光によく当たっていた顔面(特に目の周り)にできる、大きな黒ニキビ(面皰)や嚢腫 。
14.ざ瘡様梅毒 (Acneiform Syphilis)
梅毒の第二期に見られることがある、ニキビに似た皮疹。
15.結節性硬化症の顔面血管線維腫 (Facial Angiofibromas of TuberousSclerosis)
遺伝性の病気の一部で、顔の中心部(鼻の周りなど)に赤っぽい小さなブツブツが多発します。
16.好酸球性膿疱性毛包炎 (こうさんきゅうせいのうほうせいもうほうえん)(Eosinophilic. Pustular Folliculitis – EPF)
かゆみの強い毛穴一致性のブツブツ(丘疹・膿疱)が顔や体に出る病気。特定のタイプがあります。
17.面皰母斑 (めんぽうぼはん) (Nevus Comedonicus)
生まれつき、あるいは幼少期から見られる、黒ニキビ(面皰)が集まったアザのようなもの。
18.伝染性軟属腫 (でんせんせいなんぞくしゅ) (Molluscum Contagiosum)
いわゆる「水いぼ」。中心が少し凹んだ、光沢のある小さなブツブツ。ウイルス感染症です。
19.扁平疣贅 (へんぺいゆうぜい) (Flat Warts)
平らに盛り上がった小さなイボ。ウイルス感染症です。
20.疥癬 (かいせん) (Scabies)
ヒゼンダニというダニの寄生による病気。非常に強いかゆみと、小さな赤いブツブツや線状の皮疹(疥癬トンネル)が見られます。
これらの病気は、治療法がニキビとは全く異なります。気になる症状がある場合は、自己判断せずに、必ず当院にご相談ください。