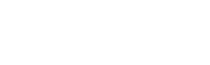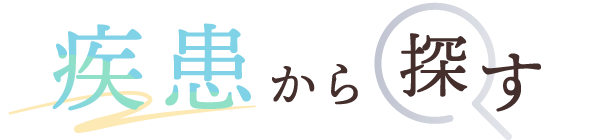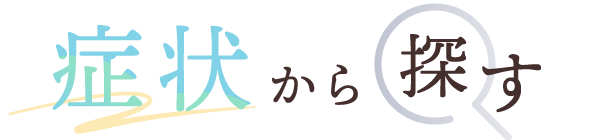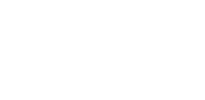- HOME
- 花粉症
花粉症とは?その症状、原因、そして皮膚科での治療
疾患概説と歴史的背景
花粉症は、医学的には季節性アレルギー性鼻炎と呼ばれる、多くの人々が悩む一般的なアレルギー疾患です。特定の季節に、空気中に飛散する植物の花粉に対して、体の免疫システムが過剰に反応することで引き起こされます。くしゃみ、鼻水、鼻詰まり、目のかゆみといった症状が代表的ですが、皮膚にも様々な影響を及ぼすことがあります。
「花粉症」という病気が認識されるようになったのは、比較的近年のことです。19世紀初頭、イギリスの医師ジョン・ボストックは、自身が夏になると体調不良や眠気に悩まされる症状を詳細に記録し、1819年に初めて医学的な報告を行いました。当初は、これらの症状は「枯れ草熱(hay fever)」と呼ばれ、その原因は干し草にあると考えられていました。しかし、1873年になって、チャールズ・ブラックリー博士が実験を通して、花粉が主な原因であることを突き止めました。興味深いことに、かつては花粉症は上流階級の人々に見られる洗練された病気であるという認識もあったようです。
一方、日本で花粉症が広く認識されるようになったのは、さらに後の時代です。初めて報告されたのは、1961年のブタクサ花粉によるアレルギーであり、次いで1963年から1964年にかけて、スギ花粉症が発見されました。年配の方々が「昔は花粉症なんてなかった」と言うのは、この歴史的事実からすると正しいと言えます。日本で最も患者数が多いスギ花粉症は、第二次世界大戦後の造林政策により大量に植えられたスギの木が成長し、花粉を大量に飛散するようになったことが背景にあると考えられています。
世界に目を向けると、花粉症のような症状は、もっと古くから記録されています。紀元前のバビロニアや古代ギリシャのヒポクラテスの記録にも、季節性の鼻炎と思われる記述が見られ、花粉症自体は比較的新しい病名ですが、その症状は古くから人類を悩ませてきたと考えられます。近年、日本において花粉症患者が増加している背景には、スギやヒノキなどの花粉飛散量の増加に加え、大気汚染食生活の変化、そして室内環境の変化などが複合的に関与していると考えられています。
なぜ花粉症になるのか?
花粉症は、体内の免疫システムが、本来無害である花粉を異物(アレルゲン)と認識し、過剰に反応することによって起こるアレルギー反応です。初めて花粉が体内に入ると、体は花粉を「敵」と認識し、それに対抗するための抗体であるIgE抗体を作り出します。このIgE抗体は、花粉に接触するたびに少しずつ体内に蓄積されていきます。一定量のIgE抗体が蓄積されると、次に花粉が侵入してきた際に、IgE抗体が鼻や目の粘膜、皮膚などに存在する肥満細胞という細胞に結合します。すると、肥満細胞からヒスタミン、ロイコトリエン、プロスタグランジンなどの化学物質が放出されます。これらの化学物質が、くしゃみ、鼻水、鼻詰まり、目のかゆみ、皮膚のかゆみや炎症といった花粉症の様々な症状を引き起こすのです。
以前は花粉症ではなかった人が、ある年から突然花粉症になるのは、それまで体内に蓄積されてきたIgE抗体が、ある閾値を超えてしまったためと考えられます。
具体的な症状と年齢別の特徴
花粉症の一般的な症状としては、鼻水(さらさらとした水のような鼻水)、くしゃみ、鼻詰まり、鼻のかゆみ、目のかゆみ、目の充血、涙目、喉のかゆみ、そして倦怠感などが挙げられます。
これらの症状は、花粉が飛散する季節に特有のものです。年齢によって花粉症の症状や現れ方に特徴が見られることがあります。
| 年齢層 | 典型的な発症 | 主な鼻症状 | 主な目の症状 |
主な皮膚症状 (花粉皮膚炎) |
症状の強さの傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子供(2-5歳) | 2-5歳 | 鼻詰まり(粘性の鼻水)、鼻水(少ない) | 目のかゆみ、充血、涙目、腫れ | まれ | – |
| 子供(学童期~青年期) | 2歳以降 | 鼻水、くしゃみ、鼻詰まり | 目のかゆみ、充血、涙目 | あり | ピーク |
| 若年成人(20-30代 ) |
どの年齢でも | 鼻水、くしゃみ、鼻詰まり | 目のかゆみ、充血、涙目 | あり | 強い |
| 成人(40-50代) | どの年齢でも | 鼻水、くしゃみ、鼻詰まり | 目のかゆみ、充血、涙目 | あり | 中程度 |
| 高齢者(60歳以上) | どの年齢でも | 鼻水、くしゃみ、鼻詰まり(比較的軽い) | 目のかゆみ、充血、涙目(比較的軽い) |
あり(比較的軽い) |
弱い |
子供
季節性アレルギーは通常2歳から5歳で始まります。幼児の場合、大人のような頻繁な鼻水やくしゃみよりも、粘り気のある鼻水による鼻詰まりが多く見られ、口呼吸になることがあります。また、目のかゆみ、充血、腫れといった目の症状が出やすい傾向があります。2歳未満の子供で慢性的な鼻の症状がある場合は、風邪の繰り返し、アデノイド肥大、牛乳アレルギーなどが原因として考えられ、花粉症である可能性は低いとされています。
大人
大人の花粉症では、年齢が上がるにつれて症状が軽くなる傾向があります。特に60歳以上の方では、20代や30代の方に比べて軽症であると回答する割合が高くなっています。また、重症の花粉症を発症した人の平均年齢は、軽症の人よりも若い傾向があります。男女別に見ると、女性の方が鼻水や目のかゆみに加え、のどの痛みや肌のかゆみを訴える割合が高いという報告もあります。
高齢者
高齢者では、一般的に花粉症の症状は比較的軽いことが多いですが、60歳を過ぎてから初めて花粉症を発症する方も少なくありません。
なぜ皮膚科なのか?―他の診療科との違い
花粉症といえば、くしゃみや鼻水、目のかゆみといった鼻や目の症状が一般的によく知られています。しかし、花粉症は皮膚にも様々な影響を与える可能性があり、その症状は「花粉皮膚炎」または「花粉症皮膚炎」と呼ばれることもあります。
花粉皮膚炎の症状は多岐にわたり、かゆみ、赤み、蕁麻疹(蚊に刺されたような膨らみ)、腫れ、乾燥、皮膚の剥がれ、そしてヒリヒリとした刺激感などが挙げられます。これらの症状は、花粉が直接触れやすい顔(特に目の周りや口元)、首、手などに現れやすいのが特徴です。花粉皮膚炎が起こる背景には、皮膚のバリア機能の低下が深く関わっています。皮膚の最も外側の層である角質層は、外部からの刺激やアレルゲンが体内に侵入するのを防ぐ役割を担っています。しかし、冬の乾燥や季節の変わり目などにより皮膚が乾燥すると、このバリア機能が低下し、花粉が皮膚に侵入しやすくなります。その結果、免疫システムが過剰に反応し、アレルギー症状として皮膚炎が生じると考えられています。
花粉による皮膚の反応には、即時型(I型アレルギー)と遅延型(IV型アレルギー)の2種類があります。即時型反応は、鼻や目の症状と同様に、花粉に触れてから比較的すぐに蕁麻疹やかゆみなどが現れるものです。一方、遅延型反応は、花粉に触れてから数時間から数日後に、接触性皮膚炎のような赤みやかゆみが生じるものです。また、鼻をかむ際のティッシュによる摩擦や、花粉を防ぐためのマスクの着用も、肌への刺激となり、皮膚炎を悪化させる可能性があります。
皮膚科医は、皮膚に関するあらゆる疾患の専門家であり、花粉皮膚炎の診断と治療においても重要な役割を担います。皮膚科では、血液検査や皮膚テスト(場合によってはパッチテスト)などを行い、原因となっている花粉を特定することができます。そして、症状や重症度に応じて、外用薬(ステロイド外用薬、抗ヒスタミン外用薬など)や内服薬(抗ヒスタミン薬、抗ロイコトリエン薬など)を処方します。さらに、皮膚のバリア機能を高め、花粉による刺激を最小限に抑えるための適切なスキンケア方法(洗顔料の選び方、保湿の重要性、日焼け止めの使用など)についても指導を行います。かつて、花粉症は一部で富裕層の病気と見なされていた時代もありましたが、現代においては、社会的な地位に関わらず多くの人々が悩む一般的なアレルギー疾患として認識されています。
当院(けんおう皮フ科クリニック)の特徴
― 当院で行っている治療アプローチ ―
当院、けんおう皮フ科クリニックでは、花粉症に伴う様々な皮膚症状に対して、皮膚科専門医によるきめ細やかな診療を行っております。一般的な治療に加え、以下のような当院ならではの治療アプローチを提供することで、患者様のQOL向上を目指しています。
治療法
花粉症の治療法は、症状を和らげるための対症療法と、アレルギー反応そのものを抑制する根本的な治療に分けられます。
対症療法
抗ヒスタミン薬
ヒスタミンの働きを抑え、くしゃみ、鼻水、かゆみを軽減します。眠気が出にくい第二世代の抗ヒスタミン薬がよく用いられます。
ステロイド点鼻薬
鼻の炎症を抑え、鼻詰まり、鼻水、くしゃみを改善します。
抗ロイコトリエン薬
ロイコトリエンという炎症物質の働きを抑え、特に鼻詰まりに効果があります。
血管収縮薬
鼻の血管を収縮させ、鼻詰まりを一時的に改善しますが、連用するとかえって鼻詰まりが悪化することがあります。
点眼薬
抗ヒスタミン作用や肥満細胞からのヒスタミン遊離を抑える作用のある点眼薬が、目のかゆみや充血を和らげます。
鼻うがい
生理食塩水で鼻の中を洗い、花粉やハウスダストなどのアレルゲンを除去します。
根本的な治療
アレルゲン免疫療法
アレルゲンを少量から徐々に投与することで、体をアレルゲンに慣らし、アレルギー反応を弱める治療法です。
- 舌下免疫療法(SLIT)…スギ花粉(シダキュア®)やダニ(ミティキュア®)のタブレットを舌の下に投与します。
- 皮下免疫療法(アレルギー注射)…アレルゲンを含む注射を皮下に行います。
抗IgE抗体療法
重症の花粉症に対して、IgE抗体の働きを抑える注射薬ゾレア®(オマリズマブ)を用いる治療法です。
当院での皮膚科的治療
(前述の「当院(けんおう皮膚科クリニック)の特徴」の項を参照)
日常生活で気をつけるポイント
花粉症の症状を軽減するためには、日常生活の中で様々な点に注意することが重要です。
花粉を避ける
- 花粉の飛散が多い日(特に乾燥した風の強い日や、雨の日の翌日など)は、できるだけ外出を控える。特に午前中や夕方は花粉の飛散量が多い傾向があります。
- 外出する際は、マスクやメガネ(花粉症用メガネ)を着用し、花粉が直接目や鼻に触れるのを防ぐ。
- 表面が滑らかな素材の服を選び、ウールなどの花粉が付着しやすい素材は避ける。
- 花粉情報(天気予報などで提供される)をこまめにチェックし、飛散量の多い日は外出を控えるなどの対策を立てる。
花粉を付着させない
- 帰宅時は、玄関に入る前に衣服や髪の毛についた花粉をよく払い落とす。
- 室内に花粉を持ち込まないよう、玄関で上着を脱ぎ、すぐに着替える。
- 洗顔、うがい、鼻をかむことを習慣にする。
室内対策
- 室内の換気は、花粉の飛散が少ない時間帯に行い、窓を開ける時間を短くする。空気清浄機(HEPAフィルター付きが望ましい)を活用する。
- こまめに掃除を行い、特に窓際や玄関周りは念入りに清掃する。掃除機はHEPAフィルター付きのものを使用し、拭き掃除も行うと効果的。
- 寝具はこまめに洗濯し、天日干しは花粉の飛散が多い時期は避けるか、室内で行う。布団乾燥機も有効。
- カーペットやカーテンはこまめに洗濯するか、アレルゲン対策の製品を使用する。
外出時の対策
- 外出時には、マスクやメガネに加え、帽子を着用して髪への花粉の付着を減らす。
- 鼻をかむ回数が増えるため、肌に優しい素材のティッシュを使用する。
- 必要に応じて、鼻の周りに花粉の侵入を防ぐクリームやスプレーを使用する。
その他
- 目をこすらないように心がける。かゆみが強い場合は、冷たいタオルで冷やしたり、点眼薬を使用する。
- ストレスを溜めない、十分な睡眠をとるなど、免疫機能を正常に保つ生活を心がける。
- 特定の果物や野菜を食べた後に口の中がかゆくなるなどの症状(口腔アレルギー症候群)が現れる場合は、原因となる食物を避けるようにする。
よくある質問
-
- 花粉症はいつから始まりますか?
-
花粉症の始まる時期は、アレルギーの原因となる花粉の種類によって異なります。日本では、スギ花粉が代表的で、多くの地域で2月下旬頃から飛び始め、4月頃まで続きます。その後、ヒノキ、カモガヤ、ブタクサなど、様々な植物の花粉が飛散しますので、ご自身がどの花粉にアレルギーがあるかを知っておくことが大切です。
-
- 花粉症の症状は風邪とどう違いますか?
-
花粉症と風邪は、鼻水、くしゃみなど似たような症状が出ることがありますが、花粉症の鼻水はサラサラとした水のような鼻水で、発熱はほとんどありません。また、目のかゆみや充血は花粉症に特徴的な症状です。一方、風邪の場合は、鼻水が黄色っぽく粘り気があり、喉の痛みや咳、発熱を伴うことが多いです。
-
- 花粉症は治りますか?
-
現在のところ、花粉症を完全に治す根治療法はありません。しかし、適切な治療を行うことで、症状をコントロールし、日常生活への影響を最小限に抑えることは可能です。アレルゲン免疫療法は、長期的な症状の軽減や体質改善が期待できる治療法です。
-
- 市販薬は効きますか?
-
はい、市販の抗ヒスタミン薬や点鼻薬、点眼薬も、軽い症状であれば効果が期待できます。ただし、症状が重い場合や、市販薬で効果が見られない場合は、医療機関を受診し、医師の診断に基づいた適切な治療を受けることをお勧めします。
-
- 妊娠中でも治療できますか?
-
妊娠中でも花粉症の治療は可能ですが、使用できる薬には制限があります。自己判断で市販薬を使用せず、必ず医師に相談し、安全な治療法を選択するようにしてください。鼻うがいなどの非薬物療法も有効です。
-
- 子供の花粉症の特徴は?
-
子供の花粉症は、鼻詰まりが強く、口呼吸になりやすい傾向があります。また、目のかゆみや充血といった目の症状が出やすいのも特徴です。2歳未満の乳幼児では、花粉症よりも他の原因による鼻炎の可能性が高いと考えられています。
-
- コンタクトレンズは使えますか?
-
花粉症の時期は、コンタクトレンズに花粉が付着しやすく、目の不快感が増すことがあります。できるだけメガネを使用するか、使い捨てタイプのコンタクトレンズを使用し、こまめに洗浄することをお勧めします。
-
- 花粉症が悪化するとどうなりますか?
-
花粉症が悪化すると、日常生活に支障をきたすだけでなく、睡眠不足や集中力の低下、鼻詰まりによる嗅覚障害などを引き起こす可能性があります。また、喘息を持っている方は、花粉症が悪化することで喘息発作が誘発されることもあります。
-
- 免疫療法は誰にでも効果がありますか?
-
アレルゲン免疫療法は、多くの方に効果が期待できる治療法ですが、すべての方に効果があるわけではありません。効果が現れるまでには時間がかかる場合もあります。治療の適応については、医師とよく相談することが重要です。
-
- 当院で受けられる特別な治療はありますか?
-
はい、当院では、一般的な花粉症の治療に加え、皮膚科ならではの花粉症に伴う皮膚症状に特化した治療を提供しています。お気軽にご相談ください。
まとめ
花粉症は、鼻や目の症状だけでなく、皮膚にも様々な影響を及ぼす可能性のある一般的なアレルギー疾患です。けんおう皮膚科クリニックでは、皮膚科専門医が、花粉症による皮膚症状をはじめ、あらゆる症状に対して適切な診断と治療を行います。当院ならではのレーザー治療など、患者様一人ひとりの症状に合わせたオーダーメイドの治療プランをご提案いたします。花粉症でお悩みの方、特に皮膚の症状にお困りの方は、ぜひ一度当院にご相談ください。
よく似た症状の別の病気(鑑別疾患)
花粉症とよく似た症状を示す病気には、以下のようなものがあります。
・感冒(かぜ)
鼻水、くしゃみなどの症状は似ていますが、感冒では発熱やのどの痛み、倦怠感などを伴うことが多いです。鼻水も、最初は水っぽいですが、徐々に粘り気のある黄色や緑色の鼻水に変わることがあります。
・血管運動性鼻炎
温度変化や湿度、特定の臭いなどが刺激となって鼻水やくしゃみ、鼻詰まりが起こりますが、アレルギー反応ではありません。目のかゆみは伴いません。
・感染性鼻炎
ウイルスや細菌による鼻の感染症で、鼻水、鼻詰まり、発熱などを伴います。鼻水は粘り気があり、黄色や緑色を呈することがあります。
・薬物性鼻炎
鼻炎スプレーの使いすぎなど、特定の薬の使用が原因で鼻詰まりが起こります。
・妊娠性鼻炎
妊娠中にホルモンバランスの変化によって鼻詰まりや鼻水が起こることがあります。
・副鼻腔炎
鼻の奥にある副鼻腔という空洞に炎症が起こる病気で、鼻詰まり、鼻水、顔の痛みなどを伴います。
・アレルギー性結膜炎
花粉やハウスダストなどが原因で、目のかゆみ、充血、涙目などの症状が現れます。花粉症と合併することが多いですが、単独で起こることもあります。
・口腔アレルギー症候群
特定の果物や野菜を食べた後に、口の中や唇、喉にかゆみや腫れなどのアレルギー症状が現れます。花粉症の方に起こりやすい症状です。
これらの病気は、花粉症と症状が似ているため、自己判断せずに、症状が続く場合や悪化する場合は、医療機関を受診して正確な診断を受けることが大切です。