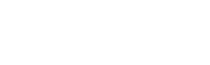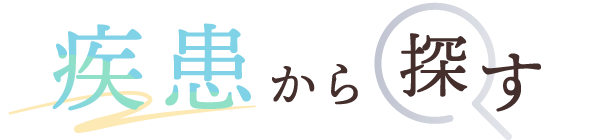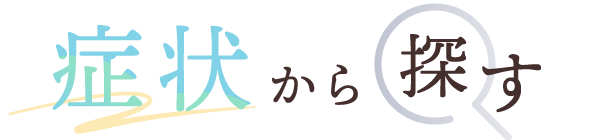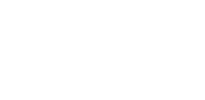- HOME
- アトピー性皮膚炎
アトピー性皮膚炎とは
アトピー性皮膚炎は、慢性的に経過する炎症性の皮膚疾患であり、強いかゆみを伴う湿疹を主な症状とします。この疾患は、皮膚のバリア機能の低下、免疫系の異常、そして様々な環境要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。古くから人々の生活を悩ませてきた病気であり、その概念や治療法は時代とともに変遷してきました。
けんおう皮フ科クリニックでは、最新の医学的知見に基づき、患者様一人ひとりに寄り添った丁寧な診療を提供いたします。
アトピー性皮膚炎の歴史
アトピー性皮膚炎の歴史は非常に古く、およそ2500年前の古代ギリシャの医師ヒポクラテスが、慢性的なかゆみを伴う皮膚の状態を初めて記述したとされています 。彼は、全身にわたる強いかゆみと、乾燥し、肥厚し、鱗状になった皮膚を持つ患者を治療しました。これらの症状は、今日私たちがアトピー性皮膚炎またはアトピー性湿疹と呼ぶ状態に相当します。古代エジプトの最も古く、重要な医学文書であるエーベルス・パピルス(約3000年前)には、皮膚のかゆみを「静める」ための治療法が記録されています 。また、初代ローマ皇帝アウグストゥスも、入浴中に掻きむしるほどの強いかゆみと、硬く乾燥した斑点に悩まされていたと言われています 。
医学用語としての「湿疹(eczema)」という言葉は、紀元543年にギリシャの医師アエティウス・アミダによって初めて使用され、「沸騰する」という意味を持ちます 。1572年には、イタリアの医師ジロラモ・メルキュリアーリが、自身初の皮膚病に関するハンドブックの中で、アトピー性皮膚炎の初期の記述を行いました 。
19世紀に入ると、アトピー性皮膚炎のより具体的な記述が、湿疹紅斑、体質性掻痒、掻痒性皮膚炎など、様々な名前で登場しました 。1817年には、イギリスの医師ロバート・ウィランとトーマス・ベイトマンが、水疱を伴う発疹(日焼けのような)を指す言葉として「湿疹(eczema)」という用語を造語しました 。これは初めてこの用語が登場した記録ですが、今日一般的に考えられている湿疹の種類とは完全に一致していません。19世紀後半には、フランスの医師ベニエが、子供のかゆみを伴う原因不明の湿疹について研究を続け、「かゆみを伴う湿疹は、ぜんそくなどの症状と一緒に起こる」という共通点を見出し、この湿疹を「ベニエ痒疹」と名付けました 。これはアトピー性皮膚炎の最初の医学的記録であると言われています。
20世紀に入り、1903年にはフランスの皮膚科医ルイ=アンヌ=ジャン・ブロクが、この状態を他の湿疹と区別するために「神経皮膚炎(neurodermatitis)」と名付け、神経との関連性を提唱しました 。この考え方は医師や一般の人々に受け入れられましたが、喘息、花粉症、食物アレルギーを持つ人にも現れることがよく知られていたにもかかわらず、神経皮膚炎は精神疾患であるという考えが広まりました。
アレルギーの概念が広まると、喘息に対する考え方に医学的な変化が見られるようになり、1923年にはアメリカの医師コークが、喘息とアレルギーが遺伝によって起こりやすいことに注目し、ギリシャ語で「奇妙な」「変わった」という意味の「アトピー(atopy)」という名前をつけました 。これが病名に「アトピー」という言葉が初めて使われた瞬間です。そして1933年、アメリカの医師フレッド・ワイズとマリオン・サルツバーガーが、かゆみや炎症が起こる皮膚炎と喘息やアレルギー性鼻炎が深く関係していることに注目し、この皮膚炎を「アトピー性皮膚炎(atopic dermatitis)」と命名しました 。
現代の治療においては、1952年に副腎皮質ステロイド外用薬が導入され、アトピー性皮膚炎の治療に革命をもたらしました 。その後、2001年には最初のタクロリムス外用薬が承認され、2016年には初の生物学的製剤が登場するなど、治療法は着実に進歩しています 。
日本においても、アトピー性皮膚炎は古くから知られており、江戸時代の医学文献に「雁瘡(がんがさ)」という言葉がしばしば登場し、アトピー性皮膚炎ではないかという説もあります 。明治時代に活躍した石塚左玄も思春期から強いかゆみに悩まされており、アトピー性皮膚炎だったのではないかと推測されています 。このように、アトピー性皮膚炎は、時代や地域を超えて、人々に影響を与え続けてきた疾患であることがわかります 。
アトピー性皮膚炎の定義と疫学(日本における)
アトピー性皮膚炎は、かゆみを伴う湿疹が良くなったり悪くなったりを慢性的に繰り返す炎症性皮膚疾患と定義されます 。多くの場合、気管支喘息、アレルギー性鼻炎、食物アレルギーなどのアトピー素因を持つ人に発症しやすいことが知られています 。
日本におけるアトピー性皮膚炎の有病率は、小児期に高く、10〜13%と報告されています 。詳細な年齢別の有病率調査によると、4ヶ月の乳児で12.8%、1歳6ヶ月で9.8%、3歳で13.2%、小学校1年生で11.8%、小学校6年生で10.6%、大学生で8.2%となっています 。
成人においても、アトピー性皮膚炎は決して稀な疾患ではありません。国内の調査によると、20歳代で10.2%、30歳代で8.3%、40歳代で4.1%、50〜60歳代で2.5%の有病率が示されています 。全体的に、若年成人に有病率が高く、年齢とともに減少する傾向があります 。性別では、女性の方が男性よりもわずかに有病率が高いことが報告されています 。
日本におけるアトピー性皮膚炎の患者数は、2017年の厚生労働省の調査では約51万人と報告されており、2008年の約35万人から増加傾向にあります 。一部の報告では、さらに多くの患者数が示唆されています 。また、小児期に発症したアトピー性皮膚炎が成人期に持ち越されるだけでなく、成人になって初めて発症する成人発症型アトピー性皮膚炎も確認されています 。
アトピー性皮膚炎の病態
アトピー性皮膚炎は、皮膚のバリア機能の低下、免疫系の異常、そして環境要因の複雑な相互作用によって引き起こされます 。
皮膚の最も外側の層である角層は、外部からの刺激やアレルゲン(ダニ、花粉、食物など)の侵入を防ぎ、体内の水分が蒸発するのを防ぐバリアとして機能しています。アトピー性皮膚炎の患者さんでは、この角層の機能が低下しており、その原因の一つとして、フィラグリンというタンパク質の遺伝子変異が強く関連しています 。フィラグリンは、角層の構造を維持し、水分を保持するために重要な役割を果たしており、このタンパク質の不足や異常は、皮膚のバリア機能を脆弱にし、外部からの刺激を受けやすく、乾燥しやすい状態を引き起こします。この「皮膚のバリアの漏れ」により、アレルゲンや刺激物が皮膚を通して体内に侵入しやすくなり、アレルギー反応や炎症を引き起こします。
免疫系の異常も、アトピー性皮膚炎の発症と悪化に深く関わっています。特に、Th2細胞と呼ばれる免疫細胞が過剰に活性化し、炎症を引き起こすサイトカイン(IL-4、IL-13、IL-31など)を過剰に産生することが知られています 。これらのサイトカインは、皮膚の炎症やかゆみを引き起こし、皮膚のバリア機能をさらに低下させる可能性があります。近年では、アトピー性皮膚炎の悪化を抑制する役割を持つ樹状細胞の機能に関する研究も進んでいます 。また、ダニなどの特定の抗原に対する免疫応答のバランスの異常も、アトピー性皮膚炎の病態に関与していることが示唆されています 。
アトピー性皮膚炎の患者さんを悩ませる強いかゆみは、掻破行動を引き起こし、それがさらに皮膚のバリア機能を破壊し、炎症を悪化させるという悪循環(かゆみと掻破の悪循環)を生み出します 。
アトピー性皮膚炎の診断基準
アトピー性皮膚炎の診断は、主に患者さんの症状と経過に基づいて行われます。日本皮膚科学会が定める診断基準では、以下の3つの主要な項目が重視されます。
1. かゆみがあること
強いかゆみはアトピー性皮膚炎の最も特徴的な症状の一つです 。
2. 特徴のある発疹とその分布
湿疹の形状や現れる部位は、年齢によって特徴的なパターンを示します。乳幼児期には顔や頭に始まり、体や手足に広がることが多く、小児期には首や関節の内側に、成人期には上半身に症状が出やすい傾向があります 。
3. 慢性的に繰り返す経過
症状が良くなったり悪くなったりを繰り返すのが特徴で、乳児では2ヶ月以上、それ以外の年齢では6ヶ月以上症状が続く場合を慢性とします 。
これらの主要な基準に加えて、アトピー素因(本人または家族にアレルギー疾患の既往がある、またはIgE抗体を産生しやすい体質)の有無も診断の参考になります 。血液検査(IgE値、好酸球数、TARC値など)は、診断の補助として、また病気の重症度や治療効果を評価するために行われることがあります 。特にTARC値は、病気の勢いを反映しやすいとされています 。まれに、他の皮膚疾患との鑑別が必要な場合には、皮膚生検が行われることもあります 。アトピー性皮膚炎の重症度やコントロール状態を評価するために、EASI(湿疹面積・重症度指数)やPOEM(患者指向型湿疹尺度)、ADCT(アトピー性皮膚炎コントロールテスト)などのスコアリングシステムが用いられることもあります 。
皮膚科におけるアトピー性皮膚炎診療の専門性
アトピー性皮膚炎の診療においては、皮膚科医が中心的な役割を果たします 。しかし、患者さんの年齢や合併症によっては、他の診療科との連携が重要になることがあります 。
皮膚科医と他の診療科との連携
乳幼児期のアトピー性皮膚炎では、小児科医との連携が不可欠です 。食物アレルギーを合併している場合や、成長発達への影響を考慮する必要があるため、緊密な情報共有と協力体制が求められます 。アレルギー専門医との連携も、原因アレルゲンの特定やアレルギー反応の管理において重要です 。
アトピー性皮膚炎は、アレルギー性鼻炎や喘息などの他のアレルギー疾患を合併することが多く、耳鼻咽喉科や呼吸器内科との連携も重要です 。特に、アレルギーマーチと呼ばれる、アトピー性皮膚炎から食物アレルギー、アレルギー性鼻炎、喘息へと病気が進行していく現象が見られる場合には、各科の専門医が連携して総合的な管理を行う必要があります 。
目の周りの湿疹がひどい場合には、眼科医の診察も定期的に受けることが推奨されます 。アトピー性皮膚炎に伴う眼の合併症(結膜炎、白内障、網膜剥離など)を早期に発見し、適切な治療を行うことが重要です 。
成人発症のアトピー性皮膚炎や、重症例、合併症を持つ患者さんの場合には、内科医との連携も考慮されます 。全身的な治療や、アトピー性皮膚炎以外の健康問題についても、包括的な管理が必要となる場合があります。
皮膚科専門医による専門的な診断と治療の重要性
皮膚科専門医は、豊富な知識と経験に基づいて、アトピー性皮膚炎とよく似た他の皮膚疾患(接触性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、貨幣状湿疹、手湿疹、尋常性乾癬、白癬、疥癬、薬疹、食物アレルギー、金属アレルギーなど)を正確に鑑別することができます 。これにより、患者さんの症状に最適な治療法を選択し、より効果的な治療を行うことが可能になります 。
皮膚科専門医は、患者さん一人ひとりの症状や生活スタイルに合わせて、外用療法、内服療法、注射療法、光線療法など、様々な治療法を組み合わせたオーダーメイドの治療計画を作成します 。また、症状の悪化因子を特定し、それらを避けるための具体的なアドバイスや、日常生活におけるスキンケアの指導なども行います 。
重症のアトピー性皮膚炎や、既存の治療法で効果が得られない場合には、生物学的製剤やJAK阻害薬などの最新の治療法を検討することも可能です 。これらの薬剤は、アトピー性皮膚炎の病態に関わる特定の分子を標的とすることで、高い治療効果が期待されています 。
皮膚科専門医による適切な管理は、症状の悪化を防ぎ、かゆみや炎症を軽減し、患者さんの生活の質を向上させる上で非常に重要です 。
けんおう皮フ科クリニックの特徴
けんおう皮フ科クリニックでは、アトピー性皮膚炎にお悩みの患者様に対し、以下のような特徴を持つ専門的な医療を提供しています。
当院で提供できる治療アプローチ
- アトピー性皮膚炎を専門とする皮膚科専門医が、患者様一人ひとりの状態に合わせたきめ細やかな診察と治療を行います 。
- 患者様の治療に対するご希望や目標を十分に考慮し、共有しながら治療方針を決定します 。
- 薬物療法だけでなく、患者様ご自身が病気と向き合い、日常生活をより快適に過ごせるように、治療に関する教育や指導を重視しています 。
導入している医療機器とその役割
エキシマライト
308nmの波長の紫外線を照射する光線治療器です。アトピー性皮膚炎、乾癬、掌蹠膿疱症、尋常性白斑、円形脱毛症などの治療に用いられ、特に限局した皮疹に対して高い効果が期待できます 。皮膚の過剰な免疫反応を抑え、かゆみや炎症を軽減する効果があり、ステロイド外用薬の使用量を減らすことができる場合もあります 。保険適用での治療が可能です 。
Vビーム
赤い色素に反応するレーザーで、アトピー性皮膚炎に伴う顔の赤みや、ステロイド外用薬の副作用による毛細血管拡張症の改善に用いられます 。保険適用外となることが多いですが、塗り薬では改善が難しい赤みに対して有効な治療法です 。
ヒーライト
LEDを用いた光線治療器で、ニキビやアトピー性皮膚炎の炎症を抑えたり、傷の治りを早めたりする効果が期待できます 。かゆみを引き起こす神経線維の正常化を促す可能性も示唆されています
保険診療を中心とした医療
当院では、患者様の経済的な負担を考慮し、保険診療を中心とした医療を提供しています。上記でご紹介した医療機器による治療も、保険適用となる場合がありますので、詳細については医師にご相談ください 。
美容皮膚科との連携
アトピー性皮膚炎の治療だけでなく、その後に気になる肌の悩み(色素沈着、傷跡など)に対しても、美容皮膚科と連携しながら、患者様一人ひとりに最適なケアを提供できる体制を整えています。
地域密着型の医療提供
けんおう皮フ科クリニックは、地域の皆様の健康な生活をサポートするため、地域に根ざした医療を提供しています。患者様との信頼関係を大切にし、安心して通院していただけるクリニックを目指しています 。
アトピー性皮膚炎の具体的な症状(年齢別)
乳幼児(2歳未満)
乳幼児期では、主に顔(特に頬)、頭、首の周りに乾燥や赤みが出ることが多いです 。かゆみが強くなると、ブツブツができたり、かき傷ができたりして、顔全体に広がることがあります 。次第に、首、脇の下、肘、膝など関節部分に湿疹が出やすくなり、お腹や背中、手足にも現れることがあります 。特に離乳期には、口の周りや頬に症状が出やすい傾向があります 。耳の付け根が赤くただれる「耳切れ」もよく見られます 。
小児(2歳~12歳)
幼児期から学童期にかけては、顔の湿疹は減少し、代わりに首の周り、脇の下、肘の内側、膝の裏側、手首、足首など、関節部分に症状が出やすくなります 。かゆくて繰り返し掻いてしまうため、皮膚がゴワゴワと硬くなることがあります(苔癬化) 。重症化すると、顔や手足の関節にも湿疹が広がり、鳥肌のように皮膚表面が小さく盛り上がることもあります 。
成人(13歳以上)
思春期以降から成人期にかけては、主に顔、首の周り、胸、背中など上半身に湿疹が強く見られるようになります 。顔や首が重症なタイプ、胸や背中、腕、足に強いかゆみを伴う結節状の皮疹が多発するタイプ、全身の皮膚が赤くなるタイプなど、症状は多様化します 。炎症を繰り返すと、色素が沈着して皮膚が黒ずむことがあります 。また、手や足に症状が出やすい方もいます 。
どの年齢層においても、アトピー性皮膚炎の患者さんの多くは、皮膚が乾燥しやすいという特徴を持っています 。
アトピー性皮膚炎がなぜ起こるのか
アトピー性皮膚炎の発症には、遺伝的要因、環境要因、そして免疫系の異常が複雑に関与しています 。
遺伝的要因
アトピー性皮膚炎は、アレルギーを起こしやすい体質(アトピー素因)を持つ人に発症しやすいことが知られています 。アトピー素因は遺伝する傾向があり、ご家族にアレルギー疾患(気管支喘息、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎など)を持つ方がいる場合、発症リスクが高まります 。特に、皮膚のバリア機能に関わるフィラグリンというタンパク質の遺伝子変異は、アトピー性皮膚炎の発症に強く関連していることがわかっています 。ただし、遺伝的要因を持つ人が必ずアトピー性皮膚炎を発症するわけではありません 。
環境要因
様々な環境要因が、アトピー性皮膚炎の症状を悪化させる可能性があります 。代表的なものとして、ダニ、ハウスダスト、花粉、ペットの毛、カビなどのアレルゲン 、石鹸、洗剤、化粧品などの刺激物 、乾燥した空気 、汗 、そしてストレス などが挙げられます。これらの要因は、皮膚のバリア機能を低下させたり、免疫系を刺激したりすることで、炎症やかゆみを引き起こすと考えられています 。
免疫系の異常
アトピー性皮膚炎の患者さんでは、免疫系のバランスが崩れており、本来は体に害のない物質に対しても過剰な免疫反応が起こります 。特に、Th2細胞と呼ばれる免疫細胞が活性化し、炎症性サイトカイン(IL-4、IL-13など)を過剰に産生することが、皮膚の炎症やかゆみの原因となります 。近年では、アトピー性皮膚炎の悪化を抑える役割を持つ樹状細胞の機能に関する研究も進んでいます。
日本における疫学データ
日本におけるアトピー性皮膚炎の罹患率は、小児期で10〜13%、20歳代で10.2%、30歳代で8.3%、40歳代で4.1%、50〜60歳代で2.5%と報告されています 。厚生労働省の調査によると、国内の患者数は2017年時点で約51万人とされていますが、近年増加傾向にあります 。
現在行われているアトピー性皮膚炎の治療法
アトピー性皮膚炎の治療は、皮膚の炎症を抑え、かゆみを軽減し、皮膚のバリア機能を回復させることを目的として行われます 。
外用療法
ステロイド外用薬
炎症を速やかに抑える効果があり、症状の悪化時に第一選択として用いられます。強さによっていくつかのランクに分けられています 。商品名としては、アンテベート、ロコイド、リンデロンなどがあります 。
非ステロイド性抗炎症外用薬
タクロリムス(商品名:プロトピック)
ステロイドとは異なるメカニズムで炎症を抑え、ステロイド外用薬の副作用が懸念される部位(顔や首など)にも使用できます 。
デルゴシチニブ(商品名:コレクチム)
JAK-STAT経路を阻害することで、炎症やかゆみを抑えます 。
ジファミラスト(商品名:モイゼルト)
PDE4を阻害することで、炎症を抑制するシグナルを上昇させます 。
タピナロフ(商品名:ブイタマー)
AhR(芳香族炭化水素受容体)を活性化することで、炎症を抑制し、皮膚バリア機能を改善します 。
内服療法
抗ヒスタミン薬
かゆみを抑える効果があり、特に夜間の掻痒感を軽減するのに役立ちます。商品名としては、ポララミン、ジルテック、アレグラなどがあります 。
ステロイド内服薬
重症の症状に対して、短期間用いられることがあります。プレドニン、デカドロンなどが商品名として挙げられます 。
免疫抑制薬
シクロスポリン(商品名:ネオーラル)などが、重症のアトピー性皮膚炎に対して用いられることがあります 。
注射療法
生物学的製剤
デュピルマブ(商品名:デュピクセント)
IL-4とIL-13の働きを阻害することで、炎症を抑えます 。
ネモリズマブ(商品名:ミチーガ)
かゆみを誘発するIL-31の働きを抑えます 。
トラロキヌマブ(商品名:アドトラーザ)
IL-13を選択的に阻害します 。
レブリキズマブ(商品名:イブグリース)
IL-13の働きを阻害します 。
JAK阻害薬
バリシチニブ(商品名:オルミエント)
JAK1/2を阻害し、炎症を抑えます 。
ウパダシチニブ(商品名:リンヴォック)
JAK1を選択的に阻害します 。
アブロシチニブ(商品名:サイバインコ)
JAK1を選択的に阻害します 。
注目の最新トピック
1.タピナロフ(ブイタマー)クリーム
2024年に承認された新しい作用機序の外用薬で、AhRを活性化することで炎症を抑制し、皮膚バリア機能を改善します 。
2.レブリキズマブ(イブグリース)皮下注
2024年5月に発売された新しい生物学的製剤で、IL-13を標的とし、既存治療で効果不十分な中等度以上のアトピー性皮膚炎の患者さんに使用されます 。
3. JAK阻害薬の内服薬
バリシチニブ、ウパダシチニブ、アブロシチニブなどのJAK阻害薬は、炎症に関わるJAKという酵素の働きを抑えることで、高い治療効果が期待されています 。
アトピー性皮膚炎の予防や治療において、日常生活で気をつけるべきポイント
アトピー性皮膚炎の予防や治療には、薬物療法だけでなく、日常生活における注意も非常に重要です 。
スキンケア
- 毎日入浴またはシャワーで皮膚を清潔に保ちますが、熱いお湯やゴシゴシ洗いは避けましょう 。
- 低刺激性の石鹸やシャンプーを選び、十分に洗い流しましょう 。
- 入浴後や皮膚が乾燥したと感じた時には、すぐに保湿剤をたっぷりと塗りましょう 。セラミドやヘパリン類似物質配合の保湿剤がおすすめです 。
保湿
- 保湿剤は、症状のある時だけでなく、症状が落ち着いている時も継続して行うことが大切です 。
- 季節や肌の状態に合わせて、軟膏、クリーム、ローションなどを使い分けましょう 。
環境整備
- 室内のダニやハウスダストを減らすために、こまめに掃除や換気を行いましょう 。
- 寝具は清潔に保ち、布団乾燥機や天日干しを活用しましょう 。
- 室内の温度や湿度を適切に保ち、乾燥を防ぎましょう 。
食事
- バランスの取れた食事を心がけ、特に野菜や果物を積極的に摂りましょう 。
- 甘いものや脂っこいもの、刺激物は控えめにしましょう 。
- 特定の食物アレルギーが疑われる場合は、医師の指導のもとで食事療法を行うことがあります 。
ストレス管理
- ストレスはアトピー性皮膚炎の悪化要因となるため、適度な運動や趣味などでストレスを解消しましょう 。
- 十分な睡眠を確保し、規則正しい生活を送りましょう 。
その他
- 爪は短く切り、掻きむしりを防ぎましょう 。
- 刺激の少ない綿素材の衣類を選び、新品の衣類は洗濯してから着用しましょう 。
- 汗をかいたらこまめに拭き取るか、シャワーで洗い流しましょう。
よくある質問(FAQ)
-
- アトピー性皮膚炎は治るのか?
-
アトピー性皮膚炎は、症状が良くなったり悪くなったりを繰り返す慢性的な病気ですが、適切な治療と日常生活でのケアを続けることで、症状をコントロールし、日常生活に支障がない状態を維持することが可能です 。小児期に発症した場合は、成長とともに自然に軽快することもありますが、成人期にも症状が続く場合や、成人になってから発症する場合もあります 。
-
- 市販薬で対応できるのか?
-
軽度の症状であれば、市販の保湿剤や弱めのステロイド外用薬で改善が見られることもありますが、症状が改善しない場合や悪化する場合は、自己判断せずに皮膚科専門医を受診し、適切な診断と治療を受けることが重要です 。
-
- 悪化したらすぐに受診すべきか?
-
かゆみがひどい、湿疹が広範囲に広がった、ジュクジュクしている、化膿しているなどの症状が見られた場合は、速やかに皮膚科を受診してください。早期に適切な治療を開始することで、症状の悪化を防ぎ、早期の改善につながります 。
-
- アトピー性皮膚炎は人にうつるのか?
-
アトピー性皮膚炎は、細菌やウイルスによる感染症ではないため、人にうつることはありません 。
-
- 食事制限は必要か?
-
アトピー性皮膚炎の原因は様々であり、必ずしも食べ物が直接的な原因とは限りません 。自己判断での過度な食事制限は、成長期のお子さんの場合、栄養バランスを崩す可能性があります。食物アレルギーが疑われる場合は、医療機関で検査を受け、医師の指導のもとで食事療法を行うようにしましょう 。
まとめ
けんおう皮フ科クリニックでは、アトピー性皮膚炎にお悩みのすべての患者様に対し、専門的な知識と豊富な経験に基づいた、質の高い医療を提供しています。患者様一人ひとりの症状やライフスタイルに合わせたオーダーメイドの治療計画を作成し、最新の治療法と医療機器を駆使して、症状の改善と生活の質の向上をサポートいたします。地域ナンバーワンを目指し、患者様に寄り添った丁寧な診療を心がけておりますので、アトピー性皮膚炎でお困りの方は、ぜひ一度当院にご相談ください 。
アトピー性皮膚炎とよく似た症状を示す可能性のある他の病気
アトピー性皮膚炎と症状が似ているため、鑑別が必要となる皮膚疾患は多岐にわたります。
以下に代表的なものを挙げます 。
接触性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、貨幣状湿疹、手湿疹、尋常性乾癬、白癬(水虫)、疥癬、薬疹、食物アレルギー、金属アレルギー、アレルギー性鼻炎、喘息、新生児中毒性紅斑、乳児脂漏性皮膚炎、突発性発疹、伝染性膿痂疹(とびひ)、単純ヘルペス、帯状疱疹、汗疹(あせも)、皮脂欠乏性湿疹、痒疹 。
結論
アトピー性皮膚炎は、歴史的に長く人々に苦しみを与えてきた慢性炎症性疾患であり、その病態は複雑で多岐にわたります。しかし、近年における医学の進歩により、様々な治療法が開発され、患者さんの生活の質は大きく改善しています。けんおう皮フ科クリニックでは、最新の知見に基づいた専門的な診療と、患者様一人ひとりに寄り添った丁寧なケアを通じて、地域のアトピー性皮膚炎診療をリードしてまいります。症状にお悩みの方、治療にご不安をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください 。