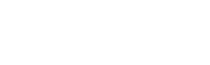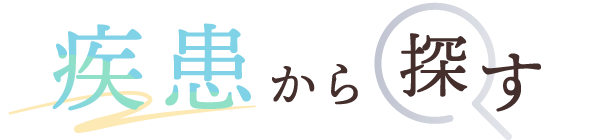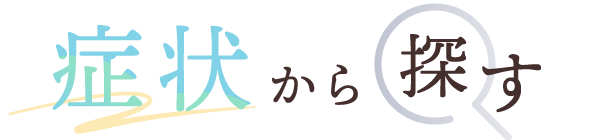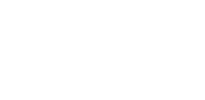- HOME
- 子どもの青あざ、赤あざ、茶あざ、黒あざ
赤ちゃんのあざとは
生まれつきまたは乳幼児期に現れる皮膚の変色や斑点は、一般に「赤ちゃんのあざ」と呼ばれます。医学的には母斑(ぼはん)とも言い、皮膚の一部分に色素細胞や血管が集中することで生じる現象です。昔から世界各地であざにまつわる文化や迷信があり、例えば「妊娠中に特定の食べ物(例えばイチゴ)を我慢すると、赤ちゃんにその形のあざができる」といった言い伝えが知られています。しかしもちろん、こうした迷信に科学的根拠はありません。赤ちゃんのあざは妊娠中の母親の行動や出産時のトラブルが原因で起こるものではなく、胎児の発育過程で生じる皮膚のちょっとした「むら」によるものです。実際、赤ちゃんの約1割には何らかのあざが見られるとも報告されており、多くは良性で健康に影響しません。ただし大きさや場所によっては見た目の問題や合併症につながることもあり、適切なケアや治療が必要な場合があります。
歴史的にも赤ちゃんのあざは様々な記録があります。例えば、日本の赤ちゃんに多いお尻の青いあざ「蒙古斑(もうこはん)」は、1883年に来日していたドイツ人医師エルヴィン・ベルツによってその存在が報告・命名されました。蒙古斑は東アジア系の民族に特有と考えられたためこの名がつきましたが、その後の研究で人種を問わず発生しうることが分かっています。一方、額やまぶたに現れる薄紅色のあざは「天使のキス」、首の後ろのあざは「コウノトリが運んできた赤ちゃんをつかんだ跡」などと呼ばれることもあり、赤ちゃんの誕生にまつわる微笑ましい俗称も各国に存在します。いずれにせよ、赤ちゃんに現れる青あざ・赤あざ・茶あざ・黒あざには様々な種類があり、その成り立ちや経過、治療法もそれぞれ異なります。本記事では、小さなお子さんの保護者の視点に立って、赤ちゃんに見られる代表的なあざの種類と原因・症状、経過、治療法、日常生活でのケアについて分かりやすく解説します。
なぜ皮膚科なのか? ― 他の診療科との違い ―
赤ちゃんのあざの相談先としては、「皮膚科でいいの?」「小児科や形成外科ではないの?」と迷われる保護者の方もいるかもしれません。結論から言えば、まずは皮膚科専門医の受診が適切です。皮膚科は皮膚の病気全般を扱う専門診療科であり、あざ(母斑)に関しても診断と治療の経験が豊富です。他方、小児科は子どもの全身の健康を扱う総合診療科で、あざ自体の専門的な治療(レーザー治療や外科的処置など)は通常行っていません。また形成外科は手術による外見の修復を専門とする科で、あざの中でも特に外科的切除や再建が必要な場合に力を発揮します。実際の診療では、皮膚科医があざの種類を的確に診断し、経過観察でよいものか治療が必要か判断します。治療が必要と判断された場合、皮膚科で対応できるもの(レーザー治療や外用・内服治療)は皮膚科で行い、手術が望ましいケースでは形成外科と連携します。例えば、血管腫(赤あざ)に対するレーザー治療やお薬による治療は皮膚科領域であり、逆に大きな黒あざの手術は形成外科の領域ですが、その判断や術後ケアも含め皮膚科医がトータルにサポートします。つまり皮膚科は「あざ治療の司令塔」として、必要に応じて他科と協力しながらお子さんにとって最適な治療プランをコーディネートする役割を担っています。
また、皮膚科では小さなお子さんへの対応にも慣れています。赤ちゃんのデリケートな皮膚に適した治療法の選択や、副作用の少ないお薬の使い方など、専門的な知識があります。当院のように小児皮膚科に力を入れているクリニックでは、子どものあざ治療の最新情報やガイドラインにも精通しています。他の診療科では得られない皮膚科ならではの専門的視点で、安心して相談できるでしょう。
当院(けんおう皮フ科クリニック)の特徴
当院で対応できる治療法や他院との連携
最新のレーザー治療設備
当院ではQスイッチレーザー(ルビーレーザーなど)やダイレーザーといった先進的なレーザー機器を備えており、青あざ・茶あざから赤あざまで幅広いレーザー治療に対応可能です。乳幼児でも安全に配慮しながら照射を行います。
内服治療は専門病院と連携
乳児の血管腫(赤あざ)で必要となるプロプラノロールなどのシロップ内服療法については、小児科専門医がいる近隣の病院と連携し、安全管理のもと治療開始します。院内での経過観察と他院での専門管理を組み合わせ、お子さんにとってベストな治療環境を整えます。
手術が必要な場合にも対応
大きな黒あざ(先天性ほくろ)等で外科的な切除手術が適切と判断される場合は、症例に応じて当院での日帰り手術を行うか、提携先の形成外科専門病院にご紹介し対応いたします。皮膚科と形成外科が協力し、手術後の傷跡ケアも含めたフォローを行います。
経験豊富な小児皮膚科専門医
当院の医師は大学病院等で小児の皮膚疾患診療に携わってきた経験を持ち、乳幼児のあざに関する相談にも豊富な知識でお答えします。保護者の不安なお気持ちに寄り添い、丁寧に診察・説明を行いますので、小さなことでも遠慮なくご相談ください。
お子さまに優しい環境
泣いてしまう赤ちゃんや小さなお子さんにもできるだけ負担をかけないよう、診察・治療を工夫しております。必要に応じて痛みを和らげる麻酔テープ・麻酔クリームの使用や、保護者の方と相談しながら治療ペースを調整するなど、お子さん第一の対応を心がけています。
あざの種類(青あざ・赤あざ・茶あざ・黒あざ)
赤ちゃんに見られる主なあざを、その色調によって「青あざ」「赤あざ」「茶あざ」「黒あざ」の4つに大別し、それぞれの特徴や経過、治療法について解説します。
青あざ(蒙古斑・太田母斑 など)
青あざは皮膚が青紫色~灰色に見えるあざで、生まれつき存在することが多いタイプです。代表例が蒙古斑(もうこはん)で、殆どの日本の赤ちゃんに見られるお尻や背中の青灰色の平坦なあざです。蒙古斑は、皮膚のメラニンを作る色素細胞(メラノサイト)が表皮ではなく真皮の深い部分に取り残されていることが原因で起こります。一見すると打撲によるあざ(いわゆる青たん)にも見えますが、痛みもなく生後すぐから存在する点で打撲とは区別できます。蒙古斑は成長とともに色が薄くなり、ほとんどの場合は学童期までに自然に消えていきます。実際、お尻の蒙古斑であれば約96~97%が10歳頃までに消失すると報告されています。ただし、お尻以外にできた異所性蒙古斑(いしょせいもうこはん)と呼ばれる青あざでは自然消退しにくい傾向があり、肩や四肢に生じたものは一部が成人後も残ることがあります。いずれの場合も健康上の問題となることはほとんどなく、経過観察で差し支えありません。なお、蒙古斑はその見た目から周囲に虐待によるあざと誤解されることがまれにありますが、小児科健診などでも周知のものですので過度に心配されないでください。
もう一つの代表的な青あざが太田母斑(おおたぼはん)です。こちらは主に顔面(片側の頬から額、まぶたにかけて)に生じる青黒いあざで、生後すぐから目立つ場合もあれば幼児期に徐々に濃くなって気づかれる場合もあります。太田母斑は蒙古斑と同じく真皮内の色素細胞による真皮メラノサイトーシスの一種ですが、自然に消えることはほとんどなく、生涯にわたり残存します。また眼球(強膜)や眼の周囲にも色素沈着を伴うことがあり、まれに緑内障などを合併することも報告されています。そのため、太田母斑は皮膚科で経過を追い、必要に応じて治療を検討すべき青あざです。同様に、肩や上背部にできる伊藤母斑(いとうぼはん)という青あざもありますが、これも自然には消退しません。
青あざに対する治療は、見た目の改善を目的として行います。蒙古斑は前述の通り大半が自然に消えるため通常治療の必要はありませんが、学童期を過ぎても残存する部位の蒙古斑や、太田母斑・伊藤母斑などはレーザー治療の有効な対象です。特にQスイッチレーザー(ルビーレーザー、アレキサンドライトレーザー、Nd:YAGレーザー等)は真皮のメラニン色素に選択的に反応し、青あざを徐々に薄くすることができます。レーザー照射は数ヶ月おきに複数回(5~10回程度)行う必要がありますが、幼児期から治療を開始することで少ない回数で高い効果が得られるとの報告もあります。実際、乳幼児期にQスイッチレーザーを開始し7回施行したところ、約99%の症例でほぼ消失するまで改善したとのデータもあります。レーザー治療による皮膚へのダメージは最小限で、安全性も確立されています(後述の「よくある質問:レーザー治療は痛い?安全?」も参照してください)。太田母斑に対するレーザー治療は日本では保険適用となっており、多くの症例で思春期前後から治療が検討されますが、症状が強い場合はもっと小さいうちから施行することもあります。治療後は一時的に色素沈着(茶色っぽい跡)が残ることもありますが、数ヶ月で薄れていきます。最新の動向として、従来のナノ秒レーザーよりさらに短いパルス幅をもつピコ秒レーザーが登場し、青あざ治療の効果向上が期待されています。ピコ秒レーザーは従来よりメラニン粒子を微細に破壊できるため、治療回数の短縮や難治例への有効性が報告されつつあります。いずれにせよ、青あざの治療は病変が浅い幼少期ほど反応が良い傾向があるため、将来的に治療を希望される場合は早めに皮膚科専門医に相談されるとよいでしょう。
赤あざ(乳児血管腫・サーモンパッチ・ポートワイン母斑 など)
赤あざは皮膚が赤やピンク色に見えるあざの総称で、主に血管の異常によって生じます。代表的な赤あざには、盛り上がった鮮やかな赤色の苺状血管腫(いちごじょうけっかんしゅ)や、平坦でピンク~赤紫色のポートワイン母斑(正式には単純性血管奇形)、新生児期に額や後頸部に見られる薄紅色のサーモンパッチ(俗称:天使のキス、ウンナ母斑)などがあります。
乳児血管腫(苺状血管腫)は、生後しばらくしてから現れる柔らかい赤いできもので、イチゴのような見た目からそう呼ばれます。出生時には目立たず、生後数週間以内に赤い斑点や小さな腫れ物として出現し、その後3~4か月頃まで急速に大きくなるのが特徴です。多くの場合、乳児血管腫は生後5~6か月で増殖が落ち着き、その後は少しずつ縮小に向かいます。約半数は生後5年、7割以上は7歳までに自然消退するとも言われ、最終的には痕跡を残さず消えるものも少なくありません。ただし、消えた後も皮膚が少したるんだり、毛細血管の拡張による赤みが残ったりするケースが全体の55~69%で報告されています。乳児血管腫は良性の腫瘍であり、多くは健康上問題を起こしません。しかし、場所や大きさによっては注意が必要です。例えば、目の周りにできた場合は視力発達への影響、鼻や口唇にできた場合は呼吸や授乳の障害、オムツが当たる場所では潰瘍(ただれ)を起こす可能性があります。また、肝臓など体内に多発する合併症(非常にまれですが「PHACE症候群」など)が隠れていることもあります。そのため、乳児血管腫が大きい場合や増殖が速い場合、機能障害の恐れがある場合は早期に皮膚科専門医の評価を受けることが勧められます。
一方、単純性血管腫(ポートワイン母斑)は、生まれつき皮膚表面に存在する平らな紅斑です。名前の通りワインをこぼしたような赤~紫の色を呈し、主に顔面や体幹に地図状に分布します。サーモンパッチ(新生児斑)と見た目が似ていますが、サーモンパッチは額や鼻根、項部の正中にでき、成長とともに薄くなっていくのに対し、ポートワイン母斑は体の片側(顔なら三叉神経領域に沿うことが多い)にでき、生涯にわたり色が残存する点が異なります。ポートワイン母斑は出生時からは淡いピンク色でも、年齢とともに色調が濃くなり紫色を帯び、皮膚が肥厚してでこぼこしてくる傾向があります。思春期以降になると結節や小腫瘤が生じ、成人期には約2/3以上の患者で皮膚の肥厚が認められるとの報告もあります。また、顔面の広い範囲(額や眼の周囲)に及ぶポートワイン母斑を有する場合、スタージ・ウェーバー症候群という脳や眼の血管奇形を伴う病態の可能性があります。これはごく一部ですが、皮膚科では必要に応じてMRI検査や眼科検査などを手配し、合併症の有無をチェックします。ポートワイン母斑自体は良性で痛みもありませんが、見た目の問題が大きく将来的に合併症が進行する可能性もあるため、早期から治療介入を検討すべき赤あざとされています。
赤あざの治療は、種類によってアプローチが異なります。乳児血管腫の場合、小さいものであれば経過観察のみで最終的に消えていくことも多いですが、前述のように機能障害の恐れがある場合や美容的・心理的な負担が大きい場合には薬物療法を行います。2008年、フランスのLéauté-Labrèze医師らの報告により、生後まもない赤ちゃんの血管腫に心臓の薬であるプロプラノロール(βブロッカー)が劇的な効果を示すことが発見されました。それ以来、プロプラノロール内服は乳児血管腫の第一選択治療として世界的に用いられています。低用量のプロプラノロールをシロップ剤で飲ませると、血管腫が硬く縮小しはじめ、数週間~数ヶ月で赤みや盛り上がりが大きく改善します。ただし、副作用として一時的な血圧低下や低血糖を起こすリスクがあるため、投与開始時は入院または管理下で慎重に量を調節します。当院でも近隣病院と連携し安全に治療を開始できる体制を整えています。外用薬による治療も近年注目されています。小さめの表面的な血管腫であれば、緑内障の点眼薬として使われるβブロッカーの一種チモロールを患部に塗る治療が有効です。チモロールマレイン酸塩液を1日数回塗布すると、数ヶ月で病変が平坦化・退色していく例が多く報告されています。この外用療法は痛みもなく副作用も少ないため、「小さな苺状血管腫にはまずチモロール外用を試みる」という流れがガイドラインにも取り入れられています。一方、単純性血管腫(ポートワイン母斑)の治療にはレーザー照射療法が最も有効です。中でもダイレーザー(PDL)は血管の多い赤いあざ治療のゴールドスタンダードです。PDLは黄色いレーザー光を瞬間的に照射し、拡張した毛細血管だけを選択的に破壊します。これにより周囲の皮膚を傷つけずにあざを薄くすることが可能です。乳幼児期から複数回のレーザー治療を行うことで、ポートワイン母斑の発達を抑え、かなり目立たなくできるケースもあります。実際、色素レーザー照射は開始年齢が早いほど有用とされ、生後早期から治療を始めたお子さんでは学童期にはほとんど分からない程度まで改善した例もあります。当院でもダイレーザー(Vビーム®)を用い、小さな赤ちゃんにも安全に照射を行っています。レーザー治療は1回では完全に消えないため、通常は数ヶ月おきに複数回(10回以上になることもあります)継続します。痛みについては後述しますが、照射時に輪ゴムで弾かれた程度の刺激があるものの、表面冷却や麻酔クリームで軽減できます。副作用として一時的な腫れや紫斑(皮下出血)が数日~1週間ほど残りますが、その後皮膚が新しく生まれ変わるにつれてあざが薄くなっていきます。
ポートワイン母斑の場合、完全に消すことは難しくとも、色調を薄く保つことで将来の肥厚や合併症を抑えられる可能性があります。加えて、海外の最新研究トピックとして、レーザー治療にシロリムス軟膏(mTOR阻害剤の一種、ラパマイシン)を併用する試みが報告されています。2018年の症例報告では、難治性のポートワイン母斑5例に対しレーザー照射後に1%シロリムス軟膏を塗布する治療を行ったところ、レーザー単独治療より短期間での著明な色調改善が得られたとされています。シロリムスには血管内皮細胞の増殖を抑える作用があり、レーザー後の再血管化を防ぐことで効果を高める可能性があります。現在、この併用療法の有効性を検証する臨床研究が進められており、近い将来治療成績の向上につながることが期待されています。
サーモンパッチ(額や項の薄紅色のあざ)については、乳幼児期には自然に目立たなくなることが多く、基本的に治療の必要はありません。額のもの(“天使のキス”)は多くが1~2歳までに消えますし、項のもの(“ウンナ母斑”)も髪で隠れてしまうため気にしないことが一般的です。ただ、学童期以降になっても残っている場合で本人が気にするようであxば、こちらもパルス染料レーザーで薄くすることが可能です。サーモンパッチは血管が浅く病変が薄いため、レーザー治療には反応しやすく、少ない回数で目立たなくできる傾向があります。
茶あざ(カフェオレ斑 など)
茶あざは皮膚が薄い茶色~カフェオレ色に見える平坦なあざで、メラニン色素の過剰沈着によるものです。代表的なのはカフェオレ斑と呼ばれるものです。名前の通りコーヒー牛乳のような淡い茶色を呈し、形は滑らかな縁取りをもつ丸いまたはだ円形のシミのように見えます。大きさは数ミリから10cm以上まで様々で、体のどの部分にも生じる可能性があります。カフェオレ斑は生まれつき一つだけ持っている赤ちゃんもいますが、乳幼児期にかけて新たに出現することもあります。成長とともに皮膚が伸びるため、あざも少し大きくなることがありますが、色調が濃くなることはあっても自然に消えることはありません。カフェオレ斑それ自体は良性で健康に影響を及ぼすことはありません。痛みやかゆみもなく、皮膚の質感も周囲と同じです。
注意すべき点は、カフェオレ斑の数と大きさです。小さいものが1~2個あるだけなら全く問題ありませんが、5つ以上のカフェオレ斑が直径5mm以上ある場合(学童期以降では6個以上かつ15mm以上)は、神経線維腫症1型(NF1)という遺伝性疾患を疑う手がかりになります。NF1の場合、思春期までに皮膚や神経に良性腫瘍が多数発生する可能性があるため経過観察が必要です。ただしカフェオレ斑だけでは確定診断ではなく、腋の下のそばかす状の色素斑や眼の虹彩結節など他の所見と組み合わせて診断されます。お子さんに多数のカフェオレ斑が見られる場合は、小児科や皮膚科で一度相談してみるとよいでしょう。それ以外のケースでは、カフェオレ斑は単なる「ほくろの仲間」と考えて差し支えありません。
美容的にカフェオレ斑を目立たなくしたい場合、レーザー治療が試みられることがあります。QスイッチルビーレーザーやYAGレーザーを照射すると、一時的にカフェオレ斑が薄くなることが多く、一部では周囲の皮膚と見分けがつかない程度になる例もあります。しかし、カフェオレ斑は再発しやすいことが知られています。レーザーで色素を破壊しても、根本的な原因(遺伝子的素因)が残っているため、1年後・数年後にまた色が戻ってくることが少なくありません。特に大きなカフェオレ斑では再発率が高いため、治療を繰り返す必要が出てくる可能性があります。また日焼けなど紫外線刺激によっても色素が濃くなることがあるため、カフェオレ斑がある部位は日焼け止めや衣服で紫外線対策をしてあげると色調悪化を防げます。レーザー以外の治療法としては、ハイドロキノンなどの美白剤の外用で薄くなることもありますが、幼児には刺激が強いこともあり慎重に判断します。いずれにせよ、医療的には治療の必要がないケースがほとんどですので、お子さん本人が気にする様子がなければ無理に治療する必要はありません。成長して思春期以降になり、本人が強い希望を持つようであれば治療を検討する、というスタンスで問題ないでしょう。
黒あざ(先天性母斑 など)
黒あざは皮膚が黒っぽく見えるあざで、一般的には先天性のほくろ(母斑細胞母斑)が該当します。生まれつき存在するホクロは大小様々で、直径1cm未満のものもあれば、体の一部を大きく覆う巨大なものもあります。小さい先天性黒あざの場合、見た目以外の問題を起こすことはまずなく、経過とともに相対的に目立たなくなることもあります(皮膚が成長して面積が広がるため、あざが小さく見えてくる)。一方、中~大型(直径数cm以上)の黒あざでは将来的に注意が必要なことがあります。先天性の黒あざはメラニンを作る母斑細胞という細胞の良性の増殖ですが、あまりに数が多かったり面積が大きかったりすると、まれにそこから皮膚がん(悪性黒色腫=メラノーマ)が発生する可能性が指摘されています。特に、生まれつき体表の広い範囲(例えば背中一面など)を覆う巨大先天性黒色母斑では、そのリスクが一生のうちに5~10%程度あるともいわれます。ただし、小さなほくろでは悪性化のリスクはごく低く、一般的には経過観察で問題ないとされています。また、大きな先天性黒あざの中には脳や脊髄の周囲にメラニン細胞が沈着する合併症(神経皮膚黒色症)を伴うケースもごく稀ですがあり、その場合は乳幼児期からけいれん等の神経症状が起こることがあります。このようなリスクの高い黒あざについては、皮膚科専門医のもとで計画的に経過を追い、必要なら早い段階で治療することが推奨されます。
黒あざの治療としては、基本的に外科的切除が第一選択です。小さいほくろであれば、局所麻酔下で皮膚をくり抜くように取って縫合すれば一度で除去できます。幼児の場合、動いてしまうため基本的には鎮静処置や全身麻酔が必要ですが、場所によってはある程度成長を待ってから切除することもあります。中型以上の黒あざになると、一度に全てを取り切ることが難しいため、数回に分割して切除したり、皮膚を伸ばすエキスパンダーという風船のような器具を皮下に入れて正常皮膚を拡張してから手術したり、といった段階的治療が行われます。巨大な黒あざでは乳児期からレーザーや外科的アプローチでできるだけ母斑細胞の量を減らしておき、その後形成外科での再建手術につなげることもあります。いずれの場合も、傷跡とリスクのバランスを考慮した治療方針の決定が重要です。傷跡が大きく残っては元のあざと取り換えたようになってしまうため、美容面の改善とリスク低減を天秤にかけ、最適解を探ります。この判断には専門的知見が必要なため、中~大型の黒あざをお持ちのお子さんは皮膚科医・形成外科医の両面から評価を受けることをおすすめします。
小さな先天性の黒あざや、小児期に新しくできたホクロについては、多くは様子見で問題ありません。ただ、徐々に大きくなったり色や形に不規則な変化が出てきたりした場合は、悪性のできものとの鑑別が必要になります。ダーモスコピーという拡大鏡で精査したり、必要に応じて部分的に切除して病理検査をすることもあります。これは大人のホクロと同様です。保護者の方が気になるホクロがあれば、小児でも判断できますのでお気軽に皮膚科にご相談ください。近年ではホクロのレーザー治療も行われるようになってきました。炭酸ガスレーザーやQスイッチレーザーでメラニンを破壊し、メスを使わずにほくろを除去する方法です。ただし、一度で完全に除去しきれず再発することも多く、特に先天性の母斑細胞は皮膚の深部に存在するためレーザーでは取り残しがちです。したがって、根本的に除去したい黒あざは手術が推奨されます。レーザー治療は、メスによる切除では傷が大きくなりすぎる顔面の複数の小さなホクロなど、美容目的で慎重に行うケースが中心です。
海外の最新研究では、巨大先天性母斑の原因となる遺伝子(NRAS変異など)が解明されつつあり、将来的には遺伝子を標的とした治療法の開発も期待されています。しかし現時点では確立した薬物療法はなく、やはり外科的に除去する以外に根本的リスク低減策はありません。皮膚科領域では悪性黒色腫に対する新しい免疫療法薬なども登場していますので、仮に将来黒あざから悪性が生じた場合でも治療の選択肢は確実に広がってきています。不安に感じすぎる必要はありませんが、定期的なチェックだけは怠らないようにしましょう。
日常生活で気をつけたいポイント
赤ちゃんのあざと共に生活する上で、知っておいていただきたいポイントをまとめます。
日光による色素沈着に注意
あざの部分は紫外線の影響を受けやすいことがあります。特に茶あざ(カフェオレ斑)やレーザー治療後の部位では、強い日差しに当たると色が濃くなったり周囲とのコントラストが増す可能性があります。お散歩や外遊びの際は、帽子や日傘を利用したり日焼け止めクリームを塗るなどして適度に紫外線対策を行いましょう。皮膚が弱い赤ちゃんには低刺激のベビー用日焼け止めを使い、汗をかいたらこまめに拭いて落としてあげてください。
こすったり傷つけないようにケア
あざの部分を強く擦ったり引っかいたりすると、出血したり潰瘍を起こしたりする恐れがあります。血管腫(赤あざ)は特に擦れる刺激でただれやすいため、おむつや衣服が当たる部分にある場合はガーゼを当てるなどして保護しましょう。爪を短く切り整えておくことも有効です。石鹸で洗う時もゴシゴシ擦らず、泡で優しく洗い流す程度で十分です。保湿剤を適度に塗って皮膚のバリアを保つことも、間接的にあざ部分をトラブルから守ることにつながります。
経過を記録し、変化を見逃さない
お子さんのあざの大きさ・色・厚みの変化には注意を払いましょう。定期的に写真を撮っておくと、少しずつの変化も把握しやすくなります。急に大きくなった、色が濃くなった、表面がただれてきた、出血した、といった変化に気付いた場合は早めに医師に相談してください。特に黒あざの場合、色調のムラや形のいびつさ、急激な隆起などは重要なサインです。また赤あざが破れて潰瘍になった場合は感染のリスクがありますので清潔に保ち、受診して処置を受けましょう。
周囲の人への説明・配慮
赤ちゃんの目立つあざについて、周囲から心無い言葉をかけられることも残念ながらあります。お子さん本人が小さいうちは親御さんが気に病んでしまうかもしれませんが、「将来治療で良くなるものだから大丈夫」と前向きに伝えるようにしましょう。保育園や幼稚園などお子さんを預ける際にも、あらかじめ保育士さんにあざのことを説明しておくと安心です。蒙古斑であれば虐待との誤解を防ぐことにもなります。
よくある質問(FAQ)
-
- 赤あざは放っておいても自然に消えますか?
-
赤あざにも種類があります。乳児血管腫(苺状血管腫)であれば、上記の通り多くは幼児期までに自然に縮小・消退します。一方、単純性血管腫(ポートワイン母斑)は自然には消えず、生涯残存します。サーモンパッチは成長とともに薄くなるものが多いです。このようにタイプによって経過が異なります。専門医であざの種類を診断してもらい、「経過観察でよいもの」か「早めに治療すべきもの」か評価してもらうことをおすすめします。放置して問題ないあざも多いですが、適切なタイミングで治療すればよりきれいに治るあざもありますので、まずは皮膚科で相談してください。
-
- 赤ちゃんのあざは痛がったり痒がったりしますか?
-
通常、あざそのものが痛んだり痒くなったりすることはほとんどありません。血管腫や色素斑自体は皮膚の一部が変色しているだけで、赤ちゃんにとって痛みを感じるものではないからです。ただし例外的に、苺状血管腫が大きくなって表面に潰瘍ができると痛みを伴うことがあります。この場合は赤ちゃんが患部を気にして触ったり泣いたりするので気付きます。そのような潰瘍が起きた際には早めに受診して治療しましょう。基本的にはあざ=痛いものではないので、触れてしまっても過度に心配はいりません。痒みも通常ありませんが、乾燥など他の要因で周囲の皮膚が痒い場合は掻き壊さないよう注意してください。
-
- レーザー治療は小さい赤ちゃんにとって安全ですか?痛みはありませんか?
-
レーザー治療は乳幼児にも安全に行える治療法です。実際、苺状血管腫やポートワイン母斑の治療に生後数ヶ月の赤ちゃんからレーザー照射を行うことは世界中で一般的に行われています。レーザーの種類にもよりますが、例えば当院のVビーム®は照射の瞬間に皮膚を冷却するスプレーが出る仕組みになっており、痛みや熱傷リスクを最小限に抑えています。痛みの感じ方としては、輪ゴムではじかれたような一瞬の刺激がある程度です。小さいお子さんの場合、照射時に驚いて泣いてしまうことはありますが、長く続く痛みではありません。必要に応じて事前に麻酔クリームを塗布したり、年長児であれば笑気麻酔(鼻から吸う鎮静法)を併用することもできます。ほとんどの乳児は麻酔なしでも短時間であれば施術可能です。安全面についても、適切なエネルギー設定で行えば皮膚に跡が残るリスクは極めて低く、長年の臨床実績があります。当院でも赤ちゃんのレーザー治療に細心の注意を払いながら取り組んでおり、多くのお子さんがトラブル無く治療を受けています。
-
- あざの治療費は保険でまかなえますか?
-
日本の公的医療保険では、医療上必要と認められるあざの治療は保険適用となります。例えば、視力障害の恐れがある血管腫のプロプラノロール内服や、顔面の広範な単純性血管腫に対するレーザー治療などは保険診療で行われます。この場合、0歳~小学生までは乳幼児医療助成の対象となり自己負担が軽減される自治体も多いです。一方、明確な医学的適応がなく美容目的と判断される治療(例:小さなカフェオレ斑を完全に消したい場合のレーザー治療など)は自費診療になる可能性があります。また、保険適用外の最新治療(美容皮膚科的な位置づけの治療)を希望される場合も自費となります。実際の適用可否は診察時に医師が判断し、費用についても事前に説明がありますので、不安な点は遠慮なくご質問ください。
-
- 将来的にあざががん化することはありませんか?
-
大部分のあざは、将来がん(悪性腫瘍)になる心配はほとんどありません。血管腫(赤あざ)は良性の血管の増殖であり、がんとは無縁です。青あざや茶あざも、皮膚の色素沈着であって悪性化するものではありません。ただし、ごく一部に例外があります。先述の大型の先天性黒あざ(ほくろ)では、将来皮膚がん(悪性黒色腫)を発生するリスクがわずかながらあります。特に巨大なものだと5~10%と報告されています。このため、大きな黒あざは予防的に切除することが検討されます。また、乳幼児期にはほとんど問題とならなくても思春期以降に皮膚がんのリスクが増す疾患(例:色素性乾皮症など)は特殊なケースとして存在します。しかし、そうした例は非常に稀です。基本的には担当医がリスクの有無を把握して経過を見ていますので、過度に心配しすぎる必要はありません。逆に、「このあざは将来大丈夫なのかしら?」といった疑問や不安があれば、遠慮なく医師にお尋ねください。専門医は最新の知見に基づいてリスク評価し、必要な対策を講じます。
-
- 赤ちゃんのあざは母親の何かが原因でしょうか?妊娠中に予防する方法はありましたか?
-
いいえ、お母さんのせいではありませんし、防ぎようもありません。妊娠中の行動や体調と赤ちゃんのあざには因果関係がありません。冒頭で触れたような「母親が○○したからあざができる」という俗説は世界中にありますが、いずれも科学的には否定されています。赤ちゃんのあざは偶然に起こるもので、だれの責任でもありません。また現在の医学では、妊娠中に特別なケアをしてあざの発生を予防することもできません。お腹の中で一生懸命育っている赤ちゃんが、ほんのちょっと皮膚の色素や血管の配置にむらを作って生まれてきた――それがあざの正体です。どうかご自身を責めないでください。そして生まれてきたお子さんの個性の一つとして受け止め、必要があれば生まれた後に適切な対処をしてあげましょう。
-
- 治療は何歳から始めるのが良いでしょうか?
-
あざの種類と重症度によります。苺状血管腫(乳児血管腫)の場合、リスクが高い例では生後1か月齢からでもプロプラノロール内服を開始することが推奨されています(米国小児科学会ガイドライン2019年)。早い段階で治療を始めることで、潰瘍や瘢痕形成を防ぎ、よりきれいに治すことが期待できます。単純性血管腫(ポートワイン母斑)に対するレーザー治療も、生後数ヶ月から開始可能です。実際、乳児期早期にレーザーを開始したほうが少ない回数で大きな効果が得られるとの報告があります。一方で、蒙古斑のように放っておいても消えるものは治療の必要がありませんし、小さなホクロを将来的にどうするかは成長を見てから判断すれば良い場合もあります。大切なのは早めに専門医に相談し、あざの種類ごとに適切なプランを立てることです。必要な場合は乳児期から治療を開始しますし、経過を見てよいものは定期フォローの計画を立てます。タイミングを逃さないためにも、「こんな月齢で受診していいのかな?」と迷わず、気付いた段階で皮膚科を受診されることをおすすめします。
まとめ
赤ちゃんのあざは、多くの場合心配のないものとはいえ、やはり保護者の方にとっては不安や疑問の種になることでしょう。
「このまま消えるのかな?」「治療するとしたらいつ、どこで?」「将来いじめられないかな?」──そうした悩みを一人で抱え込む必要はありません。是非当院を受診してください。
当院では小児の皮膚疾患に詳しい皮膚科専門医が、赤ちゃんのあざについて丁寧に診察・説明いたします。最新の知見に基づいた正確な情報提供を心がけており、必要な治療があれば適切なタイミングで開始します。また当院で対応できない高度な治療が必要と判断すれば、信頼できる連携先の医療機関をご紹介し、引き続き診療をフォローいたします。「何もしなくても大丈夫」という場合には、その旨を明確にお伝えし経過のモニタリング方法を一緒に確認します。いずれにせよ、受診して頂くことで今後の方針がはっきりし、漠然とした不安が和らぐはずです。赤ちゃんの大切なお肌のことですから、少しでも気になることがあれば遠慮なく当院にご相談ください。
私たちは地域の身近な皮膚科医療機関として、お子さまの健やかな成長を皮膚の面からサポートしたいと願っています。保護者の方と二人三脚で、お子さまにとって最善のケアを提供できるよう努めてまいります。一緒にお子さんの肌を見守っていきましょう。どうぞお気軽にご来院ください。