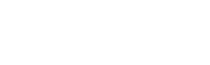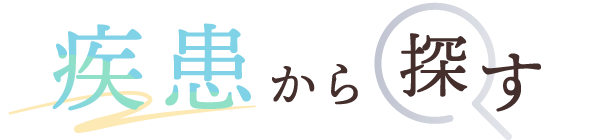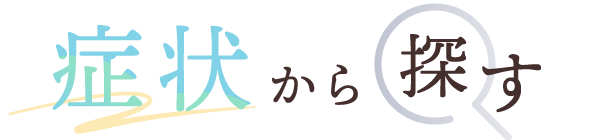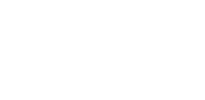- HOME
- 子どものとびひ
とびひ(伝染性膿痂疹)とは
「飛び火」の由来
昔からある寓話で、ひとつの家の火事が火の粉となって隣の家へ燃え移り、町全体に広がってしまった…という話を聞いたことはありませんか?
実は、子どもの皮膚の病気「とびひ(伝染性膿痂疹)」もそれに似ています。最初は虫刺されや小さな傷だったところが、あっという間に周りに広がってしまう様子がまるで“火事の飛び火”のようだということで、この名前がつきました。
とびひは主に細菌による皮膚の感染症です。黄色ブドウ球菌や溶連菌(A群溶血性連鎖球菌)といった細菌が皮膚の傷口や湿疹に入り込んで増殖し、水ぶくれや膿(うみ)のたまった発疹を引き起こします。それが破れて液が出ると、その液に含まれた細菌が別の場所に付着して新たな発疹が生まれます。こうして火の粉が飛ぶように次々と広がるのが最大の特徴です。特に乳幼児から小学生くらいの子どもによくみられる病気ですが、皮膚の弱い状態にある時は大人でも発症することがあります。
具体的な症状と年齢別の特徴
典型的な症状の流れ
とびひは初期症状から進行まで特徴的な経過をたどります。最初は皮膚の一部に赤いポツポツや小さな水ぶくれが現れます。例えば、虫刺されやあせものようなぶつぶつをお子さんがかき壊してしまった後、その部分が赤くただれて小さな水ぶくれになることがあります。それが次第に大きくなり、中に黄色い膿がたまった膿疱(のうほう)になります。膿疱はやがて薄い膜が破れて膿が出てきて、患部はただれた状態(びらん)になります。その上に黄色~茶色のかさぶたができるころ、周囲の皮膚にはまた新しい水ぶくれができ始めます。
こうして治りきる前に次々と新たな発疹が生まれ、適切に治療しないとどんどん広がっていくのです。お子さんは患部に痛みやかゆみを訴えることがあり、触ると熱っぽく腫れていることもあります。症状が強い時には近くのリンパ節(例えば耳の下や股の付け根)が腫れて痛むこともありますが、全身の発熱を伴うことはまれです。
年齢別の特徴
とびひはどの年齢でも起こりえますが、年齢によって出やすいパターンがあります。特に乳児(赤ちゃん)では、水ぶくれができるタイプのとびひ(水疱性膿痂疹)になりやすいとされています。おむつで覆われる部分や首の周り、脇の下など蒸れやすい場所に大きめの水ぶくれができ、皮膚が薄いためすぐに破れてしまうことが多いです。一方、幼児~小学生になると、鼻の下や口の周り、腕や脚など露出した部分にできることが増えます。これは、子どもが外で遊ぶ中で擦り傷や虫刺されを作り、それを引っ掻いてしまうことや、鼻を頻繁に触るクセによって菌が顔まわりに広がりやすいためです。園児・学童では友達同士で触れ合う機会も多く、集団生活の中で流行するケースもあります。
また、この年代のとびひはかさぶたが厚くなるタイプ(痂皮性膿痂疹)が多い傾向があります。厚いかさぶたがポロポロ剥がれ落ち、新しいかさぶたが下に次々できるため治りに時間がかかることがありますが、適切にケアすれば跡を残さず治癒します。
季節による傾向
とびひは一年中発症しますが、特に夏場(7~8月)に患者さんが急増します。暑くて湿度が高く、汗や虫刺されが増える夏は菌が繁殖しやすく、肌もダメージを受けやすいためです。
なぜとびひになるのか?
原因となる菌
前述のとおり、とびひの原因は主に細菌感染です。健康な皮膚にも常在菌といって普段からさまざまな細菌が存在しています。その中の黄色ブドウ球菌や溶血性連鎖球菌(ようれんきん)といった菌が、皮膚の表面にある小さな傷から入り込み増えることで炎症を起こします。とびひの患部からはこれらの菌が検出されることがほとんどで、まれに両方の菌が混合していることもあります。
夏に多い理由
とびひが夏に流行しやすいのは、暑さと湿気で皮膚が蒸れ、汗をかき、虫刺されやあせもが増えるためです。子どもの肌は大人より薄く弱いため、夏場に汗疹(あせも)や虫刺されを掻き壊してしまうと、そこから菌が入りとびひに発展してしまうことがよくあります。逆に冬場は空気が乾燥し菌の繁殖が抑えられること、厚着で肌が直接触れ合う機会が減ることから、相対的に発症が少なくなります。
子ども特有の行動
小さなお子さんには無意識に肌を触ってしまう習慣があります。例えば、鼻をほじるクセがある子の場合、鼻の入口(鼻孔周囲)の皮膚からとびひが始まることが多いです。鼻の中は常在菌の宝庫で、ブドウ球菌が住み着いていることもあります。そこを触った指で身体の他の部位(汗疹や虫刺され跡など)を掻くことで、菌が運ばれてとびひが発生・拡大してしまうのです。また、子どもは爪で肌を引っ掻きがちです。爪の間にも菌が潜みやすく、掻き壊した傷から感染しやすくなります。保育園や幼稚園など集団生活では、おもちゃの共有やスキンシップで直接他の子に触れる機会も多いため、一人がとびひになると周囲のお子さんに次々と飛び火してしまうことがあります。
なぜ皮膚科なのか? ― 他の診療科との違い ―
皮膚科で診る意義
とびひは小児科でも対応することがありますが、皮膚の専門医である皮膚科では、より正確な診断と専門的な治療が可能です。皮膚科医は発疹の特徴を見極めて、とびひなのか他の病気(たとえば水ぼうそうや湿疹の悪化など)なのかを判断する専門知識と経験があります。また必要に応じて、膿や水ぶくれの内容を綿棒で採取して細菌検査(培養検査)を行い、原因菌を特定することもできます。
これにより抗生剤(抗菌薬)が効いているか確認したり、まれにある耐性菌(薬の効きにくい菌)への対応も的確に行えます。皮膚科では、症状の程度に応じて外用薬と内服薬の使い分けや、患部の適切な処置方法についても詳しく指導できます。他の科よりも肌のケア(洗い方や保湿など)に重点を置いた指導ができるのも皮膚科ならではです。
とびひは再発しやすい病気でもあるため、皮膚科で今後繰り返さないための予防策まで含めたケアを受けることが、お子さんの肌を守るうえで大切です。
当院(けんおう皮フ科クリニック)の特徴
― 当院でしかできない治療アプローチ ―
当院では、とびひの治療においてお子さまと保護者の方に安心していただけるよう、以下のような独自の取り組みを行っています。
最新の外用薬を積極的に採用
症状に合わせて効果の高い塗り薬をいち早く使用し、初期の段階で感染の拡大を食い止めます。必要に応じて抗生剤の内服も検討し、適切な治療を逃しません。とびひの治療は通常、限られた範囲であれば抗菌薬の塗り薬で行い、症状が強かったり広がっている場合は飲み薬を併用します。
原因菌の特定と的確な診断
症状が重い場合や繰り返す場合には、膿や水ぶくれからサンプルを採取して細菌培養検査を行い、原因となっている菌を確認します。それにより最適な抗生剤を選択し、無駄のない治療につなげます。
丁寧なスキンケア指導(バリアケア)
看護師と連携し、ご自宅での患部の洗い方・薬の塗り方を丁寧に指導します。特に小さなお子さんの場合、保護者の方によるケアが重要なので、不安なく処置できるようサポートします。
迅速な診断と処置体制
予約制と緊急時対応を組み合わせ、症状がひどくなる前に受診しやすい環境を整えています。当院では受診当日に処置と薬の開始までスムーズに行える体制を整え、早期治療に努めています。
再発防止への取り組み
治療時に、なぜとびひが起きたのかを一緒に振り返り、今後の予防策(肌を清潔に保つ工夫や爪を短くする習慣づけなど)についてもアドバイスします。同じことを繰り返さないよう、保護者の方と二人三脚でお子さんの肌を守ります。
治療法
抗菌薬の塗り薬(外用療法)
とびひの治療の第一選択は抗菌作用のあるお薬の塗布です。患部を清潔にした上で、ブドウ球菌・溶連菌に効果のある抗生物質の入った軟膏やクリームを1日数回塗ります。局所的なとびひのほとんどは、塗り薬だけで治癒が可能です。処方されたお薬は指示された期間きちんと使い切ることが大切です。途中でやめると菌が残って再発したり、耐性菌が育つ原因になります。
抗菌薬の飲み薬(内服療法)
発疹の数が多い場合や広範囲に広がっている場合、あるいは発熱を伴うようなケースでは、飲み薬の抗生物質を併用します。子どもの体重や年齢に合わせて適切な種類・容量の抗生剤を処方します。抗生剤の内服により、体の内側から菌を抑え込んで早期に治すことが期待できます。だいたい飲み始めて1~2日ほどで新しい発疹が出なくなり、徐々に治癒に向かいます。
患部のケア
薬を使うと同時に、患部を清潔に保つことが重要です。毎日入浴して皮膚を清潔にし、やわらかくふやけたかさぶたは無理のない範囲で洗い流します。こうすることで薬が患部に浸透しやすくなります。入浴後は清潔なタオルで水気を押さえるように拭き、すぐに薬を塗ってガーゼなどで保護します。
痒みや炎症への対処
とびひには基本的にステロイド外用薬(炎症を抑える塗り薬)は用いませんが、周囲の湿疹や掻き壊しを防ぐ目的で弱めのステロイドが併用されることもあります。また、かゆみが強い時は抗ヒスタミン薬の内服を短期間用いて掻かないようにすることもあります。
合併症への対応
通常は適切な治療で数日~1週間程度で改善しますが、治療が遅れ重症化すると蜂窩織炎(ほうかしきえん:皮膚の深い部分の感染)などを起こすことがあります。ごくまれに、とびひの原因菌である溶連菌が腎臓に影響して急性糸球体腎炎という腎臓病を発症する例も報告されています 。こうした合併症は稀ですが、適切な治療で予防するためにも自己判断せず受診することが大切です。
日常生活で気をつけるポイント
とびひの治療中および予防のために、家庭で以下のような点に注意しましょう。
毎日入浴して清潔に
とびひだからといってお風呂に入らないのは逆効果です。特に夏は汗を流すことも兼ねて、毎日入浴して肌を清潔に保ちましょう。せっけんの泡でやさしく患部を洗い、こすりすぎないようにします。ただし、他の家族と一緒の湯船に浸かるのは避け、最後に短時間入浴するか、シャワーでさっと流す程度にしましょう。入浴後は患部をしっかり薬で処置し、ガーゼや絆創膏で覆っておくと安心です。
爪を短く、触らない工夫
お子さんの爪はこまめに切り揃えましょう。患部を掻きむしると菌が爪に入り込み、他の部位に広げる原因になります。小さいお子さんには「触っちゃダメだよ」と言っても難しいですが、ガーゼや包帯で覆ったり、就寝時に手袋をするなど物理的に触れさせない工夫も有効です。
タオルや衣類の管理
とびひの菌はタオルや衣服を介して他の人にうつる可能性があります。患児が使ったタオルは家族と別にし、一回使用したら洗濯するようにしましょう。他の兄弟とタオルを共有しないことはもちろん、寝具や衣類もこまめに取り替えて清潔に保ちます。洗濯物は通常の洗剤で構いませんが、しっかり乾燥させることが大切です。
鼻をほじらない・舐めない
鼻や口周りからとびひが広がるのを防ぐため、鼻ほじりのクセがある子には都度注意してやめさせるようにしましょう。小さい子は難しいですが、絵本などで「ばい菌さんがいるから、お鼻は触らないよ」と教えるのも一つの方法です。また、乳児の場合はとびひの部分を舐めてしまわないようにミトンをしたりガーゼで覆ったりして対策しましょう。
保育園・学校での対応
とびひと診断されたら、登園・登校前に患部をガーゼなどで覆い、先生に伝えておきましょう。園や学校でもプール遊びを控える、タオルを別にするなど配慮してもらいます。広範囲に広がっている場合や治療開始直後は、医師と相談の上でお休みすることも検討してください(詳しくは後述のQ&A参照)。
よくある質問
-
- 自然に治りますか?
-
時間はかかりますが自然治癒もありえます。とびひは適切に治療しなくても数週間経てばかさぶたになり治ることもあります。実際、非水疱性のとびひ(厚いかさぶたができるタイプ)は通常2週間ほどで自然に治癒すると報告されています。しかし、治療をしないままでいるとその間に患部がどんどん広がってしまったり、他のお子さんにうつしてしまう恐れがあります。また、かゆみや痛みでお子さんがつらい思いをする時間も長引いてしまいます。抗生剤による治療を行えば、症状の拡大を防いで治癒を早めることができます。とびひは感染症ですので、できるだけ早めに適切な治療を受けることをおすすめします。
-
- お風呂に入っていいですか?
-
入浴はむしろ推奨されます。前述のとおり、患部を清潔に保つことが治りを早めますので、基本的に毎日お風呂に入れてあげてください。ただし、患部をゴシゴシ洗うのは逆効果です。石けんの泡でやさしく撫で洗いし、シャワーで流す程度にしましょう。湯船に浸かるときは他のきょうだいとは別にし、最後に短時間浸かるかシャワー浴が無難です。入浴後は薬を塗ってガーゼで覆えば、服やシーツへの菌の付着も防げます。
-
- 他の子にうつりますか?
-
はい、とびひは非常にうつりやすいです。とびひは病変部に触れた手指を介して接触感染します。他のお子さんの肌にその手で触れると、そこから新たなとびひが発生してしまいます。実際、皮膚科の正式名称が「伝染性膿痂疹」と言われるほど伝染力が強い感染症です。保育園や幼稚園でもとびひが出ると広がりやすいので注意が必要です。ただし、咳やくしゃみで空気感染するものではありませんので、患部をしっかり覆っていれば日常生活で極端に神経質になる必要はありません。家庭内ではタオルや衣類の共有を避け、こまめな手洗いで対応しましょう。
-
- 保育園や学校は休ませるべきですか?
-
症状の程度によります。とびひは学校伝染病(三類)に指定されており、広がり方によっては出席停止の対象になります。基本的には皮膚科を受診して治療を始め、患部をガーゼや包帯で覆って露出しないようにしていれば通園・通学が可能とされています。医師から「登校(園)許可」を出してもらえるケースも多いです。ただし、発疹が全身に多発していたり、発熱など全身症状がある場合は無理をせずお休みした方がよいでしょう。園や学校にはとびひで治療中であることを伝え、プール遊びを控える、タオルを別にするなど配慮してもらってください。
-
- 薬はどのくらいで効きますか?
-
早ければ2〜3日で効果が現れます。適切な抗生剤が効けば、治療開始から2日ほどで新しい発疹が出現しなくなり、患部のかゆみや痛みも和らいできます。塗り薬の場合も、こまめに続けて塗れば治りが早まります。だいたい1週間から10日程度でほとんどの症状が治まるのが一般的です。もちろん個人差があり、症状の範囲や重さによって完治までの期間は異なります。処方された薬は医師の指示通りに最後まで使い切るようにしましょう。途中で勝手に中断すると、菌が生き残って再び悪化したり、薬が効きにくい菌が残ってしまうことがあります。
まとめ
夏場になると、「あれ?うちの子、また虫刺されを掻き壊しちゃったかな?」と思っているうちに、ポツポツが増えてじゅくじゅくしたかさぶたが広がってきて驚かれる保護者の方も多いでしょう。とびひは放っておいても治る場合がありますが、短期間で広がるため早めのケアが肝心です。お子さんの「いつもの湿疹とちょっと違う」「治りが悪いな」と感じたら、どうぞお気軽に当院にご相談ください。
当院では皮膚科専門医が診察し、お子さんの肌の状態を的確に判断します。痛がる処置は極力避け、なるべく笑顔で帰れるようなお子さんに優しい対応を心がけています。また、治療の際には必ず保護者の方に経過やケア方法を丁寧に説明し、不安や疑問を解消していただけるよう努めています。
とびひはきちんと治せば怖くありません。再発予防のポイントも含めてサポートいたしますので、安心して受診してください。