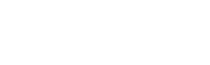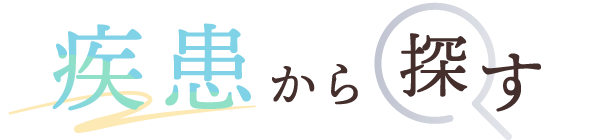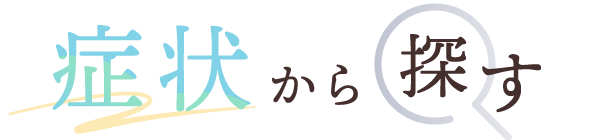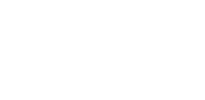- HOME
- 子どもの手足口病
手足口病とは
手足口病は、主に5歳以下の乳幼児に多く見られる、感染力の強いウイルス性の病気です。その名前の通り、口の中、手のひら、足の裏などに特徴的な発疹が現れるのが主な症状です。一般的には比較的軽症で、7日から10日程度で自然に治ることが多いとされています。しかし、まれに合併症を引き起こす可能性もあるため、注意が必要です。
手足口病の歴史と流行
手足口病が初めて医学文献に記載されたのは、1950年代のカナダでの集団発生の後でした。その後、1959年のアメリカでの流行を経て、「手足口病」という病名が確立されました。1990年代後半からは、アジア太平洋地域で大きな流行が見られるようになり、特にエンテロウイルス71(EV71)によるものが注目されました。1997年にはマレーシア・サラワクで、1998年には台湾で多数の死亡例を含む大規模な流行が発生しています。近年では、コクサッキーウイルスA6(CA6)も主要な原因ウイルスの一つとして認識されており、2011年と2013年には大きな流行が報告されています。このように、手足口病の原因となるウイルスは時代や地域によって変化しており、継続的な調査と理解が重要です。
日本においては、手足口病は夏に流行する代表的な病気の一つで、特に7月下旬に患者数のピークを迎える傾向があります。国立感染症研究所の感染症発生動向調査によると、手足口病は4歳くらいまでの幼児を中心に発症しやすく、特に2歳以下のお子さんが半数を占めています。しかし、小学生の間でも流行が見られることがあります。多くの場合、学童期以降の年齢層では、過去の感染によって免疫を獲得しているため、発症は少ないと考えられています。
2024年には、日本全国で手足口病の患者数が大幅に増加し、過去数年で最大の流行となりました。特に第19週以降、定点医療機関あたりの報告数は過去10年間で最多を記録しており、三重県、埼玉県、富山県などで高い報告数が見られました。ただし、第28週をピークにその後減少傾向にあります。このように、手足口病の流行状況は年によって大きく変動するため、最新の情報に注意することが大切です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 典型的な流行時期 | 夏(特に7月) |
| 主な罹患年齢層 | 4歳以下の幼児(特に2歳以下が半数) |
| 最近の大きな流行 | 2024年(過去数年で最大規模) |
| 主な原因ウイルス(近年) | コクサッキーA6、コクサッキーA16、エンテロウイルス71 |
| サーベイランス |
全国約3,000カ所の小児科定点医療機関から週単位で報告 |
手足口病の原因:ウイルスとその感染経路
手足口病は、主にエンテロウイルス属に属する複数のウイルスによって引き起こされます。代表的なウイルスには、コクサッキーウイルスA群(A16、A6、A10など)やエンテロウイルス71(EV71)などがあります。これらのウイルスは、主に以下の経路で人から人へと感染します。
糞口感染
感染者の便に含まれるウイルスが口に入ることで感染します。
経口感染
感染者の唾液などを介して直接感染します(例:キスや食器の共有)。
飛沫感染
感染者の咳やくしゃみによって飛び散ったウイルスを含む飛沫を吸い込むことで感染します。
接触感染
発疹の水疱に含まれる液体に直接触れることで感染します。
感染力が最も強いのは、発症後1週間以内とされています。しかし、症状が治まった後も、特に便の中には数週間ウイルスが排出されることがあります。潜伏期間は通常3日から6日程度です。このように、比較的長い期間ウイルスが排出される可能性があるため、感染予防には注意が必要です。
子供の手足口病の症状
手足口病の初期症状としては、軽い発熱(通常38℃以下)、のどの痛み、全身のだるさなどが見られます。食欲不振や、口の中の痛みによる哺乳不良なども見られることがあります。
特徴的な発疹は、発熱から1~2日後に現れることが多いです。手のひら、足の裏、口の中によく見られますが、おしり、ひじ、ひざなどにも現れることがあります。発疹は、小さな赤い斑点や少し盛り上がった赤い発疹として始まり、その後、中心が白っぽく見える水疱(水ぶくれ)になることが多いです。水疱自体はあまり痒みを伴いませんが、口の中の水疱は破れて潰瘍(口内炎)になり、強い痛みを引き起こすことがあります。
年齢別の特徴
乳幼児
口の中の痛みが強いため、よだれが増えたり、ミルクや食事を嫌がったりすることがあります。脱水症状を起こしやすいので、注意が必要です。
年長児
のどの痛みや口の中の痛みを訴えることができます。コクサッキーウイルスA6による感染の場合、発疹がより広範囲に及ぶことがあります。
すべてのお子さんにこれらの症状がすべて現れるわけではありません。ご心配な場合は、自己判断せずに医療機関を受診してください。コクサッキーウイルスA6による手足口病では、従来の発疹部位だけでなく、体幹や四肢、顔面にも水疱が見られることがあり、水疱も比較的大きい場合があります。水疱の中央にくぼみが見られることもあります。
皮膚科で手足口病を診るメリット
手足口病は小児科で診断・治療されることが多い病気ですが、皮膚科専門医は皮膚の病気に特化した専門知識を持っています。手足口病の診断は、特徴的な皮膚の発疹に基づいて行われるため、皮膚科医はその専門性を活かして正確な診断を行うことができます。また、手足口病とよく似た他の皮膚疾患との鑑別も得意としています。
皮膚科医は、発疹やかゆみなどの皮膚症状の管理についても適切なアドバイスや治療を提供できます。さらに、手足口病後に起こりうる爪の異常(爪甲脱落症)など、皮膚に関連する合併症についても知識があり、親御さんの不安を軽減し、適切な指導を行うことができます。
けんおう皮フ科クリニックでの治療アプローチ
手足口病に対する特効薬はなく、治療は症状を和らげるための対症療法が中心となります。当院では、以下の点に注意しながら診療を行っています。
水分補給
口の中の痛みで水分摂取が困難になることがあるため、脱水症状を防ぐために、冷たい飲み物や刺激の少ない飲み物を少量ずつ頻繁に摂るよう指導します。酸味や熱い飲み物は避けるようにしましょう。
痛み止め
発熱や口の中の痛みに対しては、必要に応じてアセトアミノフェンやイブプロフェンなどの市販の解熱鎮痛剤の使用を検討します(お子様にはアスピリンは使用しません)。
食事
口内炎がある場合は、柔らかく、刺激の少ない食事(おかゆ、うどん、ゼリーなど)を勧めています。
口腔ケア
口の中を清潔に保つために、食後にぬるま湯や生理食塩水で優しくうがいをするよう指導します。
当院で導入している医療機器のうち、手足口病の症状緩和や合併症予防に直接的に用いられるものはありません。しかし、二次的な皮膚症状や合併症が生じた場合には、必要に応じて適切な治療法をご提案させていただきます。例えば、細菌感染を伴う場合には外用薬を使用したり、炎症が強い場合には内服薬を検討したりすることがあります。
手足口病の一般的な管理と家庭でのケア
手足口病のほとんどは自然に治る病気ですが、ご家庭での適切なケアが大切です。
安静と休息
十分な睡眠をとり、安静に過ごしましょう。
水分補給
脱水症状を防ぐために、こまめに水分を補給しましょう。
口内炎のケア
冷たい食べ物や飲み物を与え、刺激の少ない食事を心がけましょう。酸味や塩分の強いもの、熱いものは避けましょう。
発疹のケア
発疹は清潔に保ち、無理に触ったり、潰したりしないようにしましょう。必要に応じて、医師の指示に従い外用薬を使用します。
爪のケア
コクサッキーウイルスA6感染後には、数週間から数ヶ月後に爪が剥がれることがありますが、通常は自然に治りますのでご安心ください。剥がれかけた爪は無理に剥がさず、清潔に保ちましょう。
手足口病の合併症
手足口病は通常軽症で経過しますが、まれに以下のような合併症を引き起こすことがあります。
髄膜炎
発熱、頭痛、首の痛みなどが現れます。
脳炎
意識障害やけいれんなどが起こることがあります。
急性弛緩性麻痺(AFP)
手足に力が入らなくなることがあります。
脱水症状
口の中の痛みで水分が十分に摂れない場合に起こります。
心筋炎
まれに心臓の筋肉に炎症が起こることがあります。
肺水腫
肺に水分が溜まることがあります。
ごくまれに
特にEV71感染の場合には死亡例も報告されています。
これらの症状が見られた場合は、速やかに医療機関を受診してください。
手足口病の予防
現時点では、日本国内で手足口病を予防するためのワクチンはありません。ただし、中国や台湾、タイなど一部のアジアの国では、エンテロウイルス71(EV71)に対するワクチンが利用可能です。予防の基本は、日頃からの衛生習慣をしっかり守ることです。
手洗い
石けんと流水で、少なくとも20秒以上、丁寧に手を洗いましょう。特に、トイレの後、おむつ交換の後、食事の前、咳やくしゃみをした後
などは必ず洗いましょう。アルコール消毒液も有効です。
手指消毒
アルコール消毒液などで手指を消毒するのも効果的です。
うがい
外から帰った時や、のどの痛みがある時は、うがいをしましょう。
咳エチケット
咳やくしゃみをする際は、ティッシュや袖で口と鼻を覆いましょう。
共有を避ける
タオルや食器など、他人との共有は避けましょう。
環境の消毒
ドアノブやスイッチ、おもちゃなど、よく触る場所は定期的に消毒しましょう。
感染者との接触を避ける
流行期には、できるだけ人混みを避け、感染が疑われる人との接触を控えましょう。
排泄物の処理
おむつ交換の際などは、排泄物を適切に処理し、その後は必ず手を洗いましょう。
換気
部屋の空気を定期的に入れ替えましょう。
手足口病にかかったお子さんは、熱が下がり、口の中の水疱が治るまでは、保育園や幼稚園、学校を休ませましょう。
よくある質問
-
- 自然に治りますか?
-
はい、ほとんどの場合、7~10日程度で自然に治ります。
-
- 市販薬で対応できますか?
-
発熱や痛みに対しては、市販の解熱鎮痛剤を使用できますが、基本的な治療は対症療法です。
-
- すぐに受診すべきですか?
-
生後6ヶ月未満のお子さん、免疫力が低下しているお子さん、脱水症状が見られる場合、高熱が続く場合、症状が重い場合、または10日以上症状が改善しない場合は、医療機関を受診してください。
-
- 動物の病気である口蹄疫と同じですか?
-
いいえ、手足口病はヒトの病気であり、口蹄疫は主に牛や豚などの動物に感染する別の病気です。
-
- 保育園や学校はいつから行けますか?
-
熱がなく、普段通りに食事ができ、全身状態が安定していれば登園・登校可能です。ただし、園や学校の方針を確認してください。
-
- 大人もかかりますか?
-
はい、大人もかかることがありますが、一般的に症状は軽いことが多いです。
-
- 何度もかかることがありますか?
-
はい、手足口病の原因となるウイルスは複数種類あるため、何度もかかることがあります。
手足口病と似た症状を示す病気(鑑別疾患)
手足口病と症状が似ている病気はいくつかあります。
・ヘルパンギーナ
口の奥(喉の奥)に水疱ができる病気で、高熱が出ることが多いです。
・水痘(水ぼうそう)
全身に痒みを伴う水疱が広がる病気です。水疱は時間経過とともに変化し、かさぶたになります。
・麻疹(はしか)
高熱、咳、鼻水、目の充血などの症状とともに、顔から全身に広がる赤い発疹が現れます。
・猩紅熱
のどの痛み、高熱、全身に細かい砂のような赤い発疹が現れます。
・風疹
軽い発熱とリンパ節の腫れ、全身に淡いピンク色の発疹が現れます。
・突発性発疹
高熱が数日続いた後、熱が下がるとともに全身に赤い発疹が現れます。
・伝染性膿痂疹(とびひ)
皮膚に水疱や膿疱ができ、それが破れてかさぶたになります。
・アレルギー反応
蕁麻疹など、アレルギーによる皮膚の発疹。
・異なる種類のエンテロウイルスによる手足口病
異なるウイルスに感染することで、再度手足口病を発症することがあります。
・コクサッキーウイルス感染症(非典型的な手足口病)
コクサッキーウイルスA6などによる感染では、より広範囲に発疹が出ることがあります。
・単純ヘルペスウイルス感染症
口の周りに水疱ができることがあります(口唇ヘルペス、ヘルペス性歯肉口内炎)。
・ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群(SSSS)
広範囲の皮膚が剥がれる重篤な細菌感染症です。
・多形滲出性紅斑
感染や薬などが原因で起こる皮膚反応で、標的のような形の発疹が現れることがあります。
・疥癬
ヒゼンダニによる感染症で、強い痒みを伴う小さなブツブツやトンネル状の皮疹が現れます。
・ジベルばら色粃糠疹
単一の大きな鱗屑状の斑点から始まり、その後小さな楕円形の斑点が全身に広がります。
・薬疹
薬によって引き起こされる皮膚の発疹。
・ジアノッティ・クロスティ症候群
ウイルス感染に関連する皮膚疾患で、手足やおしりに丘疹性の発疹が現れます。
・伝染性軟属腫(水いぼ)
小さく盛り上がった、光沢のある皮膚色のブツブツができます。
・溶連菌感染症に伴う発疹(猩紅熱様発疹)
のどの痛みとともに、細かい赤い発疹が全身に現れます。
これらの病気との鑑別には、医師の診察が不可欠です。自己判断せずに、症状が気になる場合は医療機関を受診してください。
まとめ
手足口病は、多くのお子さんがかかる一般的な病気ですが、ほとんどの場合は軽症で自然に治ります。しかし、まれに合併症を引き起こす可能性もありますので、注意が必要です。ご家庭では、適切なケアを行い、症状が悪化した場合は速やかに医療機関を受診してください。ご心配なことがございましたら、いつでもご相談ください。