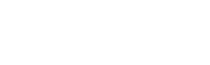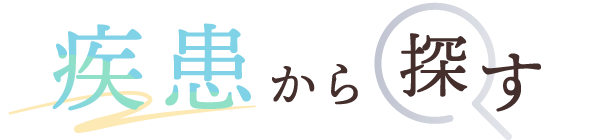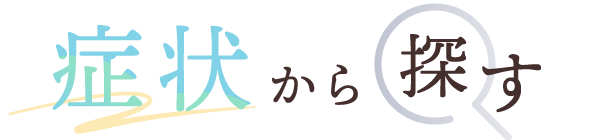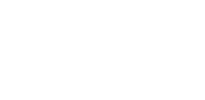- HOME
- じんましん
じんましんとは
じんましんの歴史
古代ギリシャから続く、人類の「旧友」
突然、蚊に刺されたような赤いふくらみが現れ、猛烈なかゆみに襲われる「じんましん」。その経験は、実は2000年以上も前から人類を悩ませてきた、いわば「旧友」のような存在です。
医学の父と称される古代ギリシャの医師ヒポクラテス(紀元前460年頃-377年頃)は、すでにこの疾患を明確に記録していました。彼は、その発疹がイラクサ(nettle)に触れた時の様子に似ていることから、ギリシャ語でイラクサを意味する「knido」にちなんで「knidosis」と名付けました 。現代の医学用語である「urticaria」も、イラクサのラテン名である Urticaに由来しており 、いかにこの病気の外観が特徴的であるかを物語っています。
このように、じんましんは決して珍しい現代病ではなく、有史以来、多くの人々が経験してきた非常にありふれた皮膚の反応なのです。もしあなたが今、じんましんに悩んでいるとしても、決して一人ではありません。
じんましんの正体
「皮膚の血管からの水漏れ」現象
では、じんましんとは一体何なのでしょうか。 一言でいえば、「皮膚の内部で起きる、一時的な血管からの水漏れ」です。
私たちの皮膚の中には、免疫の見張り番である「マスト細胞」という細胞がいます。このマスト細胞が何らかのきっかけで刺激されると、「ヒスタミン」という化学物質を放出します 。このヒスタミンが、皮膚の毛細血管に作用すると、血管の壁に目に見えないほどの小さな隙間が開き、そこから血液の液体成分(血漿)が周囲の組織に漏れ出します。この漏れ出た水分が、皮膚を盛り上がらせ、赤みとかゆみを引き起こすのです。これが、じんましんの「膨疹(ぼうしん)」と呼ばれる発疹の正体です 。
そして、じんましんを診断する上で最も重要な特徴が「個々の発疹の一過性」です 。つまり、一つ一つの膨疹は、通常は数十分から数時間、長くても24時間以内には跡形もなくきれいに消えてしまいます。たとえ次々と新しい発疹が出てきても、最初にできた場所の発疹が24時間以内に消えるかどうか、これが他の多くの皮膚病とじんましんを見分ける決定的な手がかりとなります。
疫学
じんましんは非常にありふれた病気で、生涯のうちに4人に1人が一度は経験すると言われています 。特に、クリニックを受診される方の多くは、原因が特定できずに6週間以上続く「慢性特発性じんましん(CSU)」です。2019年に行われた日本の成人を対象とした調査では、このCSUの有病率は1.1%と報告されています 。これは、例えば人口10万人の市であれば、1100人以上の方がこの慢性的なじんましんに悩まされている計算になります。性別では女性にやや多く(約60-66%)、発症年齢は30代から40代の働き盛りの世代に多いのが特徴です 。
なぜ皮膚科なのか?
「じんましんくらいで病院に?」あるいは「内科や小児科でもいいのでは?」と思われるかもしれません。もちろん、お子様が風邪をひいた後に出るような一過性の急性じんましんは、かかりつけの小児科の先生方でも十分に対応可能です。しかし、じんましんが長引く場合や、症状が強い場合には、皮膚科専門医の診察が極めて重要になります。
その理由は、皮膚科医の真価が「正確な診断と分類」にあるからです。 じんましんは、時に他の病気の症状と非常によく似ている「偉大な模倣者」です。皮膚科医は、その膨大な知識と経験から、それが本当にじんましんなのか、あるいは後述する20種類以上もの鑑別疾患のどれかなのかを的確に見抜きます。
さらに重要なのは、一口に「じんましん」と言っても、その種類は様々であるという点です。これは車に例えると分かりやすいかもしれません。「車」と分かっても、それがスポーツカーなのか、トラックなのか、SUVなのかで運転方法や必要な燃料が全く異なるように、じんましんも、特定の原因がない「特発性じんましん」なのか、圧迫や寒冷などの物理的な刺激で誘発される「刺激誘発型じんましん」なのか、あるいは特定の物質に対する「アレルギー性じんましん」なのかを正しく分類しなければ、適切な治療方針は立てられません 。この分類こそが、無駄な検査や効果のない治療の繰り返しを防ぎ、快方への最短ルートを示す羅針盤となるのです。
また、ごく稀に、じんましん様の皮疹が「蕁麻疹様血管炎」のような全身性の病気のサインである可能性もあります 。皮膚の症状から、そうした重大な病気の可能性をいち早く察知し、患者様の健康を守る「安全ネット」としての役割も、皮膚科医の重要な使命です。
当院での治療アプローチ
当院では、患者様一人ひとりの状況に合わせた、丁寧で根拠のある医療を提供することをお約束します。
患者様との対話が第一歩
何より大切なのは、患者様のお話をじっくりと伺うことです。「いつから始まったか」「どんな時にひどくなるか」「生活の中で何か変化はなかったか」など、あなたの物語の中にこそ、診断と治療の鍵が隠されています。
科学的根拠に基づく治療
当院の治療は、すべて「日本皮膚科学会 蕁麻疹診療ガイドライン2018」に準拠しています 。これは、あなたの治療が科学的に有効性と安全性が証明された、国内最高水準のものであることを意味します。慢性じんましんにおいて原因特定に繋がることが稀な、やみくもなアレルギー検査などは行わず、的確な診断に基づいた治療を行います。
明確な治療ステップ
治療は、安全性と有効性が確立された「治療の階段」を一段ずつ上っていくように、体系的に進めます。まずは最も安全な標準治療から開始し、効果が不十分な場合にのみ、次のステップへと進みます。目標は、最小限の治療で症状を完全にコントロールすることです。
最新・最善の治療へのアクセス
標準的な治療で改善が見られない場合でも、私たちは決してあきらめません。当院では、難治性の慢性じんましんに対して劇的な効果をもたらす可能性のある、先進の生物学的製剤(注射薬)による治療も積極的に行っています。
生活全体を見据えたアプローチ
薬は治療の一部に過ぎません。私たちは、症状に大きく影響するストレス、睡眠、食事、スキンケアといった生活習慣についても、専門的な視点から具体的なアドバイスを行います 。薬だけに頼るのではなく、あなた自身が生活の主導権を取り戻し、症状をコントロールできるよう、全力でサポートします。
具体的な症状と年齢別の特徴
じんましんの症状は、主に「膨疹」と、より深い部分のむくみである「血管性浮腫」の2つに分けられます。
膨疹(ぼうしん)
蚊に刺されたような、あるいはミミズ腫れのような、赤みを伴う皮膚の盛り上がりです。大きさは様々で、いくつかが出たり消えたりすることもあれば、融合して大きな地図状になることもあります。指で押すと一時的に白く色が抜けるのが特徴です。強いかゆみを伴います。
血管性浮腫(けっかんせいふしゅ)
皮膚のより深い部分で「水漏れ」が起こるため、膨疹のようにはっきりと盛り上がるのではなく、境界が不明瞭な、腫れぼったいむくみとして現れます 。 まぶたや唇など、皮膚の柔らかい部分によく見られます。かゆみはあまりなく、むしろ「張っている感じ」「ピリピリする感じ」「軽い痛み」などを感じることが多いです 。膨疹よりも長く続き、2~3日かけてゆっくりと引いていきます 。
特に注意が必要なのは、喉(喉頭)に血管性浮腫が起きた場合です。声がかすれたり、息がしにくい、飲み込みにくいといった症状は、気道が狭くなっている危険なサインであり、直ちに救急医療機関を受診する必要があります 。
年齢で異なるじんましんの顔
じんましんは、どの年代でも起こり得ますが、その原因や種類には年齢による傾向があります。
| 年齢層 | よく見られるタイプ | 主な誘因・背景 | 臨床上のポイント |
|---|---|---|---|
| 乳幼児・小児 | 急性じんましん | ウイルス感染症(風邪など)、食物アレルギー | 多くは一過性で自然に治る。呼吸や飲み込みの状態に注意。 |
| 思春期・若年成人 | コリン性じんましん | 運動、入浴、精神的緊張による発汗 | 汗をかくと出現する、粟粒のような小さい膨疹が特徴。 |
| 成人(20~50代) | 慢性特発性じんましん | 原因不明、ストレス、疲労、自己免疫 | 生活の質(QOL)への影響が大きい。計画的な長期管理が必要。 |
| 高齢者 | 薬剤性、慢性特発性じんましん | 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)、降圧薬(ACE阻害薬)、多剤服用 | 服用中の全ての薬剤の確認が不可欠。お子様の場合 |
急性じんましんが非常に多く、その最大のきっかけは食物アレルギーよりも、風邪などのウイルス感染症であることが圧倒的に多いです 。お子さんが風邪をひいて数日後にじんましんが出た場合、それは体がウイルスと戦っている免疫反応の一環と考えられます。また、活発に活動するお子さんや若い方では、汗が刺激となるコリン性じんましんもよく見られます 。
お子様の場合
急性じんましんが非常に多く、その最大のきっかけは食物アレルギーよりも、風邪などのウイルス感染症であることが圧倒的に多いです 。お子さんが風邪をひいて数日後にじんましんが出た場合、それは体がウイルスと戦っている免疫反応の一環と考えられます。また、活発に活動するお子さんや若い方では、汗が刺激となるコリン性じんましんもよく見られます 。
成人の方の場合
6週間以上続く慢性特発性じんましん(CSU)の発症が最も多い年代です 。この年代では、ストレス、疲労、睡眠不足といった内的要因や、後述する自己免疫が関与していることが少なくありません 。仕事や社会生活への影響も大きく、適切な治療によるQOLの改善が重要となります 。
ご高齢の方の場合
複数の持病のために多くの薬を服用されていることが多く、薬剤性のじんましんを常に念頭に置く必要があります。特に、痛み止めとしてよく使われる非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)や、一部の血圧の薬(ACE阻害薬)は、じんましんを誘発したり悪化させたりすることが知られています 。
なぜじんましんになるのか?
じんましんの引き金は多岐にわたりますが、大きく3つのカテゴリーに分類できます。
1. 特発性じんましん(原因がはっきりしないタイプ)
これが最も多く、じんましん全体の約7割を占めます 。明らかな外的要因なしに、体の内部の要因で自発的にマスト細胞が活性化してしまう状態です。
急性じんましん
発症から6週間以内のもの。多くは感染症などがきっかけとなります。
慢性じんましん
6週間以上、毎日のように症状が続くもの。治療の主戦場であり、自己免疫などが関与していると考えられています。
2. 刺激誘発型じんましん(特定の刺激で起こるタイプ)
特定の物理的な刺激が加わることで、その部分にじんましんが現れるタイプです。
機械性じんましん(皮膚描記症)
皮膚を掻いたり、こすったりすると、その跡に沿ってミミズ腫れができます。
寒冷じんましん
冷たい空気や水に触れると、その部分が赤く腫れます。
日光じんましん
日光に当たった部分にじんましんが出ます。
遅延性圧じんましん
ベルトで締め付けられたり、長時間椅子に座ったりした後、数時間経ってから、圧迫されていた部分が深く腫れます。
3. アレルギー性じんましん
多くの方が最初に疑うタイプですが、慢性じんましんの原因としては比較的稀です 。特定の物質(アレルゲン)に対して、免疫グロブリンE(IgE)という抗体が関与する、真のアレルギー反応です。食物、薬剤、昆虫の毒などが原因となります。
釣り好き院長からの特報
その魚アレルギー、本当に魚が原因ですか?
私自身、新潟の豊かな海で釣りをこよなく愛する者として、この地域にお住まいの皆様に特に知っていただきたい、特殊なじんましんがあります。それは「アニサキスアレルギー」です。
サバ、アジ、イワシ、イカ、サケなど、私たちが日常的に口にする多くの魚介類には、アニサキスという小さな寄生虫が潜んでいる可能性があります 。一般に「サバにあたった」と言うと、鮮度の落ちた魚によるヒスタミン食中毒を思い浮かべる方が多いでしょう 。しかし、それとは全く別に、アニサキスという虫そのものに対するアレルギーが存在するのです 。
これは、たとえ新鮮な魚であっても、アニサキス(生きていても死んでいても)が含まれていれば、感作(アレルギーを獲得)された人はじんましんや、時にはアナフィラキシーという重篤な反応を起こす可能性があることを意味します。
さらに重要なのは、アニサキスのアレルゲンの一部は加熱しても壊れないということです 。つまり、「焼き魚を食べてもじんましんが出るから、自分は魚アレルギーだ」と思い込んでいる方の中に、実は魚ではなくアニサキスにアレルギー反応を起こしているケースが隠れているのです 。皮膚科で正確な診断を受けることで、不必要に全ての魚介類を避ける生活から解放されるかもしれません。新鮮な海の幸に恵まれた新潟県だからこそ、この知識は非常に重要です。
治療法
当院では、日本皮膚科学会のガイドラインに基づき、以下のステップで治療を進めます。目標は「症状が完全に出ない状態」を維持し、最終的には薬なしで生活できるようになることです。
第1段階:基本治療
- 治療の主役は、眠気の少ない第2世代抗ヒスタミン薬の内服です 。フェキソフェナジン(アレグラ®)、ビラスチン(ビラノア®)、ロラタジン(クラリチン®)などがあります。
- 重要なのは、症状が出た時だけ飲むのではなく、症状を予防するために毎日定時に服用することです。
- 塗り薬は、じんましんの原因が皮膚の深部にあるため、基本的には効果が期待できません 。かゆみに対しては、冷やすことが有効です。
第2段階:治療の強化
- 第1段階の治療で1~2週間経っても症状が十分に抑えられない場合、ガイドラインに従って治療を強化します 。
- 方法としては、①抗ヒスタミン薬の用量を増量する(通常量の2倍まで)、②別の種類の抗ヒスタミン薬に変更または追加する、といった選択肢があります。
第3段階:補助的治療薬の追加
第2段階でもコントロールが難しい場合、抗ヒスタミン薬に加えて、ロイコトリエン受容体拮抗薬など、別の作用を持つ薬を追加することを検討します 。
第4段階:最新の生物学的製剤による治療
上記の治療法に抵抗する、最も重症な慢性特発性じんましんの患者様には、当院では最新の注射薬による治療(生物学的製剤)を提供しています。これらは、じんましんの根本的なメカニズムに作用する、非常に効果的な治療法です。
オマリズマブ(ゾレア®)
アレルギー反応に関わるIgE抗体を直接捕まえて無力化することで、マスト細胞の活性化を根本からブロックする注射薬です 。
デュピルマブ(デュピクセント®)
元々重症のアトピー性皮膚炎に用いられていた注射薬です。日本では2024年2月に世界に先駆けて承認されました 。じんましんの背景にある「2型炎症」という体の反応に関わるIL-4とIL-13という情報伝達物質の働きをピンポイントで抑えます 。これにより、従来の治療とは全く異なるアプローチで症状を改善させる希望が生まれました。
最新の注目トピック
じんましんの治療と理解は、近年飛躍的に進歩しています。特に注目すべき3つのトピックをご紹介します。
1. 生物学的製剤の新時代:じんましん治療の精密攻撃
抗ヒスタミン薬で症状が治まらない患者さんは、約半数にものぼると言われています 。こうした難治性の患者さんにとって、生物学的製剤は大きな希望です。従来のオマリズマブ(ゾレア®)がアレルギー抗体IgEを標的とするのに対し、2024年に日本で承認されたデュピルマブ(デュピクセント®)は、IL-4/IL-13という炎症の伝達物質をブロックします 。これは、異なる作用点を持つ「精密兵器」が複数手に入ったことを意味し、治療の個別化(パーソナライズド・メディシン)を大きく前進させました。
2. 腸-皮膚連関:腸内環境が皮膚を左右する
「腸は第二の脳」と言われますが、近年「腸は皮膚の鏡」でもあることが科学的に証明されつつあります。これは「腸-皮膚連関(Gut-Skin Axis)」と呼ばれる考え方です。最新の研究では、慢性じんましんの患者さんの腸内では、善玉菌が減り悪玉菌が増える「腸内細菌叢の乱れ(ディスバイオーシス)」が起きていることが報告されています 。腸内環境の悪化は、腸のバリア機能を低下させ(リーキーガット)、体内に炎症を引き起こす物質が漏れ出しやすくなります。これが血流に乗って全身を巡り、皮膚のマスト細胞を過敏な状態にしているのではないか、と考えられているのです 。この発見は、食事や生活習慣の指導がなぜ重要なのかに、強力な科学的根拠を与えてくれます。
3. 自己免疫という謎:じんましんが「自分自身への攻撃」である場合
慢性じんましんの約半数は、免疫システムが誤って自分自身の体を攻撃してしまう「自己免疫疾患」の一種であると考えられています 。これには大きく2つのタイプが提唱されています。一つは、アレルギー抗体であるIgEが、甲状腺の成分など自分自身のタンパク質を異物と間違えて攻撃してしまう「自己アレルギー(Type I自己免疫)」。もう一つは、IgGという別の抗体が、マスト細胞そのものや、マスト細胞上のIgE受容体を直接攻撃して活性化させてしまう「TypeIIb自己免疫」です 。この自己免疫の考え方は、なぜ一部のじんましんが抗ヒスタミン薬に抵抗性を示すのか、そしてなぜ甲状腺疾患などの他の自己免疫疾患を合併しやすいのか を説明する上で非常に重要です。
日常生活で気をつけるポイント
薬物治療と並行して、日常生活の工夫が症状の改善と再発予防に大きく貢献します。
自分のじんましんの「探偵」になる(症状日記のすすめ)
いつ、どこに、どのくらいの強さのじんましんが出たか、その時何をしていたか、食事内容、ストレスの度合いなどを簡単に記録しましょう 。この記録が、悪化因子を特定する最大のヒントになります。
悪化因子を避ける
ストレスと睡眠不足
これらは、じんましんの火に油を注ぐ最大の悪化因子です 。十分な睡眠(7~8時間を目安)と、自分に合ったストレス解消法を見つけることは、治療の一環として非常に重要です。
物理的刺激
体を洗う時にゴシゴシこすらない、衣類の締め付けを避ける(ゆったりした綿素材の服がおすすめです)、熱いお風呂を避ける、といった工夫が有効です 。
食事
ほとんどの慢性じんましんは特定の食物が原因ではありません。しかし、アルコールや香辛料の多い食事は、血管を拡張させ症状を悪化させることがあります。
皮膚のバリア機能を高める(スキンケア)
- じんましんは体の内側からの反応ですが、皮膚自体のバリア機能が低下していると、外部からのわずかな刺激にも敏感になります。
- 入浴はぬるめのお湯にし、洗浄力のマイルドな石鹸をよく泡立てて優しく洗いましょう 。
- 入浴後は、症状がない日でも必ず保湿剤を全身に塗り、皮膚の乾燥を防ぎましょう 。
かゆみへの対処法
- かゆい時に掻いてしまうと、さらにヒスタミンが放出されて悪循環に陥ります 。
- 掻く代わりに、保冷剤をタオルで包んだものや、冷たいシャワーなどで患部を冷やすと、かゆみが和らぎます 。
よくある質問(FAQ)
-
- じんましんは自然に治りますか?
-
発症して6週間以内の「急性じんましん」は、原因(多くは感染症)がなくなれば自然に治ることが多いです 。しかし、6週間以上続く「慢性じんましん」は、数ヶ月から数年単位で症状が続くことがあり、自然治癒を待つよりも、適切な治療で症状をコントロールすることが生活の質を保つ上で重要です 。
-
- 市販の塗り薬は効きますか?
-
いいえ、ほとんど効果は期待できません。じんましんの原因は皮膚の表面ではなく、内部の真皮層にあるマスト細胞からのヒスタミン放出です 。そのため、体の内側から作用する抗ヒスタミン薬の飲み薬が治療の基本となります 。冷却効果のあるローションなどは、一時的にかゆみを紛らわすのには役立ちます。
-
- アレルギー検査をすれば原因がわかりますか?
-
慢性じんましんの場合、原因が特定のアレルギーであることは稀です。7割以上は原因不明の「特発性」であり、やみくもにアレルギー検査をしても原因が見つかることはほとんどありません 。当院では、問診で「特定のものを食べたり、触れたりした時に必ずじんましんが出る」といった強い疑いがある場合にのみ、検査を検討します。
-
- 掻くと、みみず腫れのように広がるのはなぜですか?
-
皮膚を掻くという物理的な刺激そのものが、マスト細胞を活性化させ、ヒスタミンを放出させるからです 。これを「皮膚描記症」と呼び、じんましんの患者さんによく見られる現象です。掻けば掻くほど症状が悪化する悪循環に陥るため、掻かずに冷やすことが大切です。
-
- ストレスや疲れで本当に悪化するのですか?
-
はい、間違いなく悪化します。ストレスや疲労は、じんましんを直接引き起こす原因ではありませんが、症状を出現させる「引き金の感度」を著しく下げてしまう、最大の悪化因子です。生活習慣を整えることは、薬物療法と同じくらい重要な治療の一部です。
-
- 子どものじんましんは、やはり食べ物が原因でしょうか?
-
そうとは限りません。実際には、お子様の急性じんましんの最も一般的なきっかけは、風邪などのウイルス感染症です 。毎回特定の食べ物を食べた後に決まって症状が出る、という場合を除き、安易に食物アレルギーと決めつけて食事制限をするのは避けるべきです。まずは小児科または皮膚科にご相談ください。
まとめ
じんましんは、ありふれた病気でありながら、そのしつこいかゆみと予測不能な出現は、私たちの生活の質(QOL)を著しく低下させます。特に慢性じんましんは、見た目の問題だけでなく、睡眠障害や集中力の低下、精神的なストレスにも繋がり、患者さんの負担は計り知れません 。
しかし、覚えておいていただきたいのは、「じんましんは、正しい診断と適切な治療によってコントロールできる病気である」ということです。
当院では、日本皮膚科学会のガイドラインに基づいた標準治療はもちろんのこと、従来の治療では効果が不十分だった患者様のための最新の生物学的製剤(ゾレア®、デュピクセント®)による治療まで、幅広い選択肢をご用意しています。他院では行っていないような専門的な治療にも意欲的に取り組み、一人ひとりの患者様にとっての「最適解」を追求します。
長引くじんましんに「体質だから」とあきらめていませんか?そのかゆみ、我慢する必要はありません。ぜひ一度、当院にご相談ください。私たちと一緒に、かゆみのない穏やかな日常を取り戻しましょう。
よく似た症状の別の病気(鑑別疾患)
じんましんに見える皮疹でも、実は別の病気である可能性があります。正確な診断には皮膚科専門医の診察が不可欠です。
・蕁麻疹様血管炎
・虫刺症(特にブユ、アブ)
・多形滲出性紅斑
・薬疹
・接触皮膚炎(かぶれ)
・アトピー性皮膚炎
・痒疹・結節性痒疹
・成人発症スティル病
・遺伝性血管性浮腫(HAE)
・湿疹
・ジベルばら色粃糠疹
・疥癬
・水疱性類天疱瘡(蕁麻疹様期)
・皮膚肥満細胞症
・シュニッツラー症候群
・スウィート病
・多形日光疹
・血清病様反応
・全身性エリテマトーデス
・皮膚筋炎
最新の注目トピック
じんましんの治療と理解は、近年飛躍的に進歩しています。特に注目すべき3つのトピックをご紹介します。
生物学的製剤の新時代:じんましん治療の精密攻撃
抗ヒスタミン薬で症状が治まらない患者さんは、約半数にものぼると言われています 。こうした難治性の患者さんにとって、生物学的製剤は大きな希望です。従来のオマリズマブ(ゾレア®)がアレルギー抗体IgEを標的とするのに対し、2024年に日本で承認されたデュピルマブ(デュピクセント®)は、IL-4/IL-13という炎症の伝達物質をブロックします 。これは、異なる作用点を持つ「精密兵器」が複数手に入ったことを意味し、治療の個別化(パーソナライズド・メディシン)を大きく前進させました。
腸-皮膚連関:腸内環境が皮膚を左右する
「腸は第二の脳」と言われますが、近年「腸は皮膚の鏡」でもあることが科学的に証明されつつあります。これは「腸-皮膚連関(Gut-Skin Axis)」と呼ばれる考え方です。最新の研究では、慢性じんましんの患者さんの腸内では、善玉菌が減り悪玉菌が増える「腸内細菌叢の乱れ(ディスバイオーシス)」が起きていることが報告されています 。腸内環境の悪化は、腸のバリア機能を低下させ(リーキーガット)、体内に炎症を引き起こす物質が漏れ出しやすくなります。これが血流に乗って全身を巡り、皮膚のマスト細胞を過敏な状態にしているのではないか、と考えられているのです 。この発見は、食事や生活習慣の指導がなぜ重要なのかに、強力な科学的根拠を与えてくれます。
自己免疫という謎:じんましんが「自分自身への攻撃」である場合
慢性じんましんの約半数は、免疫システムが誤って自分自身の体を攻撃してしまう「自己免疫疾患」の一種であると考えられています 。これには大きく2つのタイプが提唱されています。一つは、アレルギー抗体であるIgEが、甲状腺の成分など自分自身のタンパク質を異物と間違えて攻撃してしまう「自己アレルギー(Type I自己免疫)」。もう一つは、IgGという別の抗体が、マスト細胞そのものや、マスト細胞上のIgE受容体を直接攻撃して活性化させてしまう「Type IIb自己免疫」です 。この自己免疫の考え方は、なぜ一部のじんましんが抗ヒスタミン薬に抵抗性を示すのか、そしてなぜ甲状腺疾患などの他の自己免疫疾患を合併しやすいのか を説明する上で非常に重要です。