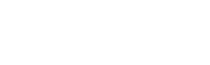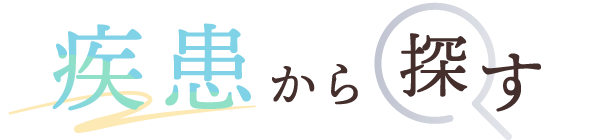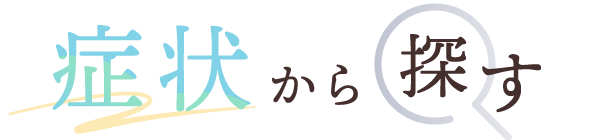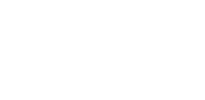- HOME
- 子どもの多汗症
多汗症とは
多汗症とは、体温調節に必要な量を超えて大量の汗が出てしまう症状です。暑いときや運動したときだけでなく、緊張したときなど体が必要としていない場面でも汗が出るため、服や持ち物が濡れてしまい日常生活に支障をきたすことがあります。決して珍しい症状ではなく、人口の約2~3%(50人に1人程度)が多汗症に該当するとされ、患者さんの中にはアトピーやニキビ以上に生活の質が下がるケースも報告されています。多汗症の大半は特定の部位(手や足、脇など)に起こる「原発性局所多汗症」で、原因がはっきりしない体質的な発汗です。これに対し、甲状腺の病気などが原因で全身に汗をかく場合は「続発性多汗症」と呼ばれます。原発性局所多汗症では左右対称に症状が現れ、就寝中は汗が止まるのが特徴です。小中学生の場合、ほとんどはこの原発性局所多汗症にあたります。例えば教室で発表するときに手に汗がびっしょり冬なのに緊張で脇汗が滝のようになってしまう、といった具合です。本人にとってはとても恥ずかしく感じられ、「汗っかきだから仕方ない」と周囲に理解されにくいこともあるため、精神的にも大きな負担となりがちです。
多汗症に悩む人々の歴史は古く、19世紀の文豪ディケンズの小説にも手に汗をかいて本に湿った跡を残す登場人物が描かれています。多汗症は当時から恥ずかしいものとして捉えられていたことがわかります。また医療の歴史を見ても、多汗症の治療には様々な工夫が凝らされてきました。今から100年以上前の1916年には、制汗剤(汗を抑える薬)として塩化アルミニウム液が初めて紹介されました。20世紀初頭には、重症の手汗に対して交感神経を切る手術(交換神経遮断術)が試みられ、その効果も報告されています。もっと昔の時代には、お酢に塩を混ぜた液を手に塗る民間療法もあったと言われます。現在では後述するように手術以外の安全な治療法が確立されており、患者さんは世界中で医療機関に相談しやすくなりました。小中学生であっても、「汗の悩み」は決して我慢する必要のない、きちんと治療できる時代になっています。
なぜ皮膚科なのか?
汗の症状で受診すると聞くと、まず小児科や内科を思い浮かべる保護者の方もいるかもしれません。確かに、発熱やホルモン異常など全身的な病気が原因で汗をかいている場合は内科(小児科)が専門になります。しかし、小中学生の手足や脇の汗のほとんどは原因不明の「原発性局所多汗症」であり、この場合は汗そのものを専門とする皮膚科での対応が適切です。皮膚科は汗腺を含む皮膚の構造や機能に精通しており、他科にはない視点から診断・治療できる強みがあります。実際、日本では長らく多汗症は重視されず「美容上の悩み」と捉えられがちでしたが、皮膚科学会を中心に診療ガイドラインが作成され、適切な治療法が整備されてきました。その結果、皮膚科で保険診療として治療を受けられるようになっています。特に2020年以降、皮膚科領域では画期的な外用薬(後述)が相次いで登場しており、小児科では対応が難しい専門的な治療が可能です。
皮膚科ではまず、本当に多汗症かどうかを判断します。例えば全身の発汗や夜間の寝汗がひどい場合は内科的な検査が必要ですが、そうでなければ原発性多汗症と診断して治療に進みます。診断基準としては、25歳以下で発症し左右対称に汗が出て、寝ている間は汗が止まる、といった所見が目安になります。これらに合致する場合、皮膚科医は多汗症と積極的に診断して治療を開始します。一方、小児科では「成長するまで様子を見ましょう」と経過観察になるケースも少なくありません。しかし汗の症状は、放っておくと本人の自己肯定感を下げてしまいかねません。皮膚科では患者さんのQOL(生活の質)を重視し、早めに治療介入することでお子さんの負担を軽減します。また、皮膚科医は汗に関する新しい知見や治療法にも常にアンテナを張っており、専門家として最適な選択肢を提示できます。このように、多汗症は皮膚科で診るべき病気であり、安心して受診いただければと思います。
けんおう皮フ科クリニックの特徴
当院では、多汗症で悩むお子さんとご家族に寄り添った独自のアプローチを行っています。小中学生の患者さんにも安心して受診いただけるよう、以下のような工夫と強みがあります。
小児患者に配慮した丁寧な説明
お子さんにもわかりやすい言葉や図を使って症状や治療法を説明します。怖がらせない雰囲気づくりを心がけ、質問や不安にもじっくり答えます。
最新治療の提供
皮膚科領域で承認された最新の多汗症治療薬(エクロック®ゲルやラピフォート®ワイプなど)をいち早く導入しています。塩化アルミニウム溶液やボトックス注射など従来からある治療も含め、年齢や症状に合わせた最適な治療プランを提案します。
子供の生活へのサポート
学校生活での対処法についてもアドバイスし、必要に応じて学校宛の情報提供書を書くことも可能です(例:体育の後に着替えを認めてもらう等)。ご家族とも連携し、家庭でのケア方法も指導します。
プライバシーと安心感
思春期のお子さんがデリケートな悩みを相談しやすいよう、診察室でのプライバシーに配慮しています。また、希望があれば同性の医師・スタッフが対応し、リラックスして治療を受けられる環境を整えています。
豊富な治療実績
多汗症に対する豊富な治療経験があり、当院で治療を受けた多くのお子さんが「もっと早く相談すれば良かった!」と笑顔を取り戻しています。症状改善だけでなく、その後のフォローアップまで責任を持って対応いたします。
以上のように、当院ならではのきめ細かな対応で、お子さんの多汗症克服を全力でサポートいたします。
具体的な症状と年齢別の特徴
多汗症の症状は、年齢によって現れやすい部位や悩み方に違いがあります。
小学生の場合、特に多いのが手のひらや足の裏の汗(掌蹠多汗症)です。早い子では幼稚園~低学年くらいから発症し、手足がいつもしっとり濡れている状態になります。絵を描くと画用紙が湿ってよれよれになったり、書いた文字がにじむことがあります。工作の時間にハサミを持つ手が滑ったり、ゲームのコントローラーが汗でべたついて操作ミスしてしまうこともあります。手の跡が机にくっきり残ったり、掌に汗疱(汗による小さな水ぶくれ)ができて痒がる子もいます。このように、小学生の多汗症は主に手足の汗によって日常生活で困ることが多いのが特徴です。体育のあとに足が蒸れて靴下がぐっしょり、上履きが臭くなってしまう、といった悩みもよく聞きます。本人は「自分だけみんなと違う…」と感じてしまいがちですが、実は決して珍しいことではありません。ある研究では、小学生を含む思春期前の子供のおよそ0.6%に多汗症が認められたとの報告があります。学年に数人いる計算になりますので、もしお子さんが手足の汗で悩んでいる場合も「自分だけおかしいわけじゃないよ」と安心させてあげてください。なお、症状が手足に限られている場合でも、皮膚科で適切にケアすれば改善できますので、後述の治療法をご参照ください。
中学生(思春期)になると、引き続き手足の汗に悩むケースもありますが、新たに脇の下の汗(腋窩多汗症)が目立ってくる子が多いです。思春期になると腋の下の汗腺(アポクリン腺・エクリン腺)が発達し始めるため、今まで気にならなかった脇汗・胸や背中の汗が急に増えてきます。部活動や体育でシャツに大きな汗ジミができ、「恥ずかしくて腕を上げられない」「制服の色が汗で変わってしまう」といった悩みがよく聞かれます。脇汗そのものは基本的に無臭ですが、長時間放置すると雑菌で臭いが出ることもあり、中には体臭と結びついて深刻に悩むケースもあります。中学生の多汗症は手足から脇へと悩みの中心が移りやすいのが特徴と言えます。クラスメイトから「なんか汗クサいよ」と心無い言葉を言われてしまい、不登校になる例も報告されています。本人はどうしても防ぎきれない症状なのに、周囲に理解されずいじめの原因になってしまうこともあり、注意が必要です。
実際には日本人の10人に1人は手や脇の多汗症に該当し、そのうち約60%は脇の汗の多汗症だと言われています。決して珍しいことではないという事実を知り、周りの子にも正しく理解してもらうことが大切です。なお、思春期の多汗症は成長とともに悪化することもありますので、早めの対策が望ましいでしょう。
なぜ多汗症になるのか?
汗を出す仕組み(汗腺)
人の体にはエクリン汗腺とアポクリン汗腺という2種類の汗腺があります。エクリン汗腺は体中の皮膚に分布し、水のようなサラサラの汗を出して主に体温調節を担います。手のひらや足の裏の汗腺もすべてエクリン汗腺です。
一方、アポクリン汗腺は脇の下や耳の中など限られた部分にあり、思春期に発達して乳白色の汗を分泌します。アポクリン汗自体は無臭ですが、皮膚の常在菌によって分解されると特有の体臭(いわゆるワキガ臭)の原因になります。小中学生の多汗症で問題となるのは主にエクリン汗腺からの汗です。
エクリン汗腺は生まれつき誰にでもありますが、多汗症の人ではこれらの汗腺が必要以上に活発に働いてしまいます。汗腺そのものに異常があるわけではなく、汗を出すよう命令する自律神経(交感神経)の働きが過剰になることが原因です。本来、交感神経は体温が上がったときや緊張したときに汗腺を刺激しますが、多汗症の人では遺伝的な要因などでこのスイッチが入りやすく、汗の量をうまく調節できないと考えられています。
思春期の影響(ホルモンと発汗)
前述のように、思春期になると新たにアポクリン汗腺が発達し始めます。そのため中学生くらいから脇汗が目立って増えてきますが、これはアポクリン腺からの刺激でエクリン汗腺も活発化するためとされています。
思春期はまた、精神的にも不安定になりやすい時期です。受験や人間関係のストレスで緊張する場面が増え、精神的ストレスが交感神経を刺激して発汗を誘発しやすくなります。例えば「汗をかいたらどうしよう」と心配するだけで手に汗がにじんでくることがあります。このように心理面と発汗は密接に関係しており、汗を気にするあまり更に汗が出てしまう悪循環に陥ることもあります。
遺伝的な要因
多汗症は家族体質が影響すると言われています。実際、ある研究では多汗症の子供の約半数に家族(親や兄弟)にも同様の症状が見られることが報告されました。遺伝形式は完全には解明されていませんが「常染色体優性遺伝(ごく一部の遺伝子の異常で発症しやすくなる)」が示唆されています。ただし、家族に汗の悩みがない場合でも多汗症になる可能性は十分あります。体質的に汗腺をコントロールしにくい人が一定数存在するというのが専門家の見解です。
その他の原因
小中学生の多汗症では、ほとんどが上記の「原発性多汗症」ですが、ごくまれに他の病気が隠れている場合があります。例えば、甲状腺機能亢進症(バセドウ病)や糖尿病、自律神経失調症などは発汗を増やすことがあります。
また、肥満傾向にあるお子さんは体温が上がりやすく汗っかきになる場合があります。これらの場合は原因となる病気の治療が優先されます。しかし夜間は汗が止まり、左右対称に特定の部分だけ汗をかくようであれば、まず原発性多汗症と考えて間違いありません。
大切なのは、本人の努力や精神力でコントロールできるものではないということです。周囲から「汗くらいで大げさだ」などと言われると本人は落ち込んでしまいますが、多汗症はれっきとした体質に根ざした症状です。無理に我慢せず、専門医に相談することで原因に応じた対処法が見つかります。
治療法
現在、多汗症には年齢や症状に合わせて様々な治療法があります。ここでは小中学生にも適用可能な主な治療法を、ポイントごとに解説します。
抗コリン作用の外用薬(塗り薬・シート)
近年登場した新しいタイプの外用薬です。汗を出す神経(交感神経)にブロックをかけ、汗腺が「汗を出せ」という信号を受け取れないようにすることで発汗を抑えます。代表的な薬剤がエクロック®ゲル5%(有効成分ソフピロニウム臭化物)とラピフォート®ワイプ2.5%(グリコピロニウムトシル酸塩)で、いずれも原発性腋窩多汗症(わき汗)に対して保険適用となっています。エクロック®ゲルは12歳以上から、ラピフォート®ワイプは9歳以上から処方可能であり、小学生高学年~中学生の脇汗治療に使える画期的な薬です。それぞれ1日1回患部に塗布または塗擦し、2~3週間で効果が現れます。副作用として皮膚のかぶれや乾燥がありますが、当院では塗り方の指導を徹底し安全に使用しています。これらの薬剤は効果が高く生活の質が大きく向上するため脇汗に悩むお子さんには第一選択となる治療法です。
塩化アルミニウム液(制汗剤)
古くから使われている外用の制汗治療です。塩化アルミニウムは汗腺の開口部を塞ぐことで物理的に発汗を抑える作用があります。市販の制汗スプレーやロールオンにもアルミニウム塩が含まれますが、病院で処方する塩化アルミニウム液はそれらより高濃度で効果が高いのが特徴です。夜間、就寝前の乾いた皮膚に塗って朝洗い流す方法で使用します。手足・脇いずれにも応用できますが、皮膚への刺激感やかぶれが出やすいため敏感肌のお子さんには注意が必要です。塩化アルミニウム製剤はドラッグストアでも購入可能ですが、市販品は濃度が低く重度の多汗症には十分な効果が得られないことも多いです。症状が強い場合は医療機関で高濃度のものを処方してもらうとよいでしょう。
イオントフォレーシス(電気浸透療法)
手のひらや足の裏の多汗症に対して有効な物理療法です。水道水を入れた容器に手足を浸し、微弱な電流を流すことで一時的に汗腺の働きを抑えます。仕組みは完全に解明されていませんが、皮膚の角質層に電気刺激を与えることで汗腺からの分泌が減少すると考えられています。1回20分程度の処置を週に数回行い、効果維持のためには定期的な継続が必要です。通院が難しい場合は家庭用のイオントフォレーシス装置も利用できます。小中学生でも安全に実施でき、副作用は軽い皮膚の乾燥や刺激感程度です。手足の汗でペンが滑るようなケースでは、薬物療法と並行して行うと効果的です。
外用β遮断薬(当院では取り扱いがありません)
比較的新しいアプローチで、汗腺の収縮を促して発汗を減らす塩類溶液を塗布する方法です。例えば塩化マグネシウム液を手足にスプレーすると、一時的に手汗が軽減するという報告があります。ただし保険適用ではなく、効果にも個人差があります。市販の制汗ジェルシートなどにも類似の成分が含まれるものがあり、軽症例では試す価値があります。
ボツリヌス毒素注射(ボトックス注射)
発汗を抑える強力な治療法です。ボツリヌス毒素製剤を患部(主に脇の下)に細かく皮内注射すると、神経から汗腺への信号伝達がブロックされ、数か月~半年以上汗が出にくくなります。効果は非常に高く、1回の治療で半年程度程度汗の量が大幅に減ります。即効性がある反面、注射の痛みや費用の問題、定期的な再注射が必要になる点がデメリットです。手のひらや足裏にも有効ですが、痛みを伴うため小中学生には基本的に脇の下への施術が中心となります。当院では表面麻酔などで可能な限り痛みを軽減しつつ施行しています。発汗による日常生活への支障が甚大な場合、選択肢となる治療法です。
内服療法(飲み薬)
汗を抑える飲み薬として抗コリン薬や漢方薬が使われることがあります。手足や脇など広範囲の汗を一度に抑えたいときに有効です。ただし、副作用として口の渇きや便秘、目のかすみなど全身的な症状が出ることがあり、小児への使用は慎重に判断されます。日本では小児科領域で漢方薬(防已黄耆湯など)が体質改善目的で処方される場合もありますが、効果には個人差があります。基本的には外用療法で十分対応できるケースが多いため、内服薬は補助的な位置づけです。
手術療法(当院では行っておりません)
他の治療で効果が不十分な重症例では、外科的治療も検討されます。代表的なのが胸部交感神経遮断術(ETS手術)で、脇の下から内視鏡を入れて肺の後ろを走行する交感神経幹を切断またはクリップで留める方法です。手のひらや脇の多汗症に対して高い効果がありますが、代償性発汗(他の部分の汗が増える副作用)が高率に生じるため慎重な適応判断が必要です。小中学生の場合、成長段階でもあるため手術は最終手段となりますが、高校生以降で生活に支障が大きい場合には検討されることがあります。もう一つの外科的治療は汗腺摘除術で、脇の下の汗腺そのものを切除または吸引で破壊する方法です。こちらは局所麻酔で行える手術で、脇汗には有効ですが手足には適用できません。近年は汗腺に熱を加えて破壊するミラドライ(microwave療法)やレーザー治療も登場しつつあります。いずれも専門医療機関でのみ実施可能な高度医療です。小中学生ではまず保存的な外用治療を十分試み、それでも改善しない場合に将来的な選択肢として手術を考える、という流れになります。
以上のように、多汗症には多彩な治療法があります。症状の程度や部位、年齢によって最適な方法は異なりますので、経験豊富な皮膚科医と相談しながらベストな治療計画を立てることが重要です。
日常生活で気をつけるポイント
制汗剤(デオドラント)の使い方
市販の制汗スプレーやロールオン、シートなどを上手に活用しましょう。汗をかく前、肌が乾いた清潔な状態で使うのがコツです。
例えば登校前に制汗剤を脇や手のひらに塗っておき、休み時間ごとに汗を拭く習慣をつけると効果的です。エアコンのない教室では冷感シートで汗を拭き取るのも良いでしょう。なお、スプレータイプは周囲の目が気になる場合、透明なロールオンやシートタイプを使うと目立ちません。就寝前に制汗剤を塗っておくと翌朝汗をかきにくくなる製品もあります。
肌に刺激を感じたら使用を中止し、医療用の制汗薬について皮膚科医に相談してください。
衣服の工夫
普段の服装を見直すだけでも汗の不快感はかなり軽減できます。通学時は吸汗速乾素材の肌着を着用し、汗をかいてもベタつかないようにしましょう。夏場は薄手で通気性の良い衣服を選び、冬場でも室内ではすぐ上着を脱げるよう重ね着で体温調節してください。色の濃い服は汗ジミが目立ちにくいので、学校指定の服装の範囲で工夫してみましょう。
また、脇汗パッドや汗取りインナーを使うと服に汗が染みにくくなります。足汗がひどい場合は5本指ソックスや通気性の良い靴を選び、替えの靴下を持参してこまめに履き替えると良いです。
食事・飲み物
発汗を促しやすい香辛料の効いた食事やカフェイン飲料は控えめにしましょう。特に夏場に辛いカレーを食べたりすると一気に汗が噴き出すことがあります。
逆に身体を冷やす食べ物(スイカやキュウリなど)を摂ったり、こまめな水分補給で体温上昇を防ぐことも大切です。ただし冷たいものの摂りすぎは胃腸を弱らせる原因となるため注意してください。適度な塩分補給も忘れずに。
生活リズムとメンタルケア
睡眠不足や生活リズムの乱れは自律神経の働きを乱し、発汗を更に悪化させることがあります。毎日できるだけ決まった時間に寝起きし、朝ごはんをきちんと食べて体内時計を整えましょう。
適度な運動習慣も自律神経を安定させます。緊張や不安を感じたとき、腹式呼吸やストレッチでリラックスする習慣を身につけると汗の噴出を和らげる助けになります。「また汗をかくかも…」と考えすぎないことも大切です。周囲には多汗症であることを理解してもらい、心理的なプレッシャーを軽減しましょう。
清潔とスキンケア
汗をかいたまま放置すると皮膚がふやけて雑菌が繁殖しやすくなります。汗をかいたらできるだけ早めに拭き取り、シャワーや入浴で清潔に保ちましょう。特に足は蒸れた状態が続くと水虫(足白癬)になるリスクがあります。
入浴後は汗疹予防にしっかり身体を乾かし、必要に応じて弱酸性の保湿剤などで肌を整えておくと良いでしょう。皮膚科で処方された外用薬を使用する際も、清潔な肌に塗ることで効果が高まります。
これらの日常生活のポイントを実践することで、治療薬の効果がより発揮され、汗によるトラブルが軽減します。お子さんと一緒にできる範囲から取り入れてみてください。習慣づけるまで大変かもしれませんが、少しの工夫で汗に悩まない快適な毎日が送れるようになります。
よくある質問(FAQ)
-
- 市販の制汗剤や薬で多汗症は治りますか?
-
軽い症状であれば、市販の制汗剤である程度コントロールできる場合もあります。
しかし、根本的に多汗症を“治す”効果は市販薬には期待できません。ドラッグストアで手に入る制汗剤の多くは、発汗を一時的に抑えるものの医療用ほど有効成分が高濃度ではなく、重度の多汗症には十分な効果が得られにくいのが現状です。
特に手のひらや足裏の頑固な汗、シャツに染み出るような脇汗には、市販品では限界があります。多汗症は身体の機能的な問題によるものなので、症状が強い場合は皮膚科で処方される薬(高濃度の塩化アルミニウム外用液や抗コリン外用薬など)や専門的な治療を受けることをおすすめします。市販の制汗剤を使いつつ、それでも日常生活に支障があるようなら我慢せず受診してください。
-
- 思春期を過ぎれば自然に治ることもありますか?
-
残念ながら、多汗症が完全に自然治癒するケースは稀です。
思春期に汗腺が発達しきる20歳前後までは症状が変化しやすく、中には成長とともに多少汗の量が落ち着く人もいます。しかし、何もしなくても治る保証はなく、大人になっても多汗症に悩む人は少なくありません。
例えば手足の多汗症は、そのほとんどが16歳までに発症すると言われ、適切な治療をしなければその後も長く付き合う可能性があります。むしろ長年の悩みを放置することで対人関係に消極的になるなど精神的な影響が蓄積しかねません。成長を待つ間にもできるケアや治療がありますので、早めに対策することをおすすめします。
-
- 学校で汗のことで困ったらどうすればいいですか?
-
学校生活の中で汗が原因の困り事が出てきた場合、まずは遠慮なく周囲の大人に相談しましょう。担任の先生や保健の先生に事情を説明すれば、きっと理解して対応策を一緒に考えてくれるはずです。
例えば、テストで手汗がひどい子には答案用紙を2部用意しておき、1枚目が湿って破れても書き直せるようにするといった配慮が考えられます。体育の後に制服のシャツを着替える時間をもらったり、教室に扇風機を置いてもらうだけでも違います。周囲に打ち明けにくい場合は、皮膚科から「多汗症で治療中である」ことを記載した連絡文を作成できますので、受診時にご相談ください。
当院でも、学校への説明が必要なお子さんには積極的に協力いたします。なお、部活動や運動に関しては基本的に我慢せず参加してください。確かに運動中は大量の汗をかきますが、運動はストレス発散にもなり自律神経のバランスを整える効果があります。汗対策(タオルや着替えの用意、水分補給など)を万全にしておけば問題ありません。むしろ汗を気にして引きこもる方が心身の健康に良くないので、周囲の理解を得ながら学校生活を楽しんでください。
-
- 冬や寒い日でも汗をかくのは異常でしょうか?
-
冬の寒い時期でも多汗症の方は汗をかくことがあります。これは決して異常ではなく、多汗症の汗は気温ではなく自律神経の信号によって起こるためです。
例えば緊張したとき、人前に出たときなどは冬でも手に汗を握るものです。同様に、多汗症の人は冬場でも発汗スイッチが入りやすく、暖房の効いた室内や厚着で汗をかいてしまいます。「寒いのになぜ?」と周囲に驚かれるかもしれませんが、身体の仕組みによるものなので心配いりません。
ただし、冬に汗をかくと身体が冷えて風邪をひきやすくなるので、吸湿発散性の肌着を着たり汗をかいたら早めに拭くなどの対策は重要です。寒い中で汗をかくのは本人もつらいものですが、上手に付き合っていきましょう。
まとめ
お子さんの多汗症に少しでも心当たりがあれば、ぜひ一度当院にご相談ください。受診をおすすめする主な理由は以下の通りです。
早期対応で心身の負担を軽減
多汗症は単なる生理現象ではなく、放置すれば本人の自己肯定感や対人関係に影響を及ぼしかねません。早めに皮膚科専門医が介入することで、汗によるストレスを和らげ学校生活を快適に送れるようサポートできます。実際、適切な治療で多汗症患者さんのQOL(生活の質)が飛躍的に向上したとの報告があります。悩み始めた今だからこそ、将来の負担を減らすチャンスです。
最新の治療が受けられる
前述のように、多汗症治療は近年大きく進歩しています。市販の対策だけでなく、医療機関でしか扱えない新薬や専門的機器による治療を受けることで、これまで改善しなかった汗の症状が劇的に良くなる可能性があります。当院では最新の治療法を常に取り入れ、エビデンスに基づいた安全な医療を提供しています。お子さんにとって最善の選択肢を一緒に見つけていきましょう。
総合的なサポート
医療としての治療はもちろん、日常生活での工夫や学校への働きかけも含めて総合的にサポートできるのが専門クリニックの強みです。当院では多汗症に関するあらゆる相談に応じており、「どうせ治らない」とあきらめる前にできることが必ず見つかります。家族だけで抱え込まず、専門家の知恵をぜひ活用してください。
安心して通える環境
小中学生の患者さんにも配慮した対応で、プライバシーを守りながら治療を進めます。些細な不安や疑問でも構いませんので、遠慮なくお話しください。スタッフ一同、お子さんの気持ちに寄り添いながら親身に対応いたします。「汗のせいで人前に出たくない」「もう諦めるしかないの?」といった不安を、一緒に解消していきましょう。
多汗症は決して恥ずかしいことではなく、適切な治療で必ず改善できる症状です。お子さんの明るい笑顔と自信を取り戻すために、当院がお力になります。 「もしかして…」と思ったら、お気軽に専門医までご相談ください。汗の悩みを克服し、快適な毎日を送れるよう全力でサポートいたします。
多汗症は決して恥ずかしいことではなく、適切な治療で必ず改善できる症状です。お子さんの明るい笑顔と自信を取り戻すために、当院がお力になります。 「もしかして…」と思ったら、お気軽に専門医までご相談ください。汗の悩みを克服し、快適な毎日を送れるよう全力でサポートいたします。
- 似た症状の疾患