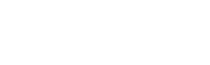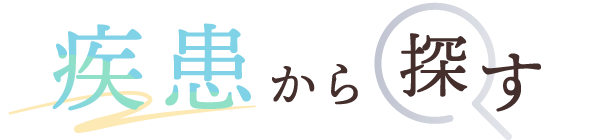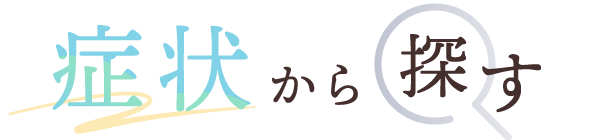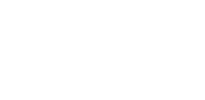- HOME
- 子どものにきび
子どものにきびとは
はるか昔から続く、にきびとの付き合い
「青春のシンボル」なんて言われることもある、にきび。でも、悩んでいるお子さんやご家族にとっては、決して軽い問題ではありませんよね。実は、にきびは決して現代だけの悩みではありません。驚くかもしれませんが、にきびに関する記述は、はるか昔、平安時代の漢和辞典『和名類聚抄』に「邇岐美(にきみ)」として登場するのです 。さらに遡れば、古代エジプトでは「嘘をつくとにきびができる」と考えられていたという記録もありますし 、古代ギリシャの医師ヒポクラテスもにきびについて言及していました 。日本でも、明治時代に、にきびに悩む奥様のために薬剤師のご主人が化粧水を作ったという心温まる話も残っています 。このように、にきびは人類が古くから向き合ってきた、とても身近な皮膚の悩みの一つなのです。
しかし、「よくあること」だからと放置してはいけません。にきびは、医学的には「尋常性痤瘡(じんじょうせいざそう)」と呼ばれる、毛穴とその周りの組織(毛包脂腺系)に起こる慢性の炎症性疾患です 。単なる見た目の問題ではなく、れっきとした皮膚の病気であり、適切なケアや治療が必要です。特に、不潔だからできるというわけではないことを理解することが大切です 。
子どものにきびはどれくらい一般的?いつからできるの?
にきびは、思春期や若者の大多数が経験すると言われています。世界的な調査では、12歳から25歳までの約85%がにきびを経験するという報告もあります 。これは非常に高い割合ですね。
具体的な数字を見てみましょう。イタリアで行われた調査では、小児科外来を受診した9歳から14歳の子どものうち、34.3%ににきびが見られました。年齢が上がるにつれてその割合は増え、9歳では6%程度ですが、13歳以上では36.3%にも達しました 。また、オランダでの約4500人の13歳児を対象とした調査では、女の子の62%、男の子の45%に目に見えるにきびが確認されています 。
一般的に「思春期のにきび」というイメージが強いかもしれませんが、実はもっと早い時期、7歳から12歳くらいの「思春期前」に始まることも珍しくありません 。アメリカのある研究では、7歳から12歳の子どものにきびの発生率は、年間1万人あたり58人と報告されています。特に年齢による差は大きく、7~8歳では1万人あたり4.3人ですが、9~10歳では24.4人、11~12歳では144.3人と急増します 。
この思春期前のにきびは、女の子に多く見られる傾向があります。先ほどのアメリカの研究でも、女の子の発生率は男の子の3倍以上でした(1万人あたり89.2人 vs 28.2人)。これは、女の子の方が少し早くホルモンの変化が始まることと関連していると考えられます 。この時期のにきびの始まりは、副腎から分泌されるアンドロゲン(男性ホルモンの一種ですが、男女ともに分泌されます)というホルモンの働きが活発になる「アドレナーキ(副腎皮質機能発現)」と呼ばれる時期(だいたい8歳頃)と関連があることがわかっています 。つまり、かなり早い段階から、にきびができやすい生理的な準備が始まっているのです。このことを知っておくと、小学校中学年くらいのお子さんにポツポツができ始めても、「まだ早いのでは?」と見過ごさずに、早めのケアを考えるきっかけになります。
また、最近の研究では、思春期前のにきびと体格指数(BMI)との関連も指摘されています。にきびのあるお子さんは、ないお子さんに比べて肥満傾向にある割合が高いという報告や 、特に男の子では、体重が重い方がにきびが重症化しやすい可能性を示唆するデータもあります 。さらに、BMIが高いお子さんほど、飲み薬による治療が必要になる傾向があるという報告もあります 。これは、ホルモンバランス(例えば、食事に関連するインスリン様成長因子(IGF-1)など)や、体全体の炎症、代謝などが複雑に関係している可能性を示唆しています。
ただし、だからといって特定の食事を制限すれば良いという単純な話ではなく、日本のにきび治療ガイドラインでも一律の食事制限は推奨されていません 。お子さん一人ひとりの状態を総合的に見ることが大切です。
肌の色による違いも指摘されることがあります。一部の研究では、肌の色が濃いお子さんの方がにきびが重症化しやすい可能性が示唆されており 、また、炎症が治った後にシミのような色素沈着が残りやすい傾向もあります 。当院では、様々な肌タイプのお子さんに対応できるよう、色素沈着のリスクも考慮した治療選択を心がけています。
なぜ皮膚科なのか?
「にきびくらいで病院に?」と思われるかもしれません。あるいは、「子どものことだから、まずは小児科かな?」と考える方もいらっしゃるでしょう。もちろん、小児科の先生方もにきびの初期対応をしてくださいますが、にきびを専門的に、そしてよりきれいに治すためには、皮膚科専門医の診察を受けることがとても重要です。
皮膚は専門知識が必要な「臓器」です
皮膚は、体を覆っている単なる「カバー」ではありません。体の中で最も大きな「臓器」であり、体温調節、水分の保持、外部からの刺激や病原体の侵入を防ぐバリア機能など、多くの複雑な働きを担っています。皮膚科は、この複雑で大切な皮膚と、それに関連する髪や爪の病気を専門的に診断・治療する診療科です。
にきびは「病気」、だから専門医へ
にきびは、先ほど述べたように「尋常性痤瘡」という皮膚の病気です。単にポツポツができるだけでなく、その背景にはホルモンの影響、皮脂の分泌、毛穴の詰まり、アクネ菌という細菌の関与、そして体の免疫反応(炎症)といった複数の要因が複雑に絡み合っています 。
小児科など他の診療科でも基本的な治療は可能ですが、皮膚科専門医は、
1. 正確な診断力
にきびの種類(白ニキビ、黒ニキビ、赤ニキビ、膿をもったニキビ、しこりなど)や重症度を的確に診断します 。これは、適切な治療法を選ぶための第一歩です。また、にきびとよく似た他の皮膚病(後述します)と正確に見分けることができます 。間違った診断は、治療の遅れにつながりかねません。
2. 幅広い治療選択肢
最新のガイドラインに基づいた塗り薬や飲み薬の知識はもちろん、それらを効果的に組み合わせる方法、副作用への対処法に精通しています 。特に、飲み薬(抗菌薬など)の適切な使い方や期間の判断、新しい治療薬の情報提供などは専門医の得意分野です。当院で導入しているような、ケミカルピーリングや光線療法などの処置も、皮膚科ならではの選択肢です。
3. にきび跡(瘢痕)の予防と治療
にきび治療の大きな目標の一つは、跡を残さないことです。皮膚科医は、炎症を早期に抑え、跡になりにくい治療法を選択することに長けています 。できてしまった跡に対しても、将来的な治療の選択肢(レーザー治療など)について相談できます。
4. 専門的なスキンケア指導
お子さんの肌質やにきびの状態に合わせた、具体的な洗顔方法や保湿ケア、日焼け止めの選び方などをアドバイスします。
5. 心理的なサポート
にきびは、特にお子さんや思春期の若者にとって、見た目の問題から心理的な負担になることがあります 。皮膚科医は、そうした悩みにも寄り添いながら治療を進めます。
このように、にきびの複雑さを考えると、皮膚の専門家である皮膚科医が診療にあたる意義は大きいのです。特に、治療がうまくいかない場合や、跡が残りそうな場合、あるいは、にきびがとても早く(幼児期などに)現れた場合は、ぜひ皮膚科にご相談ください。
当院の特徴― 当院での治療アプローチ ―
当院は、新潟県三条市に根ざし、地域の皆さまのお肌の健康を守ることを第一に考えている皮膚科クリニックです。特に、お子さんの皮膚トラブルには力を入れており、最新の知見に基づいた丁寧な診療を心がけています。
私たちの診療方針
患者様中心の医療
お子さんと保護者の方のお話をじっくり伺い、不安や疑問に丁寧にお答えします。治療方針は、一方的に決めるのではなく、ご納得いただいた上で一緒に進めていきます。
地域密着
三条市および周辺地域の皆さまにとって、気軽に相談できる「かかりつけ皮膚科医」でありたいと考えています。地域の気候やライフスタイル(例えば、アウトドア活動が盛んなことなど)も考慮に入れたアドバイスを心がけています。
エビデンスに基づいた治療
日本皮膚科学会が作成した最新の「尋常性痤瘡・酒皶治療ガイドライン2023」 を基本とし、科学的根拠に基づいた、安全で効果的な治療を提供します。
診断と説明の重視
なぜにきびができるのか、どのような状態なのか、これからどんな治療をするのか、日常生活で何に気をつけるべきかなどを、分かりやすくご説明します。お子さん自身にも、自分の肌の状態やケアについて理解してもらうことを大切にしています。
総合的な視点
皮膚の状態だけでなく、お子さんの年齢、生活習慣、学校生活、そしてにきびが心理面に与える影響なども考慮して、一人ひとりに合った治療計画を立てます。
当院での具体的な治療アプローチ
当院では、以下の点を重視して、お子さんのにきび治療に取り組んでいます。
ガイドライン遵守
まずは、日本のガイドラインで推奨されている治療法を基本とします。これには、毛穴の詰まりを改善する塗り薬(アダパレンなど)や、アクネ菌を抑えたり角質を剥がれやすくしたりする塗り薬(過酸化ベンゾイルなど)、あるいはそれらの配合剤、必要に応じた抗菌薬の塗り薬や飲み薬などが含まれます。
個別化された薬物療法
お子さんのにきびの種類(白ニキビ主体か、赤ニキビ主体かなど)、重症度、肌質に合わせて、最適な薬剤を選択し、組み合わせます。特に抗菌薬(飲み薬・塗り薬)の使用にあたっては、耐性菌の問題を考慮し、漫然とした長期使用を避け、適切な期間と他の薬剤との併用を原則としています 。処方する薬剤の例としては、アダパレン 、過酸化ベンゾイル 、両者の配合剤 、クリンダマイシンと過酸化ベンゾイルの配合剤 、ドキシサイクリン内服 などがあります。
当院ならではの処置(保険適用外診療を含む)
標準的な薬物療法に加えて、より良い効果を目指したり、特定の悩みに対応したりするために、以下の治療法を組み合わせることがあります(一部保険適用外)。
ケミカルピーリング
サリチル酸マクロゴールなど、比較的刺激の少ない薬剤を用いて、古い角質や毛穴の詰まりを取り除きやすくします。にきびの改善だけでなく、肌のターンオーバーを整える効果も期待できます。ガイドラインでも選択肢の一つとして挙げられています 。
エレクトロポレーション(導入治療)
特殊な電気パルスを用いて、肌に一時的に微細な隙間を作り、ビタミンC誘導体など、にきびや美肌に有効な成分を肌の奥まで浸透させやすくする治療です。薬剤の効果を高めるサポートをします。
ヒーライト(LED治療)
特定の波長のLED(発光ダイオード)を照射することで、にきびの炎症を抑えたり、肌細胞の活性化を促したりする治療です。痛みはなく、温かい光を浴びるような感覚です。赤みのあるにきびや、治療後の肌の回復をサポートします。
面皰圧出(めんぽうあっしゅつ)
炎症を起こす前の白ニキビや黒ニキビ(コメド)の内容物を、専用の器具で丁寧に取り除く処置です 。毛穴の詰まりを物理的に解消することで、炎症性のニキビへの進行を防いだり、塗り薬の浸透を助けたりする効果が期待できます。
にきび跡(瘢痕)への配慮
治療の初期段階から、できるだけ跡が残らないように炎症をしっかり抑えることを重視します。もし跡が残ってしまった場合でも、将来的に当院のレーザー機器(赤みに対するVビーム、凹凸に対するCO2レーザー、サブシジョンなど)を用いた治療も可能ですので、ご相談ください。ガイドラインでは、盛り上がったにきび跡(肥厚性瘢痕)に対するステロイド局所注射も選択肢として挙げられています 。 ニキビ跡については別の項でも詳しく述べます。
維持療法とスキンケア指導
にきびは良くなったり悪くなったりを繰り返しやすい慢性的な病気です。症状が改善した後も、良い状態を保ち、再発を防ぐための「維持療法」が非常に重要です 。多くの場合、毛穴の詰まりを防ぐ塗り薬(アダパレンなど)を継続します。また、日々の正しいスキンケア(洗顔、保湿、紫外線対策)が治療効果を高め、再発予防につながるため、具体的な方法を丁寧に指導します 。
当院では、これらのアプローチを組み合わせることで、お子さん一人ひとりのにきびの状態とライフスタイルに合わせた、最適な治療を提供することを目指しています。
具体的な症状と年齢別の特徴
一口に「にきび」と言っても、その見た目やでき方はいろいろです。また、お子さんの年齢によっても特徴が異なります。
にきびの種類(どんな「ポツポツ」がある?)
にきびの基本は、毛穴が詰まることから始まります。最初は目に見えない「マイクロコメド」という状態です 。それが進行すると、以下のような様々な種類の「ポツポツ」として現れます。
コメド(面皰めんぽう)
炎症のないにきび
白ニキビ(閉鎖面皰へいさめんぽう)
毛穴が完全に詰まって、皮脂や角質が中に溜まった状態。小さくて白い、あるいは肌色のポツッとした盛り上がりです 。例えるなら、皮膚の下にできた小さな風船のようなものです。
黒ニキビ(開放面皰かいほうめんぽう)
毛穴の出口が開いて、溜まった皮脂や角質が空気に触れて酸化し、黒っぽく見える状態。これは汚れが詰まっているわけではありません。例えるなら、毛穴の出口に黒い栓が見えているような状態です。
炎症性皮疹
赤みや膿(うみ)のあるにきび
赤ニキビ(紅色丘疹こうしょくきゅうしん)
コメドの中でアクネ菌が増殖し、炎症が起こって赤く腫れた状態。触ると少し痛いこともあります 。
黄ニキビ(膿疱のうほう)
赤ニキビの炎症がさらに進んで、膿が溜まって黄色や白っぽく見える状態 。例えるなら、赤い盛り上
がりのてっぺんに白い「頭」が見えるようなものです。
しこりニキビ(結節けっせつ、嚢腫のうしゅ)
炎症が皮膚の深いところにまで及んで、硬いしこりになったり、膿の袋(嚢腫)ができたりした状態 。痛みが強く、治った後に跡(瘢痕)が残りやすいタイプです。
年齢によるにきびの特徴
にきびは、できる年齢によっても、その見た目や原因、対処法が少しずつ異なります 。
新生児にきび(新生児痤瘡しんせいじざそう)(生後~約6週)
生まれて間もない赤ちゃんの顔(特に頬や鼻)にできる、小さな赤いポツポツや膿疱です。これは、お母さん由来のホルモンの影響や、皮膚に常在するマラセチアというカビ(酵母)の一種が関与していると考えられています。多くの場合、特別な治療をしなくても数週間から数ヶ月で自然に消え、跡も残りにくいです。ただし、他の赤ちゃんの湿疹との見分けが大切です。
乳児にきび(乳児痤瘡にゅうじざそう)(約6週~1歳)
新生児にきびよりも少し遅れて始まり、長引くことがあります。白ニキビや黒ニキビが見られることもあり、炎症が強いと跡(瘢痕)が残る可能性もゼロではありません。赤ちゃんの体内で作られるホルモンが影響していると考えられます 。跡を残さないためには、治療が必要になる場合があります。他の皮膚病との鑑別も重要です 。
幼児期にきび(1歳~7歳)
この年齢でにきびができるのは まれ です。もしこの時期に、にきびのようなものがたくさんできたり、なかなか治らなかったりする場合は、ホルモンの異常(早発思春期や内分泌系の病気など)が隠れている可能性も考えられます 。必ず皮膚科専門医の診察を受け、原因を調べることが重要です。
思春期前のにきび(7歳~12歳)
本格的な思春期に入る前に始まるにきびです。最初は、おでこや鼻、あごといったTゾーンに、白ニキビや黒ニキビといったコメドが目立つことが多いです 。次第に炎症を伴う赤いニキビも混じってきます。副腎由来のホルモン(アンドロゲン)の分泌が始まる「アドレナーキ」と関連しています 。この時期に早くからにきびができるお子さんは、将来的ににきびが重症化しやすいという報告もあるため 、早期からの適切なケアと治療が、悪化やにきび跡を防ぐ鍵となります。
思春期のにきび(12歳~)
いわゆる「にきび」として最もよく知られているタイプです。性ホルモンの分泌が活発になることで、皮脂の分泌が急増し、顔だけでなく、胸や背中などにも広がることがあります。症状の程度も、軽いコメド中心のものから、炎症が強く、しこりや嚢腫ができる重症型(重症の炎症性ざ瘡)まで様々です 。重症度に応じた、計画的な治療が必要になります 。
にきび跡(瘢痕)と色素沈着
にきびの炎症が強かったり、長引いたり、あるいは自分で潰してしまったりすると、治った後に跡が残ってしまうことがあります。跡には、皮膚がへこんだ状態(萎縮性瘢痕いしゅくせいはんこん)や、逆に盛り上がった状態(肥厚性瘢痕ひこうせいはんこん、ケロイド)があります。また、炎症が治まった後に、茶色っぽいシミ(炎症後色素沈着えんしょうごしきそちんちゃく)が残ることもあります。特に肌の色が濃いお子さんでは、この色素沈着が目立ちやすい傾向があります 。これらの跡は、一度できてしまうと完全に消すのは難しいため、何よりも跡を作らないこと=早期に、適切に、にきびを治療すること が最も大切です 。
お子さんのにきび:年齢別の特徴まとめ
| 年齢区分 | 主な年齢範囲 | よく見られるにきびの種類 | 特徴・注意点 | 主な対応 |
|---|---|---|---|---|
| 新生児にきび | 生後~約6週 | 小さな赤いポツポツ、膿疱 | 自然に消えることが多い、跡に残りにくい、母体ホルモン・マラセチア関与? | 清潔・保湿を基本に経過観察。他の湿疹との鑑別。 |
| 乳児にきび | 約6週~1歳 | コメド、赤いポツポツ、膿疱(時にしこり) | 新生児期より持続しやすい、跡が残る可能性あり、乳児自身のホルモン関与? | 跡が残りそうな場合は治療を検討。他の皮膚病との鑑別が重要。 |
| 幼児期にきび | 1歳~7歳 | (まれ) 様々なタイプのにきびが見られる可能性 | この時期の発症はまれ。ホルモン異常など基礎疾患の可能性を考慮。 | 必ず皮膚科専門医を受診し、原因精査を。 |
| 思春期前のにきび | 7歳~12歳 | Tゾーン中心のコメド(白・黒)、次第に炎症性皮疹も | アドレナーキと関連、早期発症は重症化のサインかも? | 早期からの適切なケア・治療で悪化や瘢痕化を防ぐ。 |
| 思春期のにきび | 12歳~ | コメド、炎症性皮疹 (赤、黄)、時にしこり・嚢腫、背中・胸にも |
思春期の性ホルモン増加が主因、重症度は様々、慢性化しやすい | 重症度に応じた計画的な治療と、根気強い維持療法が必要。 |
この表からもわかるように、お子さんのにきびが現れた「年齢」は、その原因や対応を考える上で非常に重要な手がかりとなります。特に、通常あまり見られない幼児期のにきびは、注意深い診察と原因検索が必要です。診察時には、いつ頃からにきびが気になり始めたかを、ぜひ医師にお伝えください。
なぜ子どものにきびになるのか?
どうして、にきびはできてしまうのでしょうか? その仕組みは、主に4つの要因が絡み合って起こると考えられています。毛穴を、皮膚の表面につながる細い管だとイメージしてみてください。
1. 皮脂(あぶら)の分泌が増える(皮脂分泌の増加)
毛穴の奥には皮脂腺という、皮脂を作る工場があります。思春期になると、アンドロゲンというホルモンの影響で、この工場が活発になり、皮脂がたくさん作られるようになります 。例えるなら、「皮脂工場がフル稼働」する状態です。
2. 毛穴の出口が詰まる(毛穴の角化異常 / 毛孔閉塞)
毛穴の管の内側を覆っている皮膚の細胞(角質細胞)が、通常ならスムーズに剥がれ落ちるところ、うまく剥がれずに厚くなり、出口を塞いでしまいます。過剰な皮脂と混ざり合って、毛穴の中に栓(=コメド)を作ってしまうのです 。例えるなら、「管の出口が、粘着テープで塞がれてしまう」ような状態です。
3. アクネ菌が増える(Cutibacterium acnes の増殖)
アクネ菌(以前はプロピオニバクテリウム・アクネスと呼ばれていました)は、普段から私たちの皮膚に住んでいる常在菌の一種です。しかし、毛穴が詰まって皮脂が溜まった環境は、アクネ菌にとって格好の住処となり、増殖しやすくなります 。例えるなら、「塞がれた管の中に、菌が好むエサ(皮脂)が豊富になり、菌がどんどん増えていく」状態です。
4. 炎症が起こる(炎症)
増殖したアクネ菌や、毛穴に溜まった皮脂などが刺激となって、体の免疫システムが反応し、毛穴の周りに炎症が起こります。これが、にきびの赤みや腫れ、膿の原因となります 。例えるなら、「体の防衛隊(免疫細胞)が、異常事態(菌の増殖や毛穴の詰まり)に対して攻撃を開始し、戦い(炎症)が起こる」状態です。
これら4つの要因が、にきび発生の主なメカニズムです。
他にどんなことが影響するの?
上記の4つの要因に加えて、以下のようなことも、にきびの発生や悪化に関わっていると考えられています。
遺伝的な要因
ご両親や兄弟姉妹ににきびがひどかった方がいる場合、お子さんもにきびができやすい体質を受け継いでいる可能性があります 。
ホルモンバランス
思春期のホルモン変動が主な原因ですが、それ以外にも、ストレスや睡眠不足、あるいは(まれですが)何らかの病気によってホルモンバランスが乱れると、にきびが悪化することがあります。特に幼児期のにきびや、月経周期と連動するにきびなどは、ホルモンの影響を考慮する必要があります 。
食事
食事とにきびの関係は、まだ完全には解明されていませんが、いくつかの研究で、血糖値を上げやすい食品(甘いもの、炭水化物など)や乳製品の摂りすぎが、にきびを悪化させる可能性が指摘されています。これは、インスリン様成長因子(IGF-1)などのホルモンを介した影響が考えられています 。しかし、特定の食品がすべての人に悪影響を与えるわけではなく、日本のにきび治療ガイドラインでも、「特定の食べ物を一律に制限することは推奨しない」とされています 。バランスの取れた食事を心がけることが基本ですが、もし特定の食べ物を食べた後ににきびが悪化するような気がする場合は、自己判断で極端な食事制限をするのではなく、医師に相談してみましょう。
ストレス
ストレスが直接にきびを作るわけではありませんが、ストレスによってホルモンバランスが乱れたり、無意識に顔を触ったりすることで、にきびが悪化する可能性があります 。
物理的な刺激(機械的痤瘡 / Acne Mechanica)
ヘルメット、帽子、前髪、マスク、衣類の摩擦などが、特定の部位のにきびを悪化させることがあります。これは「機械的痤瘡」と呼ばれます。特に、燕三条地域で盛んな産業(工場でのヘルメット)、スポーツ(自転車、野球など)でのヘルメット着用や、アウトドア活動での帽子、汗をかいた後の衣類のこすれなどは注意が必要です。
間違ったスキンケア
ゴシゴシ洗いすぎる、洗浄力の強すぎる洗顔料を使う、保湿をしない、といった間違ったケアは、肌のバリア機能を損ない、かえってにきびを悪化させることがあります。
「汚れ」が原因ではない!
ここで強調したいのは、にきびは「不潔だから」「顔をちゃんと洗っていないから」できるわけではないということです 。黒ニキビの黒い点も、汚れではなく、皮脂や角質が酸化したものです 。もちろん、適切な洗顔は大切ですが、洗いすぎや擦りすぎは逆効果です。にきびの本当の原因は、これまで説明してきたような、ホルモン、皮脂、毛穴の詰まり、アクネ菌、炎症といった、体の内部の要因が複雑に関係しているのです。このことを理解すれば、「ちゃんと洗っているのにどうして?」という悩みや、お子さんを不必要に責めてしまうことを避けられます。
治療法
子どものにきび治療は、一人ひとりの状態に合わせて行う「オーダーメイド治療」が基本です。年齢、にきびの種類(コメド主体か、炎症性か、混在しているか)、重症度、できている場所、肌質、そしてお子さんの生活スタイルなどを総合的に判断して、最適な治療法を選択します 。 治療には時間がかかり、根気が必要です。通常半年以上かかりますし、治った後も継続的に治療を続けるとにきびの予防にもつながります。「すぐに治る」と期待しすぎず、焦らず、医師の指示に従って治療を続けることが大切です 。
治療の目標
にきび治療の目標は、単に今あるにきびを治すことだけではありません。
- 目に見えるにきび(コメド、炎症性皮疹)を減らす
- 新しいにきびができるのを防ぐ
- 炎症をできるだけ早く、効果的に抑える
- にきび跡(瘢痕)や色素沈着を残さない
これらの目標を達成するために、様々な治療法を組み合わせていきます。
主な治療法の種類(日本皮膚科学会ガイドラインに基づく)
塗り薬(外用薬)
にきび治療の基本であり、特に軽症から中等症の場合の中心となります。皮脂の分泌を抑えたり、毛穴の詰まりを改善したり、アクネ菌を殺菌したり、炎症を抑えたりする作用があります。
過酸化ベンゾイル(BPO)[例: ベピオ®ゲル/ローション]
アクネ菌に対する殺菌作用と、毛穴の詰まりを改善する作用(角質剥離作用)があります。様々な濃度の製品がありますが、ガイドラインでは2.5%のものが推奨されています 。使い始めに、乾燥、赤み、ヒリヒリ感が出ることがありますが、徐々に慣れることが多いです。漂白作用があるため、髪や衣類につかないよう注意が必要です。
外用レチノイド [例: アダパレンゲル (ディフェリン®ゲル)]
ビタミンA誘導体の一種で、毛穴の詰まり(コメド)の根本原因である角化異常を正常化する働きがあります。にきびの初期段階であるマイクロコメドにも作用するため、新しいにきびをできにくくする効果が高く、にきび治療の基本薬(ベース)として、また、良くなった後の維持療法としても非常に重要です 。効果が出るまで時間がかかりますが、根気強く続けることが大切です。使い始めに乾燥や赤み、皮むけなどの刺激症状が出ることがありますが、保湿剤を併用したり、塗る回数や量を調整したりすることで対応できます。日光過敏性を高めることがあるため、紫外線対策が必要です。アダパレン0.1%ゲルは強く推奨されています 。
外用抗菌薬
アクネ菌を殺菌し、炎症を抑える働きがあります。主に赤ニキビや黄ニキビに使われます。重要な注意点として、抗菌薬の効きが悪くなる「薬剤耐性菌」の出現を防ぐため、単独で長期間使用することは推奨されていません 。通常、過酸化ベンゾイルや外用レチノイドと併用し、炎症が改善したら中止を検討します。
配合剤
異なる作用を持つ成分を組み合わせた塗り薬です。例えば、抗菌薬とBPO、あるいはレチノイドとBPOが一緒になっています。複数の薬を塗る手間が省け、相乗効果も期待できるため、ガイドラインでも強く推奨されています 。
その他
硫黄カンフルローションなど、従来からある治療薬が使われることもあります。
飲み薬(内服薬)
中等症から重症の炎症性のにきび(赤ニキビや黄ニキビが多い、しこりがあるなど)や、塗り薬だけでは効果が不十分な場合に用いられます。
内服抗菌薬 [例: ドキシサイクリン (ビブラマイシン®), ミノサイクリン (ミノマイシン®), ロキシスロマイシン (ルリッド®)]
体の中からアクネ菌を減らし、炎症を抑える効果があります。特にドキシサイクリンとミノサイクリンは有効性が高く、ガイドラインでも推奨されています 。非常に重要な注意点として、塗り薬の抗菌薬と同様に、薬剤耐性菌の問題から、必要最小限の期間(ガイドラインでは3~4ヶ月を目安に見直しが推奨 )にとどめるべきとされています。また、必ず過酸化ベンゾイルや外用レチノイドなどの抗菌作用のない塗り薬と併用することが、効果を高め、耐性菌を防ぐために強く推奨されています 。
イソトレチノイン内服 [例: アキュテイン®, ロアキュタン®, イソトロイン®など (日本では保険適用外、医師の判断で自費診療として用いられる場合あり)]
ビタミンA誘導体の飲み薬で、非常に効果が高い治療薬です。皮脂の分泌を強力に抑え、毛穴の詰まりを改善し、炎症も抑える作用があります。重症のしこりや嚢腫を伴うにきび、他の治療法で効果がない難治性のにきび、重度の瘢痕(にきび跡)を引き起こすにきびなどに用いられます。高い効果がある反面、副作用(皮膚や粘膜の乾燥、血液検査値の異常など)に注意が必要であり、特に妊娠中の女性が内服すると胎児に奇形を起こすリスクが極めて高いため、厳重な管理(避妊の徹底など)が必要です。経験豊富な皮膚科専門医のもとで、慎重に使用されるべき薬剤です。
ホルモン療法(女性の場合)
一部の低用量経口避妊薬(ピル)は、アンドロゲンの働きを抑えることで、にきびに効果を示すことがあります。特に月経周期に関連して悪化するにきびや、中等症から重症のにきびを持つ女性で、避妊も希望する場合などに選択肢となります 。抗アンドロゲン作用のあるスピロノラクトンという利尿薬が使われることもありますが、日本のガイドラインでは推奨されていません 。
漢方薬
一部は補助的に用いられることもあります。
当院で行う処置(保険適用外診療を含む)
ケミカルピーリング
前述の通り、角質ケアとにきび改善を目的とします。ガイドラインではC1(選択肢の一つとして推奨)。
面皰圧出
前述の通り、コメドの内容物を除去します 。
エレクトロポレーション
前述の通り、有効成分の浸透を高めます。
ヒーライト(LED治療)
前述の通り、炎症抑制と肌の回復を促します。
サブシジョン
萎縮性瘢痕に対して行われる治療です。
ステロイド局所注射
大きく腫れて痛いしこり(結節や嚢腫)に、ごく少量のステロイドを直接注射する方法です。炎症を速やかに抑え、痛みを和らげ、跡になるリスクを減らす効果が期待できます。ガイドラインではBまたはC1(推奨または選択肢の一つ)。
維持療法
にきびは慢性的な病気であり、一度良くなっても再発しやすい特徴があります。そのため、症状が改善した後も、良い状態を維持し、再発を防ぐための「維持療法」を続けることが非常に重要です 。多くの場合、毛穴の詰まりを防ぐ作用のある外用レチノイド(アダパレンなど)や、過酸化ベンゾイル、あるいはそれらの配合剤を、症状が落ち着いた後も継続して使用します。アダパレンとBPOの配合ゲルは維持療法としても強く推奨されています 。治療のゴールは「にきびがゼロになったら終わり」ではなく、「にきびができにくい肌の状態を保つこと」にあると考えましょう。
主なにきび治療法の概要
| 治療の種類 | 具体例(一般名/主な商品名例) | 主な作用 | 対象となるにきび | 主な注意点・副作用 |
|---|---|---|---|---|
| 塗り薬 |
過酸化ベンゾイル (BPO) [ベピオ®] |
抗菌、角質剥離 |
コメド、炎症性皮疹 | 乾燥、刺激感、赤み、漂白作用 |
| 外用レチノイド [アダパレン (ディフェリン®)] | 角化正常化、抗炎症 | コメド(特に重要)、炎症性皮疹、維持療法 | 乾燥、刺激感、皮むけ、日光過敏 | |
| 外用抗菌薬[ナジフロキサシン (アクアチム®)][オゼノキサシン (ゼビアックス®)] | 抗菌、抗炎症 | 炎症性皮疹(赤・黄) | 耐性菌リスクのため単独長期使用は避けるBPO 等との併用推奨 |
|
| 配合剤(エピデュオ®デュアック®) | 複数の作用を併せ持つ | コメド、炎症性皮疹、維持療法(アダパレン/BPO) | 各成分の副作用の可能性、利便性高い | |
| 飲み薬 | 内服抗菌薬 [ドキシサイクリン (ビブラマイシン®)][ミノサイクリン (ミノマイシン®)][ロキシスロマイシン (ルリッド®)] | 抗菌、抗炎症 | 中等症~重症の炎症性皮疹 | 耐性菌リスクのため短期使用が原則、塗り薬との併用必須 、胃腸症状、めまい(ミノサイクリン)、光線過敏(ドキシサイクリン)など |
| イソトレチノイン [アキュテイン®等 (保険適用外)] | 皮脂分泌抑制、角化正常化、抗炎症 | 重症・難治性のにきび | 乾燥(皮膚、粘膜)、血液検査値異常、催奇形性(妊娠絶対禁忌)、専門医による厳重管理必要 | |
| ホルモン療法(女性) [低用量ピル] | 抗アンドロゲン作用 | 中等症~重症(女性)、月経関連の悪化 | 血栓症リスク(まれ)、吐き気など | |
| 処置 | ケミカルピーリング | 角質除去、毛穴詰まり改善 | コメド、軽度の炎症性皮疹、くすみ | 刺激感、赤み、乾燥 |
| 面皰圧出 | コメド内容物の除去 | コメド(白・黒) | 処置時の軽度の痛み、一時的な赤み | |
| ステロイド局所注射 | 強力な抗炎症作用 | 大きな結節、嚢腫 | 皮膚萎縮、血管拡張(まれ) |
この表はあくまで概要です。どの治療法が最適かは、診察の上で医師が判断します。疑問や不安な点があれば、遠慮なくご相談ください。
日常生活で気をつけるポイント
にきび治療の効果を高め、新しいにきびを予防するためには、毎日のスキンケアや生活習慣を見直すことも大切です。薬による治療と合わせて、以下の点に気をつけてみましょう。
やさしいスキンケアを習慣に
洗顔は1日2回、やさしく
朝と夜の1日2回、そして汗をたくさんかいた後には、洗顔料を使って顔を洗いましょう 。洗顔料は、低刺激性のものを選び、よく泡立ててから、肌をこすらずに泡で包み込むようにやさしく洗います 。特にTゾーン(おでこ、鼻)やUゾーン(あご周り)は皮脂が多いので丁寧に。ただし、ゴシゴシ洗いは禁物です。
すすぎは十分に
洗顔料が肌に残らないように、ぬるま湯(熱すぎない温度)で、髪の生え際やフェイスラインまで、しっかりとすすぎましょう。
拭くときもやさしく
清潔なタオルで、こすらずに、軽く押さえるようにして水分を吸い取ります 。
保湿は必須
「にきび肌はオイリーだから保湿は不要」というのは間違いです。洗顔後や、にきびの治療薬を塗る前(または後、医師の指示に従ってください)には、必ず保湿をしましょう。にきび治療薬には肌を乾燥させるものも多く、乾燥はかえって皮脂の分泌を促したり、肌のバリア機能を低下させたりすることがあります。オイルフリー(油分を含まない)、ノンコメドジェニック(にきびができにくい処方)と表示された、低刺激性の保湿剤(ローションやジェルタイプなど)を選びましょう 。
製品選びのポイント
スキンケア製品やメイク用品は、「ノンコメドジェニックテスト済み」「低刺激性」「アレルギーテスト済み」などの表示があるものを選ぶと良いでしょう 。
これはNG!避けるべきこと
にきびを触らない・潰さない
気になる気持ちは分かりますが、にきびをいじったり、潰したりするのは絶対にやめましょう 。爪や指についた雑菌が入り込んで炎症が悪化したり、周りの皮膚を傷つけたりして、にきび跡(瘢痕)や色素沈着の最大の原因になります。例えるなら、火に油を注ぐようなものです。
洗いすぎ・擦りすぎ
1日に何度も洗顔したり、スクラブ入りの洗顔料でゴシゴシこすったり、ふき取り化粧水で強く拭いたりするのは、肌に必要な皮脂まで奪い、バリア機能を壊して、かえってにきびを悪化させる可能性があります 。
刺激の強い製品
アルコールが多く含まれた化粧水や、使ったときにヒリヒリ、ピリピリするような刺激を感じる製品は避けましょう。
髪型や身の回りの清潔も大切
髪
髪が顔にかからないように、特に寝るときはまとめるなど工夫しましょう。整髪料(ワックス、スプレーなど)が額やフェイスラインにつくと、にきびの原因になることがあります。髪自体も清潔に保ちましょう。
寝具
枕カバーやシーツは、皮脂や汗、雑菌が付着しやすいので、こまめに洗濯して清潔に保ちましょう。
メイクについて
製品選び
メイクをする場合は、スキンケア同様、オイルフリー、ノンコメドジェニックのものを選びましょう 。パウダーファンデーションの方が、リキッドタイプよりも毛穴を塞ぎにくい傾向があります。
メイク落としは丁寧に、でも手早く
帰宅したら、できるだけ早くメイクを落としましょう 。クレンジング剤は、肌への負担が少ないミルクタイプやジェルタイプなどがおすすめです。ゴシゴシこすらず、やさしくなじませて、短時間で済ませるのがコツです 。すすぎ残しがないように、特に髪の生え際やフェイスラインは念入りに。
道具も清潔に
パフやスポンジ、ブラシなどのメイク道具は、雑菌が繁殖しやすいので、定期的に洗うか、新しいものに取り替えましょう 。
無理に隠さない
にきびを隠そうとして厚塗りになると、かえって毛穴を塞ぎ、悪化させてしまうことがあります。ポイント的にコンシーラーを使うなど、工夫してみましょう。ガイドラインでも、QOL(生活の質)向上のために、低刺激性・ノンコメドジェニックな製品を用いたメイク指導は
選択肢の一つとされています 。
紫外線対策を忘れずに
紫外線は、にきびの炎症を悪化させたり、にきび跡の色素沈着を濃くしたりする原因になります。また、にきび治療薬の中には、肌を紫外線に敏感にするもの(特に外用レチノイドなど)があります。季節や天候に関わらず、毎日、日焼け止めを塗る習慣をつけましょう。ノンコメドジェニックで、肌にやさしいタイプ(紫外線吸収剤フリーなど)を選び、SPF30・PA++以上を目安に。汗をかいたら塗り直すことも大切です。帽子や日傘の利用も有効です。
食生活と生活リズム
バランスの取れた食事
特定の食品だけを極端に避けたり、摂りすぎたりせず、野菜、果物、タンパク質などをバランス良く摂ることを心がけましょう。ガイドラインでは一律の食事制限は推奨されていませんが 、もし特定の食品(例えば、チョコレートやスナック菓子、甘い飲み物など)を食べるとにきびが悪化すると感じる場合は、記録をつけてみて、医師に相談してみましょう。
水分補給
体の水分が不足しないように、こまめに水を飲む習慣をつけましょう。
十分な睡眠
睡眠不足は、ホルモンバランスの乱れやストレスにつながり、肌のターンオーバー(生まれ変わり)にも影響します。質の良い睡眠を十分にとるように心がけましょう。
ストレスを溜めない
適度な運動や趣味など、自分に合った方法でストレスを発散することも大切です 。
三条市・燕市などの地域性を踏まえて
自然豊かな県央地域では、お子さんがアウトドアで活動する機会も多いと思います。その際に、いくつか気をつけたい点があります。
活動後のケア
ハイキングやキャンプ、川遊び、スポーツなどで汗をかいたり、泥で汚れたりした後は、できるだけ早くシャワーを浴びるか、やさしく洗顔して、汗や汚れ、日焼け止めなどを洗い流しましょう。
摩擦に注意
自転車に乗るときのヘルメット、野球帽、登山用の帽子、リュックサックの肩紐などが、長時間肌に触れてこすれると、その部分に「機械的痤瘡」ができやすくなります。ヘルメットや帽子の内側を清潔に保つ、サイズの合ったものを選ぶ、汗をかいたらこまめに拭くなどの工夫をしましょう。
虫刺されとの見分け
アウトドアでは虫に刺されることも多いですね。虫刺されも赤いブツブツができますが、通常、急に現れて強いかゆみを伴い、中心に刺し口が見えることがあります。一方、にきびは徐々に現れ、かゆみがないか、あっても虫刺されほど強くないことが多いです。特に草むらや山に入った後にできたブツブツが、虫刺されかにきびか判断に迷う場合は、自己判断せずに皮膚科で診てもらいましょう。
これらの日常生活でのポイントは、薬による治療をサポートし、にきびができにくい肌環境を作るための土台となります。特別なことをするのではなく、「やさしく洗う」「しっかり保湿する」「むやみに触らない」「紫外線から守る」という基本を、毎日コツコツ続けることが大切です。複雑なケアよりも、シンプルで継続しやすい方法を見つけることが、成功の鍵です。
よくある質問
にきびについて、患者さんや保護者の方からよくいただく質問にお答えします。
-
- ニキビは自然に治りますか?
-
軽いニキビ、特に生まれたばかりの赤ちゃんのニキビ(新生児にきび)は、自然に消えることもあります 。しかし、中等症以上のニキビや、炎症が強いニキビ、しこりができるようなニキビは、自然治癒を待っている間に悪化したり、跡(瘢痕)が残ってしまったりする可能性が高いです 。特に思春期以降のにきびは慢性化しやすく、適切な治療を受けずに放置すると、治りにくい跡になってしまうことがあります。「そのうち治るだろう」と自己判断せず、早めに皮膚科に相談することが、きれいに治すための近道です。
-
- 市販薬で治せますか?
-
市販薬にも、殺菌成分(サリチル酸など)や抗炎症成分が含まれているものがあり、ごく軽いニキビには効果がある場合もあります。しかし、皮膚科で処方される薬(アダパレン、過酸化ベンゾイル、処方箋抗菌薬など)は、市販薬よりも有効成分の濃度が高かったり、作用機序が異なったりするため、より高い効果が期待できます 。市販薬を数週間使っても改善しない場合、赤ニキビや黄ニキビが多い場合、ニキビが広範囲にある場合、あるいは跡になりそうな場合は、市販薬での対応には限界があるため、皮膚科を受診することをおすすめします。
-
- いつ皮膚科を受診すべきですか?
-
以下のような場合は、早めに皮膚科を受診することを検討してください。
- 幼児期(1歳~7歳)にニキビのようなものができた場合(他の病気の可能性も考えるため)
- 市販薬を使っても良くならない、あるいは悪化する場合
- 赤ニキビや黄ニキビ、痛みを伴うしこりなど、炎症が強いニキビが多い場合
- ニキビの数が多く、広範囲に広がっている場合
- ニキビ跡(へこみ、盛り上がり、赤み、色素沈着)ができ始めている場合
- ニキビが原因で、学校に行きたくない、人と会いたくないなど、精神的に大きな負担になっている場合
- 自分でのケア方法や治療法について、専門家のアドバイスが欲しい場合
一般的に、ニキビは早期に治療を開始するほど、跡を残さずにきれいに治せる可能性が高まります 。
-
- 治療にはどのくらい時間がかかりますか?
-
ニキビ治療は、残念ながらすぐに結果が出るものではありません。効果を実感し始めるまでに、通常4週間から8週間程度かかります。そして、満足のいく状態になるまでには、3ヶ月以上かかることも珍しくありません 。大切なのは、すぐに効果が見えなくても、医師の指示通りに根気強く治療を続けることです。また、ニキビは慢性的な病気なので、良くなった後も再発を防ぐための「維持療法」を続けることが重要になります 。焦らず、じっくりと取り組みましょう。
-
- ニキビ跡は治せますか?
-
最も大切なのは、ニキビ跡を作らないように、アクネ菌が増殖し炎症が起きている段階(アクティブなニキビ)を早期に、かつ効果的に治療することです。一度できてしまったニキビ跡(特に凹凸のある瘢痕)を完全に元通りにするのは難しいのが現状です。しかし、諦める必要はありません。皮膚科では、ニキビ跡の種類(赤み、色素沈着、へこみ、盛り上がり)に応じて、様々な治療法があります。例えば、赤みにはレーザー(Vビームなど)、色素沈着には塗り薬やケミカルピーリング、へこみにはサブシジョン、レーザー(CO2フラクショナルレーザーなど)やダーマペン(微細な針で肌の再生を促す治療)、盛り上がりにはステロイド注射などが用いられます。ガイドラインでは、へこんだ跡に対するヒアルロン酸などの充填剤注射はC2(行ってもよいが推奨はしない)とされています 。まずは、現在できているニキビをしっかりと治療し、肌の状態が落ち着いてから、跡の治療について医師と相談するのが良いでしょう。当院でも各種レーザー治療やダーマペンなど、ニキビ跡に対する治療(一部保険適用外)を行っております。
-
- 食事はニキビに関係ありますか?
-
食事とニキビの関係については、様々な情報があり、気にされている方も多いと思います。研究レベルでは、血糖値を上げやすい食品(高GI食)や乳製品が一部の人のニキビを悪化させる可能性が指摘されていますが 、すべての人に当てはまるわけではありません。現在の日本のガイドラインでは、「特定の食べ物を一律に制限することは推奨しない」とされています 。大切なのは、栄養バランスの取れた食事を心がけることです。もし、ご自身やお子さんで、「これを食べるとニキビが悪化する気がする」という食品があれば、それを記録しておき、診察時に医師に相談してみてください。自己判断で極端な食事制限を行うことは、成長期のお子さんにとっては特に避けるべきです。
-
- 遺伝しますか?
-
はい、ニキビのできやすさには遺伝的な要因も関与していると考えられています 。ご両親や兄弟姉妹にニキビがひどかった経験がある場合、お子さんもニキビができやすい、あるいは重症化しやすい傾向があるかもしれません。しかし、遺伝だからといって諦める必要はありません。遺伝的な素因があったとしても、早期からの適切な治療とスキンケアによって、ニキビをコントロールし、跡を残さないようにすることは十分に可能です。
まとめ
子どものにきび(尋常性痤瘡)は、単なる「若者の悩み」ではなく、毛穴と皮脂腺に起こる慢性の炎症性疾患です 。ホルモンの影響、皮脂の増加、毛穴の詰まり、アクネ菌の増殖、そして体の炎症反応が複雑に関与し、新生児期から思春期まで、様々な年齢で見られます 。
最もお伝えしたいのは、「にきびは治療できる病気であり、放置せずに皮膚科で適切な治療を受けることが、きれいに治し、将来の肌への影響(にきび跡)を最小限にするための最善の方法である」ということです 。特に、炎症が強い場合や、跡が残り始めている場合は、早めの受診が肝心です。
当院では、県央地域の地域医療に貢献する皮膚科クリニックとして、お子さんから大人まで、一人ひとりの患者様に寄り添った診療を心がけています。最新の医学的知見と治療ガイドライン に基づき、塗り薬、飲み薬、そして当院で導入しているケミカルピーリング、エレクトロポレーション、ヒーライトなどの処置も組み合わせながら、お子さんに最適な治療プランをご提案します。また、日々のスキンケアや生活習慣についても、丁寧にアドバイスさせていただきます。
にきびは、見た目の問題だけでなく、お子さんの自信や気持ちにも影響を与えることがあります。「たかがニキビ」と思わず、どうぞお気軽に当院にご相談ください。一緒に、健やかで、きれいな肌を目指しましょう。
よく似た症状の別の病気(鑑別疾患)
子どもの顔や体にできるブツブツは、にきび以外にも様々な皮膚の病気が考えられます。見た目が似ていても、原因や治療法が全く異なる場合があるため、自己判断せずに皮膚科専門医の診察を受けることが非常に大切です。以下に、にきびと間違えやすい代表的な病気を挙げます。
・新生児頭部膿疱症 (Neonatal Cephalic Pustulosis)
生後数週間以内に、顔や頭に小さな膿疱や赤いポツポツが多数出現。通常かゆみはなく、自然に消えることが多い 。
・乳児脂漏性皮膚炎 (Infantile Seborrheic Dermatitis)
生後数ヶ月までの赤ちゃんに見られ、頭皮(フケのようなカサブタ)、眉毛、額、耳の後ろ、わきの下などに、黄色っぽいかさぶたや、赤み、ベタベタした湿疹ができる。かゆみは軽いことが多い 。
・アトピー性皮膚炎 (Atopic Dermatitis)
強いかゆみを伴う湿疹が、良くなったり悪くなったりを繰り返す。乳児期は顔や頭、幼児期以降は肘や膝の裏などにできやすい。乾燥肌がベースにあることが多い 。
・汗疹(あせも)/ 汗腺膿瘍 (Miliaria / Sweat Gland Abscess)
汗をたくさんかいた後に、汗の出口が詰まってできる。小さな水ぶくれ(水晶様汗疹)、赤いポツポツ(紅色汗疹)、時に膿をもつ(深在性汗疹、汗腺膿瘍)。かゆみを伴うことが多い 。
・伝染性軟属腫(水いぼ)(Molluscum Contagiosum)
ウイルス感染症。光沢のある、中央が少し凹んだ(臍窩形成)、肌色~ピンク色のドーム状の小さなイボが多発する。通常かゆみはない 。
・伝染性膿痂疹(とびひ)(Impetigo)
細菌感染症。水ぶくれができ、それが破れてジクジクし、黄色っぽいかさぶたが付着する。かゆみが強く、掻いた手で触ると他の場所に「飛び火」するように広がる 。
・毛包炎 (Folliculitis)
毛穴に細菌などが感染して炎症を起こしたもの。毛穴に一致して、赤いポツポツや膿をもった小さなできものができる。
・稗粒腫 (Milium)
目元などにできやすい、1~2mm程度の硬い、白い粒々。毛穴に角質が溜まったもの。炎症はない。
・口囲皮膚炎 / 小児期肉芽腫性口囲皮膚炎 (Perioral Dermatitis /Childhood Granulomatous Periorificial Dermatitis)
口の周り、鼻の周り、目の周りなどに、小さな赤いポツポツや肉芽腫(にくげしゅ)と呼ばれるしこりができる。唇のすぐきわは避けてできることが多い。ステロイド外用薬が誘因・悪化要因になることがある 。
・単純ヘルペス (Herpes Simplex)
ウイルス感染症。口唇やその周りに、小さな水ぶくれが集まってでき、ピリピリとした痛みを伴うことが多い。アトピー性皮膚炎があると広範囲に広がる(カポジ水痘様発疹症)ことがある 。
・水痘(みずぼうそう)(Chickenpox)
ウイルス感染症。発熱とともに、赤い斑点、水ぶくれ、かさぶたが混在した発疹が全身に出現する。強いかゆみを伴う 。
・伝染性紅斑(りんご病)(Erythema Infectiosum)
ウイルス感染症。頬がリンゴのように赤くなり、その後、腕や脚にレース状の赤い発疹が広がる。発熱や関節痛を伴うこともある 。
・ 虫刺され (Insect Bites)
蚊、ブヨ、ダニなどに刺されると、赤い腫れやかゆみの強いブツブツができる。屋外活動後などに急に出現することが多い。
・接触皮膚炎(かぶれ)(Contact Dermatitis)
化粧品、金属、植物、消毒薬など、特定の物質に触れることで、触れた部分に一致して赤み、かゆみ、ブツブツ、水ぶくれなどができる。
・扁平疣贅(へんぺいゆうぜい)(Flat Warts)
ウイルス性のイボの一種。顔や手の甲などに、平らに盛り上がった、肌色~やや褐色の小さなイボが多発する。
・毛孔性苔癬(もうこうせいたいせん)(Keratosis Pilaris)
二の腕や太もも、時に頬などに、毛穴に一致してザラザラとした小さなブツブツが多数できる。遺伝的な要因が関与。
・ 酒皶(しゅさ)(Rosacea)
主に成人に見られるが、まれに小児でも発症。顔の中心部(鼻、頬、額、あご)に、持続的な赤み、毛細血管の拡張、ニキビに似た赤いブツブツや膿疱ができる。コメド(白・黒ニキビ)は見られないのが特徴 。
・薬剤性発疹(薬疹)(Drug Eruption)
薬の副作用として、様々な形の発疹(赤い斑点、ブツブツ、蕁麻疹様など)が全身に出現することがある。
・粉瘤腫(アテローム)(Epidermal Cyst)
皮膚の下に袋状の構造物ができ、中に垢(角質)や皮脂が溜まったもの。ドーム状に盛り上がり、中央に黒い点(開口部)が見えることがある。細菌感染を起こすと赤く腫れて痛む 。
・脂腺腫(結節性硬化症の部分症状)(Adenoma Sebaceum / TuberousSclerosis)
まれな遺伝性疾患の部分症状として、顔の中心部(鼻の周りなど)に、血管線維腫と呼ばれる赤~肌色の小さな硬いブツブツが多発する。
これらは一例であり、他にも様々な皮膚の病気があります。正確な診断のためにも、気になる症状があれば、ぜひ皮膚科専門医にご相談ください。