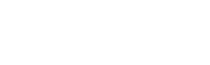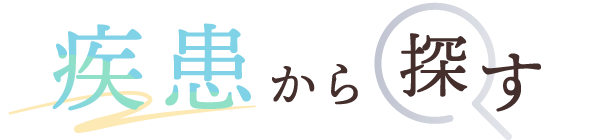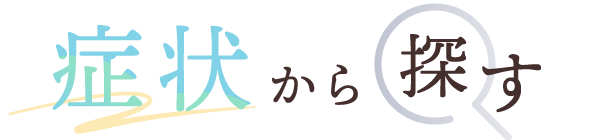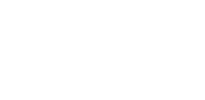- HOME
- みずいぼ
みずいぼ(伝染性軟属腫)とは
みずいぼってどんな病気?
みずいぼの正式名称は「伝染性軟属腫(でんせんせいなんぞくしゅ)」といい、ウイルスによる皮膚の感染症です。その名の通り、非常に感染力が強く、特に幼児期から学童期のお子さんに多く見られます。 実際、お子さんの5~10%が水いぼに感染すると言われています 。
みずいぼは、肌色から少し白っぽい色の、小さく盛り上がったぶつぶつ(丘疹)として現れます。その大きさは、米粒くらいからエンドウ豆くらいまで、通常は直径1~5mm程度です。表面はつるつるしていて光沢があり、よく見ると中央が少しへこんでいるのが特徴です。この中央のへこみは、「えくぼ」のように見えることもあります。
みずいぼは、最初は1つや2つでも、放っておくと次第に数が増えていくことが多いです。初期の段階では、ほとんど症状がなく、痛みやかゆみを伴うことも少ないため、気づかないうちに広がってしまうことがあります。しかし、時にはかゆみが出たり、お子さんが無意識に引っ掻いてしまったりすることで、感染が拡大することがあります。
原因となるウイルス
みずいぼの原因は、伝染性軟属腫ウイルス(Molluscum Contagiosum Virus -MCV)という、ポックスウイルス科に属するウイルスです。このウイルスは、人に特有のウイルスで、他の動物には感染しません。
みずいぼの原因となるウイルスは、一般的なイボ(尋常性疣贅)の原因となるヒト乳頭腫ウイルス(HPV)とは全く別の種類のウイルスです(細かいようですが意外と重要です)。
感染経路について
伝染性軟属腫ウイルスは、人から人へと非常に簡単に感染します。主な感染経路は以下の通りです。
直接的な接触感染
みずいぼができている皮膚に直接触れることで感染します。例えば、お子さん同士が遊んでいる時などに、肌と肌が触れ合うことで感染が広がる可能性があります。
間接的な接触感染
ウイルスが付着したタオル、衣類、おもちゃ、プールなどで使用する浮き輪やビート板などを共有することでも感染します。
自己感染
みずいぼを掻いたり、潰したりした手で体の他の部分に触れると、その部分にも感染が広がり、みずいぼが増えてしまうことがあります。
特に、皮膚に小さな傷や乾燥がある場合、あるいはアトピー性皮膚炎など皮膚のバリア機能が低下しているお子さんは、ウイルスが侵入しやすく、感染しやすいと言われています。保育園や幼稚園、プールなど、お子さんたちが集団で過ごす場所では、接触する機会が多いため、みずいぼが広がりやすい環境と言えるでしょう。
プールでの感染についてですが、プールの水自体が原因で感染することはありません。プールの水は通常、塩素で消毒されているためウイルスは死滅します。感染のリスクが高まるのは、プールサイドや更衣室での直接的な接触や、タオルなどの共有によるものです。みずいぼに感染したお子さんがプールで泳げるかどうかは各施設の判断で異なります。
感染してから症状が現れるまでの潜伏期間は、通常2週間から数ヶ月と幅広いです。このため、いつどこで感染したのかを特定するのは難しい場合があります。
伝染性軟属腫ウイルスは、皮膚の毛穴の中で増殖すると考えられています。そのため、手のひらや足の裏など、毛穴のない部位にはみずいぼはできません。
まれに、大人もみずいぼに感染することがあります。性行為によって陰部を中心に発症したり、免疫力が低下している場合に感染しやすかったりすることが知られています。
みずいぼの典型的な症状
見た目
みずいぼは、よほど小さくなければその特徴的な見た目で比較的容易に診断できます。通常、直径1~5mm程度の小さな盛り上がりで、表面はつるつるとしていて、まるで真珠のような光沢があります。色は、周囲の皮膚と同じくらいの色か、少し白っぽいことが多いです。
最も特徴的なのは、その中央部分が少しへこんでいることです。これは「臍窩(さいか)」と呼ばれ、みずいぼを見分ける上で重要なポイントとなります。みずいぼを指で軽く押すと、中から白い、粥状のような物質が出てくることがあります。これには、たくさんのウイルスが含まれています。
引っ掻いたり、強く擦ったりすると、みずいぼが破れてしまい、中のウイルスが周囲の皮膚に付着して、さらに新しいみずいぼができてしまうことがあります。また、掻き壊した部分から細菌が入り込み、化膿してしまうこともあります。
好発部位
みずいぼは、体のほとんどどこにでもできる可能性があります。しかし、特にできやすい部位があります。お子さんの場合、体幹(胸、お腹、背中など)、四肢(腕や脚)、首などによく見られます。
また、脇の下や股など、皮膚同士が擦れやすい部位にもできやすい傾向があります。重要な点として、手のひらや足の裏には通常みずいぼはできません。これは、これらの部位には毛穴がないためと考えられています。
かゆみや痛みの有無
みずいぼのほとんどの場合、かゆみや痛みはありません。しかし、お子さんによっては、特に乾燥肌であったり、湿疹を合併していたりする場合に、軽いかゆみを感じることがあります。もし、みずいぼを掻き壊してしまったり、炎症が起こったりすると、痛みを感じることがあります。また、体がウイルスと戦おうとする反応として、みずいぼの周りに炎症が起こり、かゆみが生じることがあります(軟属腫反応)。
みずいぼの診断方法
みずいぼの診断は、通常、皮膚科医による視診(見た目による診断)が基本となります。経験豊富な医師であれば、みずいぼの独特な見た目、つまり小さくて丸い、つるつるした、中央がへこんだ丘疹であることから、ほとんどの場合すぐに診断をつけることができます。また、みずいぼができやすい部位(好発部位)も診断の助けとなります。手のひらや足の裏にはできにくいという特徴も、他の皮膚の病気と区別する上で役立ちます。
ほとんどの場合、みずいぼの診断に特別な検査は必要ありません。しかし、まれに、見た目が典型的でない場合や、他の皮膚の病気と区別する必要がある場合などには、皮膚の一部を採取して顕微鏡で調べる皮膚生検(ひふせいけん)が行われることがあります。特に大人の場合は、見た目だけでは診断が難しいこともあります。
しかし、お子さんの一般的なみずいぼの場合は、皮膚生検が必要になることはほとんどありませんので、ご安心ください。
みずいぼの治療法
みずいぼの治療法には、大きく分けて自然に治るのを待つ方法と、積極的に治療を行う方法があります。どちらの方法を選ぶかは、みずいぼの数や大きさ、お子さんの年齢や状態、そして保護者の方のご希望などを考慮して決定されます。
自然治癒の可能性と期間
みずいぼは、多くの場合、特に治療をしなくても自然に治る病気です。これは、時間が経つにつれてお子さんの体がウイルスに対する免疫を獲得し、自然に排除するようになるためです。
しかし、自然に治るまでの期間には個人差が大きく、一般的には6ヶ月から2年程度かかると言われています。場合によっては、それ以上(3年以上)かかることもあります。この間、みずいぼの数が増えたり、他の部位に広がったりする可能性もあります。
皮膚科で行われる一般的な治療法(摘除、液体窒素療法など)
自然治癒を待つという選択肢もありますが、早く治したい、他の人にうつしたくないなどの理由で、皮膚科で治療を受けることを希望される方も多くいらっしゃいます。皮膚科で行われる主な治療法には、以下のものがあります。
摘除(てきじょ)
専用のピンセット(トラコーマ鑷子など)を使って、一つ一つのみずいぼを丁寧に取り除く方法です。
メリット
直接ウイルスを含む芯を取り除くため、比較的早く治る可能性があります。数が少ない場合には有効な方法です。
デメリット
処置の際に痛みを伴います。痛みを和らげるために、事前に麻酔のテープやクリームを使用することがあります。処置後、わずかに出血することがあります。また、ごくまれにですが、小さな傷跡が残る可能性もあります。
液体窒素療法
非常に低温(-196℃!)の液体窒素を使って、みずいぼを凍らせてしまう治療法です。
メリット
ウイルスに直接ダメージを与えるため、比較的効果が期待できます。
デメリット
処置の際に痛みを感じることがあります。処置後、水ぶくれや血豆ができることがあります。また、一時的に色素沈着が残ったり、ごくまれに傷跡が残ったりする可能性があります。複数回の治療が必要になることが多いです。
その他の治療法
上記以外にも、塗り薬や飲み薬による治療が行われることもあります。塗り薬としては、硝酸銀、水酸化カリウム、イミキモドなどの外用薬が用いられることがあります。飲み薬としては、漢方のヨクイニンなどが補助的に用いられることがあります。これらの治療法は、痛みが少ないというメリットがありますが、効果が出るまでに時間がかかったり、保険適用外となる場合があったりします。
どの治療法を選ぶかは、お子さんの状態や年齢、痛みに弱いかどうかなどを考慮して、医師とよく相談して決めることが大切です。
皮膚科で行われるみずいぼの治療法の比較
| 治療法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 摘除 | ウイルスを直接除去できるため、比較的早く治る可能性がある。病変が少ない場合に有効。 | 痛みを伴う。出血の可能性がある。瘢痕や色素沈着の可能性がある。小さすぎる病変は除去が難しい場合がある。 |
| 液体窒素療法 | 比較的早く治療できる。ウイルスに直接ダメージを与える。 | 痛みを伴う。水ぶくれや血豆ができることがある。瘢痕や色素沈着の可能性がある。複数回の治療が必要な場合が多い。小さすぎる子供には不向きな場合がある。 |
| 塗り薬 | 痛みが少ない。家庭で治療できる場合がある。 | 効果が出るまでに時間がかかる場合がある。保険適用外。効果が弱い場合がある。正常な皮膚に刺激を与える可能性がある。 |
| 飲み薬(ヨクイニンなど) | 副作用が少ない。全身に効果が期待できる。 | 効果が出るまでに時間がかかる。直接的な治療ではない。効果が科学的に十分に証明されていない場合がある。 |
家庭でできるケア(保湿、清潔保持、二次感染予防など)
皮膚科での治療と並行して、ご家庭でのケアも非常に大切です。
保湿
お子さんの肌が乾燥しないように、しっかりと保湿をしましょう。特に乾燥肌やアトピー性皮膚炎のお子さんは、皮膚のバリア機能が低下しているため、こまめな保湿が重要です。お風呂上がりやプールの後など、肌が乾燥しやすいタイミングで保湿剤を塗るように心がけてください。
清潔保持
患部を清潔に保つことも大切です。石鹸をよく泡立てて優しく洗い、シャワーで丁寧に洗い流しましょう。タオルでゴシゴシ擦るのではなく、優しく押さえるようにして水分を拭き取ってください。
二次感染予防
みずいぼを掻いたり、潰したりしないように、お子さんに言い聞かせましょう。掻き壊すと、ウイルスが広がったり、細菌感染を引き起こしたりする可能性があります。爪は短く清潔に保ちましょう。かゆみが強い場合は、冷たいタオルなどで冷やしてあげると楽になることがあります。患部をガーゼや絆創膏、衣類などで覆うことで、掻くのを防ぎ、他の人への感染リスクを減らすこともできます。
家庭内での注意
ご家族間でタオルや洗面用具の共有は避けましょう。手洗いをこまめに行うことも重要です。
プールでの注意
プール自体が感染源ではありませんが、タオルや浮き輪、ビート板などの共有は避けましょう。プールから上がったらシャワーでしっかりと洗い流し、患部を防水性の絆創膏やラッシュガードなどで覆うのも有効です。
民間療法や市販薬に関する注意点
インターネットや口コミで、様々な民間療法や市販薬がみずいぼに効果があると言われていることがありますが、安易に試すのは注意が必要です。特に、市販のイボ取り薬(サリチル酸含有の塗り薬や貼り薬など)は、みずいぼには使用しないでください。これらは、一般的なイボに対して効果がありますが、みずいぼに使うと皮膚を刺激して悪化させてしまう可能性があります。
内服薬のヨクイニンは、市販薬としても販売されており、補助的な治療として用いられることもありますが、効果には個人差があり、即効性も期待できません。使用する場合は、用法・用量を守り、気になる場合は医師に相談しましょう。また、自己判断で抗生物質やステロイドの塗り薬を使用することも避けてください。抗生物質はウイルスには効果がなく、ステロイドは免疫力を低下させてしまい、みずいぼを悪化させる可能性があります。
もし、市販薬や民間療法を検討される場合は、必ず事前に医師に相談し、安全で適切な方法を選ぶようにしてください。
みずいぼの予防法
みずいぼの感染を広げないためには、日頃からいくつかの点に注意することが大切です。
- 基本的な衛生習慣を徹底しましょう。 手洗いをこまめに行い、特に患部に触れた後は必ず手を洗いましょう。タオルやハンカチ、衣類、おもちゃなど、身の回りのものを共有しないようにしましょう。
- プールでの対策も重要です。 プール自体は感染源ではありませんが、プールサイドや更衣室での接触、タオルや浮き輪、ビート板などの共有を避けるようにしましょう。スイミング後はシャワーでしっかりと洗い流しましょう。患部を防水性の絆創膏やラッシュガードで覆うのも有効です。
- 日頃から適切なスキンケアを心がけましょう。 特に乾燥肌やアトピー性皮膚炎のお子さんは、皮膚のバリア機能が低下しているため、保湿をしっかり行うことが大切です。
- 早期の対応も大切です。 もし、みずいぼができてしまった場合は、数が少ないうちに皮膚科を受診して相談することも、感染拡大を防ぐ上で有効な場合があります。
- 集団生活の場では、先生やお友達にもみずいぼがあることを伝え、理解と協力を得ることも大切です。
こんなときは皮膚科を受診しましょう(受診の目安)
お子さんの肌にみずいぼのようなものができた場合、自己判断せずに、以下のようないつかの目安を参考に、皮膚科を受診することをおすすめします。
みずいぼかどうか、はっきりとわからない場合。他の皮膚の病気の可能性もあります。
みずいぼの数が急に増えたり、広範囲に広がったりした場合。
みずいぼが赤く腫れたり、痛みを伴ったり、膿が出たりするなど、炎症や二次感染の兆候が見られる場合。
お子さんが強いかゆみを訴え、日常生活に支障が出ている場合。
目の周りや陰部など、デリケートな部位にみずいぼができた場合。
数ヶ月以上経ってもみずいぼが治る兆候が見られない場合や、なかなか治らないと感じる場合。
アトピー性皮膚炎など、他の皮膚の病気を持っているお子さんの場合、みずいぼが広がりやすいことがあります。
治療法について詳しく知りたい、相談したい場合。
保育園や幼稚園、学校などで、みずいぼの治療や登園に関して指示があった場合。
よくある質問
-
- 感染力はどのくらい強いんですか?
-
みずいぼは、接触することで感染する病気です。特に小さなお子さんは、肌と肌が触れ合う機会が多いため、感染しやすいと言えます。アトピー性皮膚炎など、皮膚のバリア機能が弱いお子さんも感染しやすい傾向があります。しかし、過度に心配する必要はありません。適切な予防策を講じることで、感染のリスクを減らすことができます。
-
- 保育園や幼稚園への登園可否は?
-
みずいぼがあっても、基本的には保育園や幼稚園への登園は可能です。学校保健安全法でも、出席停止の対象となる感染症には定められていません。ただし、患部を衣服や絆創膏などで覆い、直接他の子と接触しないように配慮することが望ましいです。保育園や幼稚園には、みずいぼがあることを事前に伝えておくと、タオルを共有しないなどの対策をしてもらえる場合があります。プールについても、患部を覆うなどの対策をすれば禁止する必要はありませんが、施設によって方針が異なる場合があるので、事前に確認しておくと良いでしょう。
-
- 跡が残る可能性は?
-
みずいぼそのものが、通常、跡を残すことはありません。しかし、みずいぼを強く掻き壊してしまったり、細菌感染を起こして炎症がひどくなったりした場合には、ごくまれに小さな跡が残ってしまう可能性はあります。また、治療法によっては、ごくわずかに跡が残る可能性も否定できませんが、通常は目立たない程度です。大切なのは、みずいぼを掻かないようにすることです。
よく似た症状の別の病気(鑑別疾患)
・尋常性疣贅(いわゆる「いぼ」)
・扁平疣贅
・単純ヘルペス
・水痘(みずぼうそう)
・帯状疱疹
・伝染性膿痂疹(とびひ)
・疥癬
・アトピー性皮膚炎
・接触皮膚炎
・汗疱(かんぽう)
・Gianotti-Crosti症候群
・多形滲出性紅斑
・血管腫(乳児血管腫など)
・色素性母斑(黒子)
・軟線維腫
・汗管腫
・脂漏性角化症(若年者でも稀に)
・尋常性乾癬
・ニキビ(尋常性ざ瘡)
・水疱性類天疱瘡(小児型)
まとめ
みずいぼは、お子さんによく見られるウイルス性の皮膚感染症であり、多くの場合、自然に治るものです。しかし、感染力が強く、他の人にうつしてしまう可能性もあります。ご家庭では、しっかりと保湿を行い、清潔を保ち、掻き壊さないように注意してあげてください。プールなど、集団生活を送る上での注意点も守りましょう。もし、症状が悪化したり、なかなか治らなかったりする場合は、自己判断せずに皮膚科を受診してください。
お子さんの肌のことで心配なことがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。