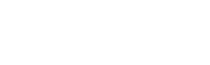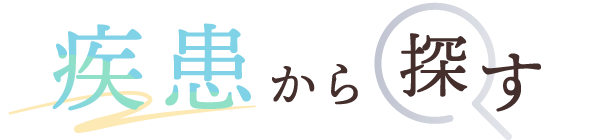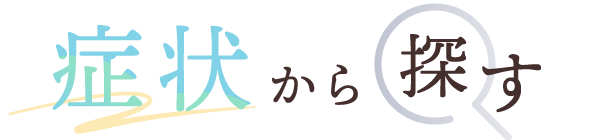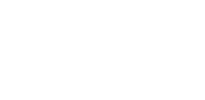- HOME
- 巻き爪
巻き爪とは
古来より、足の爪のトラブルは人々の悩みの種でした。植民地時代には、自身の足のケアを怠り、巻き爪で歩行困難になったイギリス兵が厳しく罰せられたという記録が残っています。
また、南北戦争時代のアメリカ軍のマニュアルには、巻き爪の痛みを和らげるために爪にV字型の切り込みを入れる方法が記載されていましたが、これは実際には効果がありませんでした。医学の歴史を遡ると、古代インドの文献である『スシュルタ・サンヒター』(紀元前6世紀頃)には、患部を熱湯で洗い、ナイフで排膿し、薬用オイルを塗布し、樹脂の粉末を振りかけ、包帯をするという巻き爪の治療法が記述されています。それでも効果がない場合は、熱による焼灼療法が用いられました。古代エジプトの医学文書であるハースト・パピルスには、足の指の腫れを軽減するための約36の治療法が含まれており、その中には巻き爪に対するものも含まれていた可能性があります。
紀元後1世紀のローマの医学者ケルススは、著書『医学について』の中で、ミョウバンと蜂蜜の混合物を患部に塗布することを推奨しました。それでも改善しない場合は、温湿布の後に、方解石、ザクロの皮、銅の鱗、蜂蜜で作られた薬を湿らせた亜麻布で包むことを勧めています。最終手段として、ナイフによる外科手術も言及されています。紀元後4世紀のギリシャの医学者オリバシウスは、砕いた香、鉄、鶏冠石の混合物や、蜂蜜、没食子、酸っぱいザクロの皮、赤銅、焼いた乾燥イチジクを混ぜたものをリニメントとして1日2回包帯の下に塗布する方法を記しています。
7世紀の医学者パウルス・アエギナータは、ヒ素とマンナをワインとスポンジを含ませたリントプラグで覆うという処方を勧めています。ま
た、メスで爪の角を持ち上げて切ることも提案しました。16世紀のフランスの外科医アンブロワーズ・パレは、まっすぐな刃のメスで爪を覆う軟部組織を切開し、赤熱した鉄で焼灼するという治療を行っていました。
17世紀のダニエル・ターナーは、初期の段階ではハサミで患部の爪を切ることを推奨しました。より痛みを伴う症例には、腐食性の粉末や物質、硫酸や硝酸銀を用いて爪を剥がす前に組織を脱落させる方法を勧めています。
19世紀になると、ウォードロップは硝酸銀の使用を提案し、爪の上部にV字型の切り込みを入れる一般的な慣習を支持しました。デュルラッハーは、患部の爪を縦に分割して爪溝の圧力を軽減することを提唱しました。デュピュイトランは、鋭いハサミで爪を半分に切り、潰瘍
に対応する半分を引き剥がすという手術法を記述しました。周囲の組織が過剰な場合は、熱い焼灼器を使用しました。1853年にロバート・リストンが巻き爪の手術に初めて麻酔を使用したことは、患者の苦痛を軽減する上で大きな転換点となりました。
このように、巻き爪は何世紀にもわたって認識され、様々な治療法が試されてきた疾患です。現代医学においては、より科学的根拠に基づいた理解と治療法が確立されています。医学用語では、巻き爪は「onychocryptosis(オニコクリプトーシス)」と呼ばれ、これはギリシャ語の「onyx(爪)」と「kryptos(隠れた)」に由来します。一般的には「陥入爪(かんにゅうそう)」、「unguisincarnatus(ウンギス・インカルナトゥス)」とも呼ばれ、爪の端または側面が周囲の皮膚に食い込むことで炎症や痛みを引き起こす、よく見られる爪の病気です。この状態は、異物である爪が皮膚に刺さることによる異物反応が根本的な原因と考えられています。具体的には、爪の先端や側面にある鋭い爪棘が、周囲の皮膚である爪郭に刺さり込み、炎症、感染、肉芽形成といった一連の反応を引き起こします。巻き爪の正確な発生率は不明ですが、1990年の米国国民健康調査では、巻き爪に関する質問が含まれていました。この調査からもわかるように、巻き爪は決して珍しい病気ではなく、多くの人々が経験する可能性のある一般的な疾患です。
具体的な症状と年齢別の特徴
巻き爪の主な症状は、足の親指の爪の端や側面が周囲の皮膚に食い込むことによる痛みです。初期には、爪の端に触れたり、靴を履いて圧迫されたりしたときに痛みを感じることが多いですが、進行すると、何もしていなくてもズキズキとした痛みが続くことがあります。
痛みとともに、爪の周囲の皮膚が赤く腫れ上がったり、炎症を起こしたりします。さらに悪化すると、爪が皮膚に深く食い込み、傷口から細菌感染を引き起こし、膿が出たり、ジュクジュクしたりすることがあります。慢性的な炎症が続くと、爪の周囲の皮膚が盛り上がり、肉芽(にくげ)と呼ばれる赤いブヨブヨした組織が形成されることもあります。ひどい場合には、歩行が困難になるほどの激しい痛みを伴うこともあります。
巻き爪は、どの年齢層にも起こりうる病気ですが、特に10代から20代の若年層に多く見られます。これは、成長期における骨格の変化や、運動量の増加、足の蒸れなどが関係していると考えられています。また、ハイヒールや先の細い靴を履く機会が多い女性にも多く見られます。
一方、高齢者にも巻き爪はよく見られます。加齢とともに爪が厚く硬くなり、変形しやすくなることや、視力低下や関節の可動域の制限により、適切な爪のケアが難しくなることが原因として挙げられます。
また、糖尿病や循環器系の疾患を持つ高齢者は、巻き爪が悪化しやすく、感染症などの合併症を引き起こすリスクも高いため注意が必要です。乳幼児や小さな子供にも、先天的な爪の異常や、足に合わない靴を履くことなどが原因で巻き爪が生じることがあります。
このように、巻き爪は年齢によって症状の現れ方や原因が異なることがあります。ご自身の年齢や生活習慣を考慮しながら、症状を観察することが大切です。
なぜ巻き爪になるのか?
巻き爪の原因は一つではなく、様々な要因が複雑に絡み合って起こります。最も一般的な原因の一つが、不適切な爪の切り方です。深爪をしたり、爪の角を丸く切ったりすると、爪が伸びる際に皮膚に食い込みやすくなります。また、足に合わない靴を履くことも大きな原因となります。特に、つま先が細く締め付けられるような靴や、ヒールの高い靴は、足の指に過度な圧力をかけ、爪が皮膚に食い込むのを助長します。足の指に外的な力が加わることも、巻き爪の原因となります。例えば、スポーツなどで足の指を強くぶつけたり、重い物を落としたりするなどの外傷は、爪の成長方向を歪め、巻き爪を引き起こすことがあります。体質や遺伝も巻き爪の発症に関わっていると考えられています。爪の形が生まれつき内側に湾曲していたり、「pincer nail(ピンサーネイル)」と呼ばれる、爪の先端が鉗子のように強く内側に巻き込む形状の爪を持つ人は、巻き爪になりやすい傾向があります。
足の裏や指が汗で蒸れやすい人も、巻き爪になりやすいことがあります。汗によって皮膚が柔らかくなり、爪が食い込みやすくなるためです。爪白癬(爪の水虫)などの爪の病気も、爪の肥厚や変形を引き起こし、巻き爪のリスクを高めます。
また、肥満や糖尿病、末梢血管障害などの病気も、足の血行不良やむくみを引き起こし、巻き爪のリスクを高めることが知られています。
日本の歴史を振り返ると、江戸時代以前は、わらじや草履など、足を締め付けない履物が主流だったため、巻き爪は少なかったと考えられています。明治時代以降、靴を履く生活が普及するにつれて、巻き爪が増加したと言われています。
巻き爪は、このように様々な要因が重なって発症する疾患です。ご自身の生活習慣や体質を振り返り、原因となりうる要素を避けることが、予防につながります。
疫学
日本における巻き爪の正確な罹患率は明らかになっていませんが、いくつかの調査からその状況を推測することができます。ある調査では、日本人の約19%が巻き爪で悩んでいると報告されています。また、別のインターネット調査では、18歳以上の男女の約29%が、足の親指に軽度以上の湾曲があると回答しています。2018年の報告では、陥入爪は男女ともに若年者に多く、巻き爪は中高年齢の女性に多いとされています。一般的に、巻き爪は10人に1人が罹患するとも言われています。
世界的に見ると、巻き爪は10代から30代の若年成人に最も多く見られ、一般人口における有病率は2.5%から5%と報告されています。しかし、ある研究では、21歳のネイル疾患患者の約40%が巻き爪であったと報告されており、また別の研究では、平均年齢54歳の足病治療を受けている患者の15.7%が巻き爪であったと報告されています。これらのデータは、巻き爪の有病率が年齢や調査対象によって大きく異なる可能性があることを示唆しています。近年、巻き爪の発生率と有病率は増加傾向にあるとも報告されています。
性別による差については、いくつかの研究で男性に多いとする報告がある一方で、女性に多いとする報告や、性差がないとする報告もあり、一定の見解は得られていません。ただし、中高年の女性に巻き爪が多いという日本の報告もあります。韓国で行われた大規模な調査では、巻き爪の発生率と有病率は女性で増加傾向にあり、10代と50代でピークが見られました。
このように、巻き爪は決してまれな病気ではなく、多くの人が悩んでいる一般的な疾患です。日本においても、潜在的な患者数は相当数に上ると考えられます。
なぜ皮膚科なのか?― 他の診療科との違い ―
皮膚科は皮膚とその付属器官である爪の健康を専門とする診療科であり、巻き爪の診断と治療において独自の専門知識を持っています。特に、重症化したり感染を伴ったりする巻き爪に対して、皮膚科医は適切な治療を提供することができます。例えば病院の救急外来などで初期対応を行うことはありますが、皮膚科医は爪の病気の専門家として、より深い知識と経験に基づいた診療を行うことができます。
皮膚科医は、巻き爪だけでなく、爪に生じる様々な病気を診断し治療することができます。例えば、巻き爪の原因や合併症としてよく見られるのが、爪白癬(爪の水虫)です。爪白癬は、爪が厚くなったり変形したりするため、巻き爪を悪化させる可能性があります。皮膚科医は、爪白癬の診断と適切な抗真菌薬による治療を行うことができます。また、爪の周囲の皮膚が細菌や真菌に感染する爪囲炎(ひょう疽)も、巻き爪に併発することがあります。皮膚科医は、感染症の原因菌を特定し、抗菌薬や抗真菌薬を用いた適切な治療を行います。
さらに、まれではありますが、爪の変形や痛みが、爪の腫瘍(良性・悪性)や、皮膚の病気である爪乾癬などによって引き起こされている可能性も考慮する必要があります。皮膚科医は、これらの疾患との鑑別診断を行い、必要に応じて適切な検査や専門的な治療を提供することができます。特に、爪の下に黒い線が現れるなどの症状がある場合は、悪性黒色腫(メラノーマ)の可能性も否定できません。皮膚科医は、ダーモスコピーなどの特殊な機器を用いて爪の状態を詳しく観察し、必要に応じて生検を行うことで正確な診断を行います。このように、巻き爪は単なる爪のトラブルとして捉えられがちですが、その背景には様々な皮膚や爪の病気が隠れている可能性があります。皮膚科医は、これらの病気との関連性を考慮しながら、患者さん一人ひとりの状態に合わせた最適な治療法を選択し、提供することができるのです。
当院(けんおう皮フ科クリニック)の特徴
― 当院でしかできない治療アプローチ ―
けんおう皮フ科クリニックは、地域の皆様の健康を第一に考えた地域密着型の医療を提供しています。保険診療を中心に、小さなお子様からご高齢の方まで、幅広い年齢層の患者さんの皮膚に関するお悩みに対応しております。また、美容皮膚科とも連携し、皮膚の健康と美しさをトータル面からサポートしています。当院では、患者さんの症状を正確に診断するために、丁寧な問診と詳細な視診を心がけており、その診断に基づいた適切な治療法をご提案しています。
巻き爪の治療においては、患者さんの症状の程度やライフスタイルに合わせて、様々な治療法をご用意しています。保存的治療から外科的治療まで、幅広い選択肢の中から最適なものをご提案できるのが当院の強みです。保存的治療であれば、コットン法(爪が食い込んでいる部分にコットンを詰め込む方法)、外科的治療であれば側爪郭楔状切除術(麻酔の注射を打った後に斜めに爪を切る方法)、フェノール法などで治療することが可能です。炭酸ガスレーザーで肉芽組織を焼灼することもあります。
このように、けんおう皮フ科クリニックでは、豊富な経験と最新の医療機器を駆使し、患者さん一人ひとりに合わせた最適な巻き爪治療を提供しています。他院では行っていないような新しい治療アプローチも積極的に取り入れており、患者さんの足の健康をサポートできるよう努めてまいります。
治療法
巻き爪の治療法は、症状の程度や患者さんの状態によって異なります。大きく分けて、保存的治療と外科的治療があります。
保存的治療
温水に浸す
患部を1日に数回、10〜20分程度、ぬるま湯に浸すことで、爪と皮膚を柔らかくし、炎症を和らげることができます。石鹸などを加え
ることも有効です。
コットンパッキング
爪が皮膚に食い込んでいる部分を、綿球などを使って優しく持ち上げ、爪と皮膚の間に挟むことで、爪が皮膚に直接当たるのを防ぎます。
テーピング
患部の皮膚をテープで引っ張り、爪が食い込んでいる部分から離すことで、圧力を軽減し、痛みを和らげます。
ガター法
爪が深く食い込んでいる場合に、細く切ったビニールチューブを爪の端に挿入し、爪と皮膚の間を分離する方法です。痛みを軽減し、爪が正常に伸びるのを助けます。
市販薬
痛みが強い場合には、鎮痛剤(アセトアミノフェンやロキソプロフェンなど)を服用することで、症状を和らげることができます。感染の兆候がある場合は抗生剤を内服することもあります。
外科的治療
保存的治療で改善が見られない場合や、症状が重い場合には、外科的治療が検討されます。
部分抜爪
爪が食い込んでいる部分のみを、局所麻酔下で切除する方法です。
フェノール法
部分抜爪後に、爪が生えてくる組織(爪母)をフェノールという薬剤で焼灼する方法です。これにより、問題のある部分の爪が再発するのを防ぐことができます。
鬼塚法
陥入爪の原因となっている肥厚した側爪郭を切除する方法です。
完全抜爪
爪全体を局所麻酔下で完全に除去する方法です。重度の巻き爪や、爪の変形が著しい場合に行われることがあります。
炭酸ガスレーザー治療
炭酸ガスレーザーを用いて、爪が食い込んでいる周囲の軟部組織を蒸散させる治療法です。爪母を損傷させずに治療できる可能性があり、痛みが少なく、回復が早いと報告されています。
ガイドラインに載っていない最新の情報
近年注目されているのが、炭酸ガスレーザーを用いた巻き爪の治療法です。特に、爪母を切除せずに、爪の周囲の軟部組織のみをレーザーで焼灼することで、爪の機能と外観を維持しつつ、高い治療効果と低い再発率が期待できるという研究結果が報告されています。この治療法は、従来の外科手術と比較して、患者さんの負担が少なく、早期の日常生活への復帰が可能になる可能性があります。
よくある質問(FAQ)
-
- 巻き爪は自然に治りますか?
-
軽度の巻き爪であれば、適切なセルフケアで改善することもありますが、多くの場合、放置すると悪化する可能性があります。
-
- 市販薬で治せますか?
-
市販の塗り薬や痛み止めは、症状を一時的に和らげることはできますが、根本的な治療にはなりません。
-
- すぐに病院を受診すべきですか?
-
痛みが強い場合、化膿している場合、炎症が広がっている場合。持病に糖尿病や血行不良がある場合は、すぐに医療機関を受診してください。
-
- 放置するとどうなりますか?
-
感染が広がり、蜂窩織炎や骨髄炎などの重篤な合併症を引き起こす可能性があります。特に、糖尿病や血行不良のある方は注意が必要です。
-
- 治療は痛いですか?
-
保存的治療はほとんど痛みを伴いません。外科的治療の場合は、局所麻酔の痛みはありますが、手術中の痛みはほとんどありません。炭酸ガスレーザー治療も、痛みが少ないと報告されています。
-
- 再発しますか?
-
巻き爪は再発しやすい病気ですが、適切な治療と日頃のケアを行うことで、再発のリスクを減らすことができます。フェノール法や炭酸ガスレーザー治療は、再発率が低いとされています。
-
- 治療期間はどのくらいですか?
-
症状の程度や治療法によって異なります。保存的治療で数週間程度、外科的治療の場合は、爪が生え変わるまでに数ヶ月かかることもあります。炭酸ガスレーザー治療は、比較的短い期間で改善が見られることが多いです。
まとめ
巻き爪は、多くの方が経験する可能性のある一般的な爪のトラブルですが、放置すると痛みが悪化したり、感染症を引き起こしたりする可能性があります。けんおう皮膚科クリニックでは、患者さん一人ひとりの症状や状態に合わせた丁寧な診断と、最新の治療法を含む様々な治療オプションをご用意しております。特に、炭酸ガスレーザーを用いた新しい治療法は、従来の治療法と比較して、痛みが少なく、回復が早く、再発のリスクも低いと期待されています。地域の皆様の足の健康をサポートするため、お子様からご高齢の方まで、安心してご相談いただけるクリニックを目指しております。巻き爪の症状でお悩みの方や、ご自身の爪の状態が気になる方は、ぜひ一度、当院までお気軽にご相談ください。
よく似た症状の別の病気(鑑別疾患)
巻き爪とよく似た症状を示す病気には、以下のようなものがあります。
・爪下外骨腫
・爪床腫瘍(良性・悪性)
・爪囲炎(ひょう疽)
・爪白癬(爪の水虫)
・陥入爪(巻き爪と区別されないこともありますが、爪の棘が皮膚に刺さっている状態を指すことが多いです)
・彎曲爪(爪全体が強く湾曲している状態)
・爪甲鉤彎症(爪が厚く硬くなり、湾曲して伸びる状態)
・爪の変形(外傷や他の病気によるもの)
・爪下血腫(爪の下に血が溜まった状態)
・爪甲剥離症
・化膿性肉芽腫
・爪黒色線条(特に急に現れた場合や変化がある場合は注意が必要です)
・爪乾癬
・足の指の皮膚炎
・異物刺入
これらの病気も、巻き爪と同様に、足の指の痛みや腫れ、炎症などを引き起こすことがあります。自己判断せずに、症状がある場合は皮膚科を受診し、正確な診断を受けることが大切です。