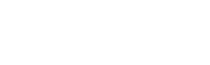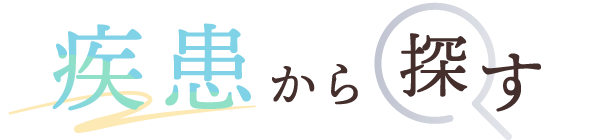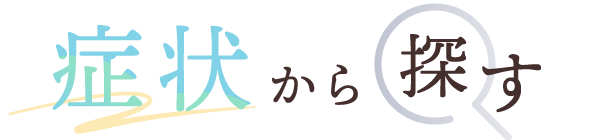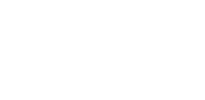- HOME
- 疥癬
疥癬とは
古代ギリシャの哲学者アリストテレスは「小さなブツブツをつぶすとシラミのような虫が出てくる」と記録しています。これは疥癬(かいせん)という皮膚の病気のことだと考えられています。実際、17世紀になってイタリア人医師ボノーモが疥癬の患者の皮膚から虫を発見し、疥癬がダニによる感染症であることを突き止めました。こうして疥癬は人類で初めて原因が解明された皮膚病の一つとなったのです。
疥癬は、ヒゼンダニという肉眼ではほとんど見えないダニが人間の皮膚に寄生することで起こる病気です。ダニは皮膚の一番表面にある角質層にトンネルを掘ってすみつき、卵を産みながら増殖します。体長は約0.3mmほどで白っぽい半透明の虫です。疥癬に感染すると激しいかゆみが生じ、赤いブツブツとした発疹が現れます。人から人へ接触でうつる伝染性の皮膚病であり、家族内や介護施設で集団感染することもあります。疥癬には大きく分けて2種類あり、寄生するダニの数が少なく主にかゆみが強い「通常疥癬」と、ダニが数百万匹と爆発的に増殖して皮膚が厚いカサブタにおおわれる「角化型疥癬(別名:ノルウェー疥癬)」があります。角化型疥癬は免疫力の低下した高齢者などに生じやすく、感染力が非常に強い点が特徴です。
日本では衛生環境の改善に伴い一時期疥癬は減少しましたが、近年は再び高齢者施設や病院での集団発生が問題になっています。新潟県三条市のような地域でも例外ではなく、高齢化や介護の現場で疥癬が見つかることがあります。「昔の病気」と思われがちですが、疥癬は現在でも誰でもうつる可能性がある皮膚病なのです。早期発見・早期治療すればきちんと治せる病気ですので、「もしかして?」と思ったら恥ずかしがらずに専門医を受診しましょう。
なぜ皮膚科なのか?
疥癬は一見すると湿疹(皮膚炎)やじんましんなど他の皮膚病と区別がつきにくいことがあります。実際、疥癬に感染していても最初はかゆみだけでブツブツが目立たないため、皮膚科医でも見落としてしまうケースがしばしばあります。例えば内科や小児科で「ただのかぶれでしょう」とステロイド入りの塗り薬を処方され、一時的に症状が治まったものの実は疥癬が治っておらず、その間に家族にうつってしまった…ということも起こりえます。疥癬の治療は皮膚科専門医で行うことが大切です。
皮膚科では、診察の際に皮膚の状態を詳しく観察し、必要に応じてダーモスコピー(拡大鏡)や顕微鏡検査を行ってダニや卵・フンを確認します。疥癬虫は非常に小さいため肉眼では見えませんが、皮膚科医は疥癬特有の皮膚症状(後述のトンネルなど)を手がかりにダニを探し出します。顕微鏡で虫体を発見できれば診断は確定し、すぐに適切な治療に入れます。
他科で処方されがちなステロイド軟膏は、炎症を抑えてかゆみを軽くする効果があります。しかし疥癬に対してステロイドを漫然と使うと、かゆみだけが治まってダニの増殖に気づかなくなるおそれがあります。最悪の場合、疥癬を見逃したままステロイドを長期間塗り続けた結果、通常疥癬がダニだらけの角化型疥癬に進行してしまうこともあります。こうした誤った治療を避けるためにも、「原因不明のかゆみが続く」「家族も同じような発疹がある」「治療しても湿疹が良くならない」場合は早めに皮膚科を受診しましょう。
当院の特徴
当院では疥癬の診療において迅速かつ的確な診断と、患者様に寄り添った丁寧な治療説明を心がけています。当院で疥癬の治療を受けるメリットをご紹介します。
的確な診断力
豊富な皮膚科臨床の経験から、疥癬を他の皮膚病と見分ける高い診断能力があります。指の間の小さな発疹も見逃さず観察し、その場で皮膚を少し削って顕微鏡検査を行い、ダニや卵を素早く確認します(痛みはほとんどありません)。初診当日に診断確定まで行えるため、無駄な通院や誤治療を減らせます。
院長自らダニを“生け捕り”
院長は大の虫好きです。過去には患者様の皮膚から運良く生きたヒゼンダニを採取できたこともあるほどで、院長いわく「虫の動きを見ると燃える!」とのこと。そんな虫への探究心も相まって、疥癬の診断には自信があります。
ご家族・施設への対応アドバイス
疥癬は本人だけでなく周囲のケアも重要です。当院では患者様のご家族や介護施設での対策についても丁寧にアドバイスしています。同居のご家族への同時治療の呼びかけや、寝具の洗濯方法、施設内での感染拡大防止策など、生活面での不安も一緒に解消できるようサポートいたします。
最新ガイドラインに基づく治療
疥癬治療薬の内服薬・外用薬について、国内外の最新の知見を踏まえた治療を行います。効果の高い治療法を優先しつつ、妊娠中や乳幼児など患者様個々の事情に合わせて安全な治療プランを選択します。必要に応じて内服と外用の併用療法や、重症例では大学病院との連携も含めた最善策を提案いたします。
プライバシーと配慮
疥癬というとデリケートな印象を持たれるかもしれませんが、当院では診療のプライバシーに十分配慮しています。受付から会計までスタッフ一同が患者様の立場に立ち、安心して治療に専念できる環境を整えています。「自分が疥癬かも」と不安に思ったら、どうぞお気軽に当院にご相談ください。
具体的な症状と年齢別の特徴
疥癬の主な症状は激しいかゆみとそれに伴う皮疹(発疹)です。かゆみは特に夜間に強くなるのが特徴で、寝ている間に無意識に掻きむしってしまうほどです。これはヒゼンダニが皮膚の中で産卵したりフンをしたりすることに対するアレルギー反応によるかゆみだと考えられています。
皮疹としては、まず赤いブツブツ(丘疹)が体のあちこちに現れます。大きさは小指の頭くらいで、蚊に刺された跡に似たものから湿疹状のものまで様々です。典型的には指と指の間、手首、ひじ、わきの下、乳房まわり(女性)、おへそのまわり、腰まわり、陰部や臀部など肌と肌が触れ合いやすい箇所に出やすいです。男性では陰嚢(いんのう)や陰茎に赤いしこり(疥癬結節)ができることがあります。これも疥癬特有の症状で、掻いてもなかなか消えない硬めのブツブツです。また、指の股や手首、陰部の皮膚を見ると、細い線状の跡が見えることがあります。まるで小さなトンネルのように見えるこの線は、ヒゼンダニのメスが皮膚の中に掘り進んだ「疥癬トンネル」と呼ばれるものです。長さは数ミリ~1cm程度のことが多く、灰白色~肌色のうねうねとした線として観察できます。ただし非常に細かいため、専門家でないと見つけることは難しいです。
これらの皮疹は激しいかゆみのために引っ掻いてしまい、掻き壊し(掻破痕)や出血痕が多数みられることもあります。掻いた傷から細菌が感染するととびひ(伝染性膿痂疹)を併発して化膿し、黄色いカサブタが付くこともあります。患者さんは夜も眠れないほどのかゆみに悩まされ、日常生活に大きな支障を来す場合があります。
年齢によって疥癬の症状や出やすい部位に少し違いがあります。乳幼児(赤ちゃん)や小さいお子さんの場合、大人と比べて皮膚が柔らかく薄いためか、疥癬トンネルが見つけにくい傾向があります。その代わり、水ぶくれ(小さな水疱)が手のひらや足の裏にできたり、おむつで覆われる股や臀部にジクジクした湿疹が出ることがあります。また、生後間もない赤ちゃんでは疥癬そのものが非常に稀ですが、もし感染すると全身(顔や頭皮も含む)に激しい湿疹が出て不機嫌になり、ミルクの飲みが悪くなることがあります。小児~青年期では、保育園や学校、スポーツの合宿、学生寮や社宅生活など集団生活の場で感染するケースがあります。この年代では家族内感染か、あるいはごく親しい友人・恋人同士のスキンシップや性交渉でうつることが多く、発疹も手指や手首、腹部や陰部など典型的な部位に現れることがほとんどです。
高齢者の場合, 疥癬にかかってもかゆみの自覚が意外と強くないことがあります。加齢に伴い皮膚の感覚が鈍くなったり、もともと糖尿病などで神経障害があると、疥癬によるかゆみに気づきにくいのです。このため発疹が広範囲にあっても「少し肌が乾燥してかゆいくらい」と思い込んでしまい、治療が遅れてしまうケースがあります。また高齢者では指の股よりも背中やお尻、太ももなど広い範囲に掻き傷が目立つことがあります。通常、疥癬の皮疹は首から上(顔や頭皮)には出ませんが、乳幼児や高齢者、免疫力の落ちた方では例外的に頭部や首に症状が及ぶことがあります。特に重症の角化型疥癬になると、顔や頭を含む全身の皮膚が赤く厚い角質におおわれ、爪も白く濁ってボロボロになります。角化型ではかゆみを感じない場合もあり、周囲に感染を広げて初めて発見されることもあります。
まとめると、疥癬は夜間の強いかゆみと体の各所にできる小さな赤いブツブツが主症状です。指の間のトンネルや陰部のしこりなど特徴的な皮疹がヒントになりますが、素人目には他の湿疹と区別が難しいことも多いです。乳幼児からお年寄りまで幅広い年代で発症しうるので、「自分は歳だからただの乾燥だろう」「子供だから虫刺されだろう」と自己判断せず、気になる症状があれば皮膚科で診てもらうことが大切です。
なぜ疥癬になるのか?
疥癬の直接の原因はヒゼンダニの寄生ですが、ではヒゼンダニはどこから来るのでしょうか。答えは「疥癬にかかっている人」からうつります。疥癬は人から人へ移る感染症であり、感染経路のほとんどは皮膚と皮膚の直接的な接触です。具体的には、患者さんと長時間一緒のベッドで寝たり(添い寝)、抱っこ・介護したり、性交渉を持ったりすると、その間にダニが肌をはい登って相手に移ります。また患者さんが使った衣類やタオル、寝具などを共有することでうつることもあります。特に角化型疥癬のようにダニの数が非常に多い患者さんでは、短時間の接触や寝具・衣服を介した間接的な接触でも感染する場合があります。
とはいえ、スキンシップ程度の一瞬の触れ合いで即座にうつる心配はあまりありません。ヒゼンダニは人の皮膚から離れると乾燥に弱く、数時間~2日ほどで生きられなくなるため、ある程度しっかりと密着した接触がないと感染しにくいのです。例えば患者さんとすれ違いざまに手が触れた程度であればまず大丈夫です。しかし逆に言えば、一緒に暮らして布団を並べて寝ている家族や、濃厚な接触のある相手には高い確率でうつってしまいます。疥癬は誰でも感染しうるものなので、「自分は清潔にしているから大丈夫」ということはなく、家族や集団生活で患者さんが出た場合には注意が必要です。
なお、ペットの犬や猫のノミ・ダニとは直接関係ありません。犬や猫にもヒゼンダニに似たダニが寄生して「疥癬(疥癬症)」になることがありますが、これら動物のダニは人に寄生する種類とは別種です。動物のヒゼンダニが人間に付着しても一時的にかゆみが出る程度で、人の体では繁殖できず自然に消えてしまいます。ですから「ペットから疥癬をもらったのでは?」と心配する必要はあまりありません(むしろペットに人間の疥癬がうつることはあります)。布団や絨毯にいるチリダニ(コナヒョウヒダニなどのハウスダスト中のダニ)とも疥癬は無関係です。チリダニは人の肌を刺したりはしませんので、寝具にダニ対策用スプレーをしても疥癬予防にはならないのです。
疥癬に感染しやすいのは、やはり家族間や集団生活の場です。特に高齢者施設や病院、介護の現場では免疫力の低いお年寄りに角化型疥癬が発生し、気づかないうちに周囲へ広がってしまうケースがあります。新潟県のように冬場に家族みんなでこたつに入ったり布団で暖をとったりする習慣がある地域では、その密着度の高さゆえに疥癬が広がりやすい側面もあるかもしれません。実際に当院でも、同じお布団で寝ていたご夫婦が次々に発症したり、介護していた家族にうつってしまったりといった例を経験しています。
もう一つ知っておいていただきたいのは、疥癬は感染してもすぐ症状が出るとは限らないということです。初めて疥癬にかかった場合、皮膚にダニが住み着いてから数週間(平均4~6週間)は自覚症状が出ないことがあります。この間に少しずつダニが増殖し、ある程度数が増えてから急にかゆみが出始めます。そのため、最初の患者さんは「いつ誰からうつったのか思い当たらない」ことが多いです。また症状が出る前から他の人に感染させてしまう可能性もあります。一方、以前に疥癬にかかったことがあって再感染した場合は、ダニに対するアレルギー反応ができているため数日~1週間程度で比較的早くかゆみが出現します。症の出方には個人差がありますが、「最近身近で疥癬と診断された人がいる」「集団生活先で疥癬が流行している」という場合には、症状がなくても皮膚科でチェックを受けると安心です。
治療法
疥癬は適切な治療によって完全に治すことができる病気です。治療の中心はヒゼンダニを駆除する駆虫薬(殺虫薬)の塗り薬や飲み薬です。症状の程度や患者さんの年齢・体調に応じて使い分けます。当院でも患者様一人ひとりに最適な治療薬を選択しています。
代表的な治療薬を以下に箇条書きでご紹介します。
ストロメクトール錠(イベルメクチン)
疥癬治療用の飲み薬です。体内からダニを殺す効果があり、通常体重に応じた量を1回、卵には効きにくいため、幼虫が孵化する約1週間後にもう一度内服します。現在、疥癬に対して保険適用となっている唯一の経口薬で、標準治療として第一選択となっています。
スミスリンローション5%(フェノトリン)
ピレスロイド系の殺虫成分フェノトリンを含む外用薬で、日本では疥癬治療に広く用いられています。首から下の全身にくまなく塗って一晩おき、翌朝洗い流すという方法で使用します。卵には効きにくいため1週間後にもう一度繰り返すことが推奨されます。フェノトリンは本来シラミ駆除シャンプー剤として開発された薬ですが、疥癬にも有効で保険適用となっています。
硫黄軟膏(いおう軟膏)
昔から使われてきた外用の殺虫薬です。硫黄(いおう)を10~30%程度含む軟膏を全身に塗ります。肌への刺激は少ないものの臭いが独特で、衣服や寝具を汚す欠点があります。妊婦さんや赤ちゃんでも使える安全な薬で、海外では今でも小児疥癬の第一選択肢になることがあります。日本でも保険適用のある外用薬として備蓄されています。
オイラックスクリーム(クロタミトン)
かゆみ止めとしておなじみの外用薬ですが、元々は動物の疥癬治療のために開発された経緯があり、人間の疥癬虫にもある程度の殺ダニ効果があります。1日2回、皮疹のある部位を中心に全身に塗ります。即効性は他の薬に劣りますが、皮膚の炎症を鎮める働きもあるため、軽症の通常疥癬に用いられることがあります(保険適用外ですが疥癬への使用が認められています)。
リンデン(γ-ベンゼンヘキサクロリド=γ-BHC製剤)
リンデンはかつて疥癬治療によく使われた塗り薬(ローション)です。有効成分γ-BHCは殺虫効果が高いものの、経皮吸収による神経毒性のリスクが指摘され現在ではほとんど使用されません。日本では市販されておらず、患者さん向けにはあまり目にしない薬です。※商品名リンダンなど。
安息香酸ベンジル外用(ベンジルベンゾエート)
海外で疥癬治療に用いられる塗り薬です。日本では市販されていませんが、欧州などでは25%安息香酸ベンジルを塗布する方法が一般的です。臭いと皮膚刺激が強いため近年は使われる機会が減っています。
(※日本で保険承認されている疥癬治療薬は硫黄軟膏とイベルメクチン内服薬のみですが、実臨床では上記のようなその他の薬剤も組み合わせて使用されています。海外では5%パーメトリンクリーム(日本未承認)が第一選択薬として広く使われています。)
治療薬は以上のようにいくつか種類がありますが、医師の指示通りに正しく使うことが重要です。 塗り薬は「かゆい所だけに塗れば良い」というものではなく、見た目に何も症状がなくても首から下の全身に塗布する必要があります。これはダニが移動して広範囲に潜んでいる可能性があるためです。また、決められた時間だけ塗ったままにしてから洗い流す、何日か空けてからもう一度全身に塗る、といった用法も守りましょう。飲み薬のイベルメクチンも、体重に合わせた適切な量を1回だけ服用します。「効き目を早く出したいから」と自己判断で多く飲んだりするのは危険です。
治療を開始すると、多くの場合は数日以内に新たな発疹が出なくなり、1〜2週間でかゆみも徐々に収まってきます。ただし、かゆみ自体はダニを駆除した後もしばらく(数週間ほど)残ることがある点に注意が必要です。治療開始から4週間以上経っても激しいかゆみが続いたり、新しいブツブツが増えてくるようなら、ダニが駆除しきれていない可能性があります。その場合は医師の判断で再度薬を使うことがあります。自己判断で治療を中断せず、完全に治ったと確認できるまで根気よく治療を続けましょう。
日常生活で気をつけるポイント
疥癬と診断されたら、治療と並行して生活上の注意も必要です。特に家庭内感染を防ぐため、以下のポイントに気をつけましょう。
家族も含め同時に治療を行う
疥癬は一緒に暮らす家族にうつりやすいため、症状が出ていない同居家族でも皮膚科を受診してもらい、必要ならば
全員で一斉に治療することが大切です。一人だけ治療しても、あとから別の家族から再感染してしまう可能性があります。
肌と肌の直接接触を避ける
治療が終わるまで、できるだけ他人との濃厚なスキンシップは控えてください。特に家族内では添い寝をしない、ハグや接触の多い遊びをしないようにしましょう。小さいお子さんが疥癬の場合、しばらくは別々の布団で寝る、抱っこのあとはしっかり手を洗うなど工夫してください。
タオルや衣類の共有禁止
患者さんが使ったタオル、寝巻き、下着類を他の人が共用しないようにします。また入浴時のバスマットも毎回交換し、家族で使い回さないようにしましょう。角化型疥癬の患者さんは可能なら個室にし、看護・介護する人は手袋やガウンを着用することが望ましいです。
寝具や衣類の洗濯
シーツや衣類はこまめに洗濯しましょう。ダニは50℃以上の熱に10分以上さらされると死滅するので、できれば熱めのお湯で洗濯すると効果的です。乾燥機に20~30分かけるのも有効です。布団や毛布は難しければ天日干しでも構いませんが、完全に駆除するにはクリーニングやスチームアイロンなど高温処理が望ましいです。
洗えないものは密封
カーペットやソファ、ぬいぐるみ等、洗濯や乾燥が難しいものは、大きなビニール袋に入れて密封し2~3日間放置します。ヒゼンダニは宿主の皮膚から離れても最長で2~3日しか生きられないため、その間隔離すれば自然に死滅します。念のため1週間程度密封しておくと確実です。
お部屋の掃除
床や畳、カーペットには剥がれ落ちた皮膚の角質片(フケ)が落ちており、その中にダニが潜んでいることがあります。日頃から掃除機をこまめにかけ、ダニの温床となるほこりや角質を除去しましょう。掃除機のあとは使い捨ての雑巾等で拭き掃除をするとより安心です。
爪を短く切る
かゆくて掻いてしまうと爪の間にダニや卵が入ることがあります。そこから自分の体の他の部分にダニが移動したり、他の人に接触した際にうつしてしまう可能性があります。爪は短く清潔に保ち、石鹸で手を丁寧に洗う習慣をつけましょう。掻き壊しによる二次感染(とびひ)予防のためにも有効です。
治療後も油断しない
薬の効果で新しい発疹が出なくなっても、すぐに普段の生活に完全に戻して良いかは主治医の指示に従ってください。通常、適切な治療開始から数日で感染力はほぼなくなるとされますが、念のため治療開始後1週間くらいは上記の対策を続けることをおすすめします。特に集団生活の場(学校や施設など)に早期に復帰する場合は、医師に相談のうえ決めましょう。
以上のような生活管理を行うことで、疥癬の再発予防と周囲への感染防止が可能です。「家の掃除が大変…」と思われるかもしれませんが、一度徹底して対策すればダニは駆逐できます。根気よく取り組んでください。
よくある質問(FAQ)
-
- 家族に疥癬がうつってしまいました。どうすればいいですか?
-
ご家族も含めて全員一緒に治療を受けることが大切です。
疥癬は直接肌が触れ合うことで家族間でも容易に感染します。症状の有無にかかわらず、同居のご家族は全員皮膚科で検査・治療を受けてください。同時に治療しないと、治った人にまた別の家族から再感染する恐れがあります。治療薬の内服や塗布のタイミングも家族で揃えるようにしましょう。
また、家庭内でのタオルや寝具の共用を避ける、掃除・洗濯を徹底するなど前述の日常生活の注意点も実行してください。
-
- 犬や猫から疥癬をもらうことはありますか?
-
通常、ペットから人への感染はほとんどありません。 犬や猫にも疥癬(ヒゼンダニ症)があり、人間とは異なるダニが寄生します。これら動物の疥癬虫が人の肌についた場合、一時的にブツブツ・かゆみが出ることがありますが、人間の皮膚では繁殖できないため自然に消滅します。
逆に人間の疥癬がペットにうつる可能性もゼロではありませんが、基本的にヒゼンダニは種ごとに適した宿主が決まっています。なお、ノミやマダニなどペットに付く他の寄生虫が人を刺してかゆみを起こすこと(いわゆる「虫刺され」)はありますが、これらは疥癬とは全く別物です。
疥癬は人から人への接触で広がるものと覚えておきましょう。
-
- きちんと治療すればどのくらいで治りますか?
-
適切な治療により、ほとんどの疥癬は1~2週間程度で治ります。飲み薬(イベルメクチン)は1回の服用で駆虫効果が期待でき、塗り薬も1週間おきに2回塗れば多くの場合ダニを駆除できます。早い方だと治療開始から数日でかゆみが和らぎます。
ただし、かゆみが完全になくなるまでにはダニが死んだ後も少し時間がかかることがあります。治療後もしばらくは皮膚に赤みやかゆみが残ることがありますが、これはダニの死骸や排泄物に対するアレルギー反応が続いているためです。通常、治療開始から2~4週間かけて徐々に治まっていきます。
逆に、治療後に新しい発疹が増えてきたりかゆみが悪化するようなら再度受診してください。
-
- 薬を塗ったのにまだかゆいです。治っていないのでしょうか?
-
治療後もしばらくかゆみが続くのは珍しくありません。 上述の通り、ダニ自体は駆除できていても皮膚のアレルギー反応がすぐには収まらないためです。
この「疥癬治癒後のかゆみ」には、医師がかゆみ止めの飲み薬(抗ヒスタミン剤など)やステロイド外用薬を追加で処方することがあります。それらを使って1~2週間ほど様子を見てもなお新しいブツブツが出るようであれば、ダニが生き残っている可能性があります。その際はもう一度同じ薬を使用する、あるいは別の薬剤に切り替えるなど追加治療が必要です。
自己判断で「効かなかった」とあきらめず、必ず医師に経過を伝えて相談してください。
-
- 清潔にしていれば疥癬にはなりませんか?汚い病気ですか?
-
疥癬は決して不潔な人だけがなる病気ではありません。実際、人種や清潔さに関わらず世界中どこでも発生します。
確かに戦後間もない衛生環境の悪い時代には「疥癬=貧乏人の病気」と言われたこともありました。しかし現代では、介護が必要な高齢者から元気な子供まで、誰でも感染の機会があれば疥癬になります。むしろ清潔好きな人ほど「まさか自分が疥癬なんて…」と発見が遅れる傾向があります。
大切なのは偏見を持たずに正しく対処することです。疥癬と分かったら入浴や洗濯で清潔を保ちつつ、前述のとおり適切な治療と環境整備を行えば必ず治ります。恥ずかしがる必要は全くありませんので、症状に心当たりがあれば早めに皮膚科を受診してください。
-
- 疥癬と診断されたら仕事や学校を休まないといけませんか?
-
基本的には治療開始までは休むことをおすすめします。 疥癬は接触によって他人にうつる可能性があるため、まだ治療を始めていない段階で多数の人と接触するのは避けるべきです。仕事や学校に疥癬患者がいると周囲も心配になりますから、きちんと治療してから復帰する方が安心でしょう。
一般的な疥癬の場合、適切な治療を開始してから約24~48時間経てば感染力はほぼ無くなるとされています。症状が落ち着いているなら、医師の判断にもよりますが治療翌日もしくは2日後あたりから職場や学校に戻ることが可能です。念のため患部をガーゼで覆う、長袖長ズボンを着用するなど配慮すると良いでしょう。集団生活の場では、他の人への周知や消毒対応も必要になる場合がありますので、医師の指示に従ってください。
まとめ
疥癬はかゆみが強く、一見すると驚いてしまう病名かもしれません。しかし正しい診断と治療によって完治が可能な病気です。戦後の混乱期には多くの人が悩まされた疥癬ですが、現在では治療薬も発達し、適切に対処すれば怖がる必要はありません。「湿疹がなかなか治らない」「夜になるとかゆみで眠れない」「同居家族も同じようなブツブツが出てきた」という場合は、ぜひ当院を受診してください。早期に発見できればその分周囲への感染拡大を防ぎ、短期間で治すことができます。当院は疥癬の診断・治療経験も豊富で、患者様の不安に寄り添いながら丁寧に対応いたします。
かゆみから解放され、安心して生活できるようになるまでしっかりサポートいたしますので、「もしかして疥癬かも?」と思ったら一人で悩まず当院にご相談ください。けんおう皮フ科クリニックのスタッフ一同、皆様の健康な皮膚と快適な暮らしを全力でお手伝いいたします。
よく似た症状の別の病気(鑑別疾患)
疥癬は他の皮膚病と間違われることがあります。以下に疥癬と症状が似ている主な疾患を挙げます(※専門的な病名も含みますが、参考として紹介します)。
・皮膚瘙痒症(ひふそうようしょう)
これといった発疹がないのに全身または身体の一部がかゆくなる状態です。内臓の病気やストレス、皮膚の乾燥など様々な原因で起こります。皮膚に目立つブツブツが無い点が疥癬との違いですが、高齢者で全身がかゆい場合は疥癬と紛らわしいことがあります。疥癬が治癒した後にかゆみが長引くこともあります。
・虫刺症(ちゅうししょう)
いわゆる虫刺されです。蚊やノミ、ダニ、ブヨなどに刺されて赤く腫れ、かゆみが出ます。虫に刺された直後にかゆくなる「即時型反応」と、1~2日遅れてから腫れる「遅延型反応」があり、体質によって症状の強さは様々です。疥癬との違いは、多くの場合刺された箇所が限定的であること、家族間で一緒に発生しにくいことなどです。
・アトピー性皮膚炎
乳幼児期に発症することが多い体質性の湿疹です。慢性的に肌がカサカサし、痒みを伴う赤い湿疹が出ます。特に肘や膝の内側、首周りなどに左右対称に症状が現れる点が特徴です。疥癬と異なり、人にうつる病気ではありません。
・接触皮膚炎(かぶれ)
特定の物質が皮膚に触れることで起こるアレルギー性の湿疹です。原因となった物(植物のかぶれ液、金属、洗剤など)が接触した部位に一致して赤いブツブツや水ぶくれが生じます。疥癬では接触部位に限らず全身に発疹が広がるのに対し、かぶれは原因物質が当たった部分だけに症状が出る点で区別できます。
・蕁麻疹(じんましん)
ミミズ腫れのような膨疹(紅斑)が突然出現し、強いかゆみを伴う疾患です。虫刺されと見分けがつきにくい場合もありますが、疥癬との違いはブツブツというより地図状に広がる一過性の腫れであること、普通は長期間持続しない(24時間以内に消える)ことです。蕁麻疹体質の方でも、疥癬にかかれば蕁麻疹用の治療では治りません。
・ノミ刺症
ノミに噛まれたことによる皮膚炎です。蚤は主に脚や足首など衣服で覆われていない部分を集中的に刺す傾向があります。複数箇所に赤い点状の発疹が列をなすように現れ、激しいかゆみがあります。家にペットがいる場合や、野良猫の寝床が近くにある場合などに起こりやすいです。疥癬との鑑別点は、人から人へは感染しないことと、刺し口の中心に小さな点(出血点)が見られることです。
・シラミ症
シラミの寄生による皮膚症状です。髪の毛に寄生するアタマジラミ、陰部に寄生するケジラミ、衣類に潜むコロモジラミ(体シラミ)などがあります。いずれも人から人へ直接接触でうつりますが、シラミの場合は肉眼で虫や卵(白いフケのようなもの)が確認できる点で疥癬と異なります。かゆみの部位も、アタマジラミなら頭皮、ケジラミなら陰毛部と局所的です。
・乾皮症(かんぴしょう)
乾燥肌のことです。皮膚の表面がカサカサに乾き、粉をふいたり細かな皮むけ(落屑)が見られます。痒みを伴うこともありますが、乾皮症そのものを疥癬と間違えることは通常ありません。ただし高齢者では乾燥肌によるかゆみが強くなることがあり、掻き傷だらけの皮膚を見ると一見疥癬のように思える場合があります(実際にはダニ
がいない点で区別できます)。
・乾癬(かんせん)
読み方が「かいせん」と似ていますが乾癬は全く別の病気です。赤く盛り上がった皮疹の表面に銀白色のかさぶた(鱗屑)が厚く積もるのが特徴で、ひじ・ひざ・頭皮などに好発します。痒みは強くないことが多く、他人にうつる心配もありません。重症の乾癬では全身の皮膚が赤くなりますが、疥癬との違いは皮膚にいるダニの有無であり、顕
微鏡検査で判別可能です。
・水疱性類天疱瘡(すいほうせいるいてんぽうそう)
高齢者に多い自己免疫性の皮膚病で、強いかゆみを伴う湿疹や小さな水ぶくれが全身に出現します。疥癬に酷似するため誤診されることがありますが、類天疱瘡では経過とともに緊満性(水風船のようにピンと張った)大きな水疱が現れる点で区別できます(疥癬でも緊満性水疱ができることも稀ではありません、ややこしいですね)。こちらも感染症ではありません。
・ 爪白癬(つめはくせん)
白癬菌(はくせんきん)というカビが爪に感染する「爪水虫」です。爪が白~黄色く濁り厚く変形してきます。疥癬では稀にダニが爪の中にまで寄生する「爪疥癬」という病態がありますが非常に珍しいため、爪の濁りや肥厚は多くが爪白癬です。爪白癬と疥癬は全く別の病気ですが、高齢者で皮膚の厚いかさぶたや爪の濁りが見られる場合、角化型疥癬との鑑別として念頭に置かれます。
・結節性痒疹(けっせつせいようしん)
長期間にわたり強いかゆみが続くことで、皮膚にゴリゴリと硬い結節(しこり状の発疹)が多数生じた状態です。慢性的な湿疹や虫刺され、疥癬などを掻き続けることで起こる二次的な症状で、皮疹だけ見ると疥癬結節との区別が付きにくいことがあります。結節性痒疹自体は感染症ではなく、皮膚を掻かないようにしていけば徐々に改善します。
以上、疥癬と紛らわしい皮膚疾患を挙げました。実際の診療では、患者さんの症状や経過を詳しく伺い、必要な検査を行うことでこれら鑑別疾患と疥癬を区別します。「自分の症状は本当に疥癬なのだろうか?」と不安な場合も、皮膚科専医はこのような多数の可能性を検討したうえで診断を下しています。一人で調べて悩むより、ぜひ専門医に相談してスッキリ原因を突き止めましょう。