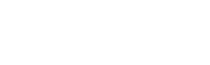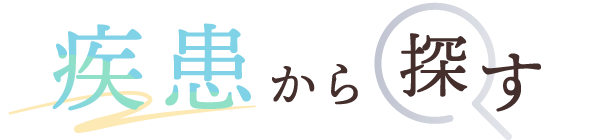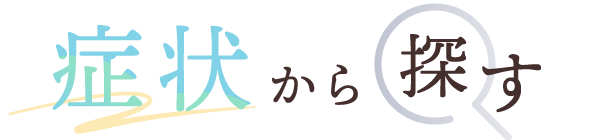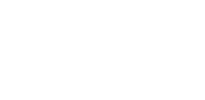- HOME
- 尋常性疣贅(いぼ)
いぼとは?
古来より、いぼは人々の悩みの種でした。古代エジプトでは蜂蜜が、古代ギリシャではニンニクがいぼの治療に用いられていた記録が残っており、その歴史は非常に長いことがわかります。中世ヨーロッパでは、いぼは悪霊や魔女の仕業と考えられ、生肉でいぼを擦って土に埋める、あるいは生きたヒキガエルで触るといった奇妙な治療法が信じられていました。日本においても、いぼ取りにご利益のある神様や仏様が各地に存在し、京都には800年の歴史を持ついぼ取り寺があり、皮膚科医も祈祷に訪れるそうです。また、ある地域に伝わる伝説では、いぼに悩む姉妹が馬頭観音に祈願し、像を擦り続けることでいぼが治ったとされています。このように、いぼに対する人々の関心と治療への試みは、時代や文化を超えて存在してきたのです。17世紀には、医師ゼンネルトゥスが「疣贅(いぼ)」を意味する「verruca」という言葉を作り、いぼを小さな丘の隆起に例えました。また、かつてはいぼの原因として、現代では考えられないような習慣が挙げられていたこともありました。
いぼは、医学的には疣贅(ゆうぜい)とも呼ばれ、ヒトパピローマウイルス(HPV)というウイルスが皮膚に感染することで生じる一般的な皮膚の病変です。世界人口の約10%が、特に学童期のお子さんでは10〜20%もの方がいぼに悩まされているというデータもあり、非常に一般的な皮膚疾患と言えるでしょう。いぼは体の様々な部位に発生する可能性があり、そのほとんどは良性ですが、中には性器いぼのように、特定のHPVの型が原因でがんのリスクを高めるものも存在します。また、水いぼと呼ばれる伝染性軟属腫は、HPVではなく、ポックスウイルス科のウイルスによって引き起こされ、特にお子さんに多く見られます。
いぼにはいくつかの種類があり、代表的なものとして以下の4つが挙げられます。
尋常性疣贅(じんじょうせいゆうぜい)
一般的に「いぼ」と呼ばれるもので、表面がザラザラとしたカリフラワーのような盛り上がりを示すことが多いです。手の指や手のひら、足の指、足の裏、膝などによく見られ、爪の周りにできることもあります。痛みは通常ありませんが、小さな黒い点(血栓化した毛細血管)が見られることがあります主な原因となるHPVの型は、2a型、4型、27型、57型などです。
扁平疣贅(へんぺいゆうぜい)
比較的小さく、平らな盛り上がりを示すいぼで、表面は滑らかか、わずかに角化していることが多いです。ピンク色、薄茶色、黄色っぽい色をしています。顔、手の甲、すねなどによくでき、時に多数(20〜100個程度)発生することがあります。引っ掻き傷などに沿って線状に広がることもあります。主な原因となるHPVの型は、3型、10型、28型、29型、41型、49型などです。
尖圭コンジローマ(せんけいコンジローマ)
性器や肛門の周りにできるいぼで、小さく硬い盛り上がりであったり、カリフラワーのような形状の集団を形成したりすることがあります。かゆみや灼熱感を伴うこともありますが、無症状のこともあります。約90%がHPVの6型と11型によって引き起こされます。
伝染性軟属腫(でんせんせいなんぞくしゅ)
一般的に「水いぼ」と呼ばれ、小さく、皮膚と同じ色かピンク色で、中央にくぼみのある丸い盛り上がりを示します。お子さんの顔、体、腕、脚によく見られ、大人では性器にできることもあります。原因はHPVではなく、伝染性軟属腫ウイルスというポックスウイルスです(本来は尋常性疣贅に分類されませんが、「いぼ」の仲間として便宜上コンテンツに含めました)。
これらのいぼは見た目が似ていることもありますが、原因となるウイルスや適切な治療法が異なります。ご自身で判断せずに、皮膚科を受診して正確な診断を受けることが非常に重要です。
なぜ皮膚科なのか?― 他の診療科との違い ―
いぼの診断と治療において、皮膚科専門医は他の診療科とは異なる専門的な知識と経験を持っています。皮膚科医は、いぼの種類を正確に診断し、適切な治療法を選択するために、皮膚の状態を詳細に観察する訓練を受けています。いぼに似た皮膚病変、例えば脂漏性角化症や軟性線維腫などは加齢に伴う良性の変化であることが多いですが、ウイルス性のいぼとの鑑別には皮膚科医の専門知識が不可欠です。特に、いぼと間違えやすい皮膚がんなどの悪性腫瘍との鑑別は、皮膚科医の重要な役割です。
適切な治療を受けることは、いぼの症状を改善するだけでなく、周囲への感染を防ぐためにも重要です。特に足の裏にできた尋常性疣贅は、歩行時に痛みを生じることがあり、日常生活に支障をきたすこともあります。また、性器にできた尖圭コンジローマは、性感染症であり、パートナーへの感染を防ぐために適切な治療が必要です。さらに、いぼは見た目の問題から精神的な苦痛を感じる方も少なくありません。
小児科や耳鼻咽喉科、内科など他の診療科でもいぼの治療が行われることがありますが、皮膚科専門医はより専門的な知識と豊富な治療オプションを持っています。例えば、皮膚科医はダーモスコピーという拡大鏡を用いていぼを詳細に観察し、診断の精度を高めることができます。
また、液体窒素療法、電気焼灼、レーザー治療、外用薬、内服薬、手術療法など、様々な治療法の中から患者さんの症状や希望に合わせた最適な治療法を選択することができます。皮膚科専門医は、幅広い知識と経験に基づき、患者さん一人ひとりに最適な医療を提供できるのです。
当院の特徴
豊富な臨床経験に基づいた正確な診断と、患者一人ひとりに合わせた丁寧な治療
当院では、長年の臨床経験に基づき、患者さんのいぼの状態を正確に診断し、それぞれの症状やライフスタイルに合わせたきめ細やかな治療をご提供いたします。
保険診療を中心とした経済的な負担の少ない治療の提供
当院では、液体窒素療法など、保険診療で可能な治療法を積極的にご提供し、患者さんの経済的な負担を軽減できるよう努めております。
CO2レーザー
炭酸ガスレーザーは、いぼの組織を正確に蒸散させることができ、特に顔などの目立つ部位のいぼや、液体窒素療法で効果が得られにくい場合に有効です。出血が少なく、比較的短時間で治療が可能です。
Vビーム
血管に反応するVビームレーザーは、いぼに栄養を送る血管を破壊することで、特にウイルス性のいぼの治療に用いられます。液体窒素療法で治りにくい場合や、指先など治療が難しい部位にも適しています。
局所免疫療法
難治性のいぼに対して行われる治療です。人為的にいぼに対する免疫反応を誘導する治療です。
具体的な症状と年齢別の特徴
いぼの種類
いぼの種類によって、現れる症状には特徴があります。
尋常性疣贅
手の指、足の裏、膝などによく見られる、表面が硬くザラザラした盛り上がりです。痛みは通常ありませんが、触ると硬く感じることがあります。
扁平疣贅
顔面や手の甲、すねなどにできやすい、平らで少し盛り上がった小さなブツブツです。色はピンク色や薄茶色をしています。かゆみを感じることもありますが、ほとんどの場合は無症状です。
尖圭コンジローマ
性器や肛門の周りにできるイボで、小さなブツブツが集まってカリフラワーのような形になることがあります。かゆみや出血を伴うこともありますが、気づかないうちに大きくなることもあります。
伝染性軟属腫
水いぼとも呼ばれ、主に子供の体にできる、光沢のある小さな丸いブツブツです。中央が少しへこんでいるのが特徴で、触ると柔らかいです。年齢によっていぼの現れ方や治療の注意点には違いがあります。
年齢別の特徴
年齢によっていぼの現れ方や治療の注意点には違いがあります。
小児
尋常性疣贅や伝染性軟属腫が非常に多く見られます。お子さんのいぼは自然に治ることもありますが、他の人にうつしてしまう可能性があるため、治療を検討することが多いです。治療の際には、痛みの少ない方法が優先されることがあります。
成人
尋常性疣贅や扁平疣贅に加え、性行為によって感染する尖圭コンジローマが見られます。また、加齢とともに脂漏性角化症といういぼに似た良性の皮膚腫瘍ができることもあります。大人のいぼは子供に比べて治りにくいことがあります。
高齢者
脂漏性角化症(老人性いぼ)が多く見られます。免疫力の低下により、いぼに対する体の反応が弱くなることもあります。
尋常性疣贅は小児に多く、日本の皮膚科外来患者の調査では、6〜10歳で23.01%、11〜15歳で17.18%の有病率が報告されています。伝染性軟属腫は、日本では年間約100万人が医療機関を受診し、その約9割が9歳以下の小児です。
なぜいぼになるのか?
いぼの主な原因は、ヒトパピローマウイルス(HPV)への感染です。HPVは、主に皮膚の小さな傷から侵入し、感染します。直接的な接触感染が主な経路ですが、温泉施設やプール、ジムなどの公共施設での間接的な接触によっても感染することがあります。また、いぼを自分で触ったり、掻いたりすることで、ウイルスが体の他の部位に広がることもあります(自家感染)。性器いぼ(尖圭コンジローマ)は、性行為による接触が主な感染経路です。伝染性軟属腫は、直接的な皮膚の接触や、ウイルスが付着したタオルや遊具などを介して感染します。
免疫力が低下している人は、HPVに感染しやすく、いぼができやすい傾向があります。アトピー性皮膚炎の方も、皮膚のバリア機能が弱いため、いぼに感染しやすいと言われています。健康な状態であれば、HPVに接触しても感染しないこともあります。体の免疫システムは、HPVの感染を抑えたり、自然に治したりする働きを持っています。
日常生活でいぼの感染を予防するためには、以下の点に注意しましょう。
- いぼに直接触れないようにする。
- 手洗いをこまめに行う。
- タオルやハンカチ、爪切りなどの個人的なものを共有しない。
- プールや温泉など、公共の場所では裸足で歩かない。
- いぼを掻いたり、むしったりしない。
- 皮膚の乾燥を防ぎ、小さな傷を保護する。
- 性行為の際にはコンドームを使用する(性器いぼの予防)。
- HPVワクチンを接種する(性器いぼの原因となるHPVの感染予防)。
治療法
いぼの治療法は、いぼの種類、大きさ、数、部位、患者さんの年齢や希望などによって選択されます。当院では、以下の様々な治療法をご用意しております。
液体窒素療法
液体窒素という非常に冷たい液体でいぼを凍らせて、皮膚組織を破壊する方法です。
メリット
比較的安価で、多くのいぼに有効です。性器いぼに対しても妊娠中でも比較的安全に行えます。
デメリット
治療時に痛みがあり、水ぶくれができることがあります。数回、数週間の間隔で治療を繰り返す必要があります。
治療期間
数週間から数ヶ月。
当院での適用
各種いぼに対して、第一選択として行うことが多い治療法です。
電気焼灼
電気メスを用いて、いぼを焼き切る方法です。
メリット
一度の治療でいぼを除去できることがあります。
デメリット
液体窒素療法よりも痛みがあり、局所麻酔が必要です。傷跡が残る可能性があります。
治療期間
処置自体は短時間ですが、治癒に2週間以上かかることがあります。
当院での適用
他の治療法で効果が得られない場合や、特定のいぼに対して検討します。
レーザー治療
レーザーを照射して、いぼの組織を破壊する方法です。
CO2レーザー
いぼの組織を蒸散させ、特に顔のいぼなどに適しています。
メリット
小さなものであれば、ほぼ1回で治療可能です。傷跡に残りにくい治療です。
デメリット
保険適用外となります。治療後に再発することもあります。目立ちませんが傷痕になることがあります。
治療期間
通常1〜2回の治療で済みますが、治癒に数週間かかることがあります。
当院での適用
顔のいぼや、他の治療法で効果が得られない場合に検討します。
Vビームレーザー
いぼに栄養を送る血管を破壊し、特にウイルス性のいぼに有効です。
メリット
液体窒素療法で治りにくいいぼにも効果が期待できます。
デメリット
保険適応外の治療です。複数回の治療が必要となることがあります。
治療期間
数週間間隔で複数回の治療が必要です。
当院での適用
難治性のいぼに対して検討します。
外用薬
塗り薬を用いていぼを治療する方法です。
イミキモドクリーム(ベセルナクリーム)
免疫を活性化させることで、性器いぼや扁平疣贅の治療に用いられます。
メリット
自宅で治療できます。
デメリット
治療に時間がかかり、皮膚炎などの副作用が出ることがあります。保険適応外です。
治療期間
数週間から数ヶ月。
当院での適用
主に性器いぼや扁平疣贅に対して処方します。
o 5-FU軟膏(フルオロウラシル軟膏)
抗がん剤の一種で、扁平疣贅などに用いられることがあります。
メリット
扁平疣贅に有効な場合があります。
デメリット
皮膚への刺激が強く、赤みやかぶれが出やすいです。保険適応外です。
治療期間
数週間から数ヶ月。
当院での適用
慎重に経過を観察しながら、特定のいぼに対して使用を検討します。
ブレオマイシン局所注射
抗がん剤の一種で、難治性の尋常性疣贅、爪周囲の尋常性疣贅などに用いられることがあります。
メリット
他のイボの治療に比して有効率が高いとされています(60~90%)。
デメリット
皮膚への刺激が強く、赤みやかぶれが出やすいです。疼痛や水疱形成、爪の場合は爪の変形や脱落などの副作用が起こることがあります。保険適応外です。
治療期間
1か月ごとに治癒するまで繰り返します。。
当院での適用
慎重に経過を観察しながら、特定のいぼに対して使用を検討します。当院では1回3300円で行っております(保険適応外)。
その他の外用薬
サリチル酸含有の塗り薬や、トレチノイン、カンタリジンなどがあります。
内服薬
飲み薬を用いていぼを治療する方法です。
ヨクイニン
ハトムギ由来の生薬で、免疫力を高め、いぼの治療に用いられることがあります。特に扁平疣贅に効果があると言われています。
メリット
比較的安全で、副作用が少ないです。
デメリット
効果が現れるまでに時間がかかることがあります。
治療期間
数ヶ月。
当院での適用
扁平疣贅を中心に、補助的な治療として用いることがあります。
シメチジン
免疫力を高める効果があり、難治性のいぼに対して用いられることがあります。
手術療法
メスなどを用いて、いぼを外科的に切除する方法です。
メリット
確実性の高い治療法です。
デメリット
傷跡が残る可能性があります。保険適応外になります。
治療期間
手術自体は短時間ですが、治癒に時間がかかります。
当院での適用
大きなものや、他の治療法で効果が得られない場合に検討します。保険適応外になります。
その他の治療法
カンタリジン
医療機関で塗布する外用薬で、水疱を形成し、いぼを除去します。特に伝染性軟属腫に対して2023年にFDAで承認されました。本邦でも2025年に承認されました(®ワイキャンス外用液0.71%)。
局所免疫療法
特殊な薬剤を用いて、いぼにアレルギー反応を起こさせ、免疫力でウイルスを排除する方法です。当院でも行えますが、保険適応外になります。
日常生活で気をつけるポイント
いぼの予防と悪化を防ぐために、日常生活では以下の点に注意しましょう。
- いぼを触らないようにしましょう。
- 手をよく洗いましょう。
- タオルや洗面用具などを共有しないようにしましょう。
- プールや公衆浴場など、人が多く集まる場所では注意しましょう。
- いぼを掻いたり、潰したりしないようにしましょう。
- 皮膚を清潔に保ち、乾燥を防ぎましょう。
- 免疫力を維持するために、バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動を心がけましょう。
よくある質問(FAQ)
-
- いぼは自然に治りますか?
-
小さなお子さんのいぼは、免疫力の向上とともに自然に治ることがあります。しかし、大人のいぼは治りにくいことが多いです。
-
- 市販薬で治せますか?
-
市販のいぼ治療薬もありますが、効果がない場合や悪化する可能性もあります。自己判断で使用せず、皮膚科医に相談することをおすすめします。
-
- すぐに病院を受診すべきですか?
-
いぼが急に大きくなった、数が増えた、痛みやかゆみが強い、出血がある場合は、早めに皮膚科を受診してください。
-
- 治療は痛いですか?
-
治療法によって痛みの程度は異なります。液体窒素療法や電気焼灼、レーザー治療は痛みを伴うことがあります。外用薬や内服薬は比較的痛みが少ない治療法です。
-
- 再発はしますか?
-
いぼは、治療後も再発することがあります。治療後も注意深く経過を観察し、再発した場合は再度治療が必要です。
-
- 尖圭コンジローマは性行為なしでも感染しますか?
-
稀に、性行為以外の接触(手指など)で感染することもありますが、主な感染経路は性行為です。
-
- 水いぼはプールでうつりますか?
-
プール自体が原因でうつることは少ないですが、皮膚と皮膚の接触や、タオル、ビート板などを介して感染することがあります。
-
- 扁平疣贅は治りにくいですか?
-
扁平疣贅は、他のいぼに比べて治療に時間がかかることがあります。
まとめ
いぼの適切な診断と治療には、皮膚科専門医の診察が不可欠です。
当院では、豊富な臨床経験に基づき、患者さん一人ひとりの症状に合わせた丁寧な診療を行っております。最新の医療機器であるCO2レーザー、Vビームレーザー、ジェントルマックスプロなどを駆使し、様々な種類のいぼに対して最適な治療をご提供いたします。また、保険診療を中心とした経済的な負担の少ない治療を心がけております。いぼでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
よく似た症状の別の病気
いぼと間違えやすい皮膚の病気には、以下のようなものがあります。
・水いぼ(伝染性軟属腫)
中央がくぼんだ、光沢のある小さなブツブツ。
・タコ
足の裏などにできる、皮膚が厚く硬くなったもの。
・魚の目
足の裏や指にできる、芯のある硬い盛り上がり。
・皮膚線維腫
皮膚にできる良性の硬い腫瘍。
・脂漏性角化症
加齢によってできる、茶色や黒色のイボ状の隆起。
・メラノーマ
皮膚のがんの一種で、いぼに似た形状を呈することがあります。
・軟性線維腫
首やわきの下などにできる、柔らかい小さなイボ状の突起。
・汗管腫
目の周りなどにできる、小さな白いブツブツ。
・脂腺増殖症
顔などにできる、小さな黄色っぽいブツブツ。
・伝染性膿痂疹
細菌感染による皮膚の病気で、水ぶくれや膿を持つブツブツができます。
・扁平苔癬
皮膚や粘膜にできる、平らで光沢のある紫色のブツブツ。
・毛包炎
ニキビのこと。
・稗粒腫
皮膚の浅い部分にできる、白い小さなできもの。
・毛嚢炎
毛穴の炎症によってできるブツブツ。
・ヘルペス
ウイルス感染による水ぶくれ。
・梅毒性コンジローマ
梅毒の症状の一つで、性器などにできる平たいイボ。
・ボーエン病、有棘細胞癌
皮膚がんの一種で、いぼに似た見た目をすることがあります。
・日光角化症
紫外線によってできる、ザラザラした赤い斑点。
・疣贅状表皮発育異常症
遺伝性の病気で、全身に多数のいぼのようなものができます。
これらの病気は、いぼと見た目が似ていることがありますが、原因や治療法が異なります。自己判断せずに、皮膚科を受診して正確な診断を受けることが大切です。