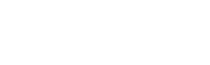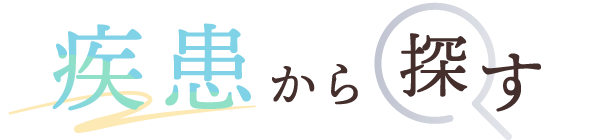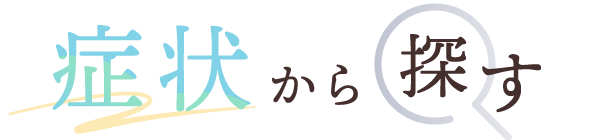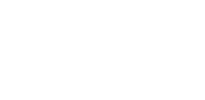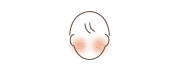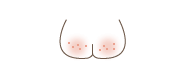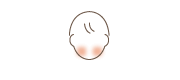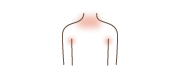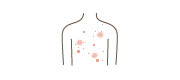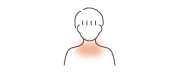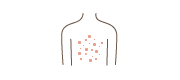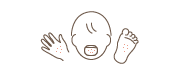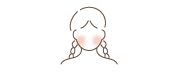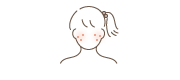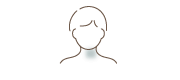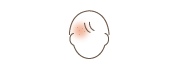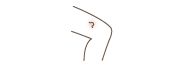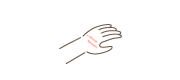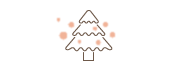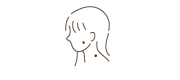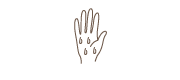- HOME
- 小児皮膚科
小児皮膚科とは
 新潟の豊かな自然に囲まれ、海や山で生き物たちと触れ合う中で、私はいつも、生物がいかに巧みに外界と関わり合っているかに感銘を受けます。私たちの体でその最前線に立つのが、全身を覆う最大の臓器「皮膚」です。お子様にとって、この世界との接点である皮膚は、特に繊細でダイナミックな存在です。
新潟の豊かな自然に囲まれ、海や山で生き物たちと触れ合う中で、私はいつも、生物がいかに巧みに外界と関わり合っているかに感銘を受けます。私たちの体でその最前線に立つのが、全身を覆う最大の臓器「皮膚」です。お子様にとって、この世界との接点である皮膚は、特に繊細でダイナミックな存在です。
皮膚の病気に関する記録は古くから存在しますが、子どもの皮膚だけを専門的に扱う「小児皮膚科」という分野が確立されたのは、実は比較的最近のことです。その夜明けを告げたのが、1827年に英国の外科医ウォルター・クーパー・デンディが出版した一冊の本、『小児期に付随する皮膚疾患に関する論文』でした。これは、子どもの皮膚疾患だけに焦点を当てた世界で初めての専門書であり、大人の皮膚のミニチュアではない、子ども特有の皮膚科学の始まりを象徴する出来事でした。その後、1972年に国際小児皮膚科学会が、1977年には日本小児皮膚科学会が設立され、現在では1,500名以上の会員が専門的な診療と研究にあたっています。
では、なぜ子どもの皮膚には特別な配慮が必要なのでしょうか。釣り好きの私は、よく魚のことを考えます。魚には私たち陸上動物が持つような硬い角層がありません。その代わり、彼らは「粘液」の層で体を守っています。この粘液は驚くべき物質で、物理的なバリアであると同時に、リゾチームや抗菌ペプチドといった免疫物質を豊富に含み、水中の無数の病原体から身を守る化学的な砦でもあるのです。お子様、特に赤ちゃんの皮膚もこれと似ています。皮膚のバリア機能は未熟で、外部からの刺激が侵入しやすく、水分も失われやすい。まるで、魚が粘液を失えば無防備になってしまうように、お子様の未熟な皮膚バリアは、丁寧なケアで守ってあげる必要があるのです。
小児皮膚科では、アトピー性皮膚炎やおむつかぶれといった日常的なトラブルから、あざ(血管奇形)や遺伝性の皮膚疾患まで、お子様の皮膚に起こるあらゆる問題に対応します。
なぜ皮膚科なのか?
 お子様の皮膚にトラブルが起きたとき、「小児科と皮膚科、どちらに行けば?」と迷われる保護者の方は少なくありません。もちろん、お子様の健康を総合的に診てくださる小児科の先生は、最初の窓口として素晴らしい存在です。しかし、こと「皮膚」に関しては、専門家である皮膚科医が持つ独自の強みがあります。
お子様の皮膚にトラブルが起きたとき、「小児科と皮膚科、どちらに行けば?」と迷われる保護者の方は少なくありません。もちろん、お子様の健康を総合的に診てくださる小児科の先生は、最初の窓口として素晴らしい存在です。しかし、こと「皮膚」に関しては、専門家である皮膚科医が持つ独自の強みがあります。
皮膚は心臓や肺と同じ、専門性を持った一つの「臓器」です。皮膚科医は、医師免許取得後、さらに5年以上にわたり専門の研修施設で皮膚科学だけを深く学び、皮膚の構造から病気のメカニズム、治療法までを熟知した「皮膚の専門家」です。
 当院のような皮膚科専門クリニックでは、診断の精度を高めるための特別な機器を備えています。その代表が「ダーモスコープ」です。これは特殊なライトがついた拡大鏡で、肉眼では見えない皮膚の浅い層の色素の並び方や血管のパターンを詳細に観察できます。これにより、多くのケースで皮膚を切り取る検査(生検)をせずとも、ほくろと皮膚がんの鑑別や、様々な発疹の正体を見極めることが可能になります。
当院のような皮膚科専門クリニックでは、診断の精度を高めるための特別な機器を備えています。その代表が「ダーモスコープ」です。これは特殊なライトがついた拡大鏡で、肉眼では見えない皮膚の浅い層の色素の並び方や血管のパターンを詳細に観察できます。これにより、多くのケースで皮膚を切り取る検査(生検)をせずとも、ほくろと皮膚がんの鑑別や、様々な発疹の正体を見極めることが可能になります。
また、皮膚は「全身を映す鏡」とも言われ、内臓の病気や膠原病などが、最初のサインとして皮膚に現れることも少なくありません。皮膚科医は、そうした全身疾患のサインを皮膚症状から読み解く訓練も受けています。
当院では、かかりつけの小児科の先生との連携を大切にしながら、皮膚の専門家として、より正確な診断と最適な治療を提供することを目指しています。
当院での治療アプローチ
当院では、お子様の健やかな笑顔とご家族の安心を第一に考え、以下の基本方針に沿って診療を行っています。
正確な診断が治療の第一歩
私たちは、推測で治療を始めることはありません。丁寧な問診と視診に加え、ダーモスコピーなどの専門機器を駆使し、必要であればアレルギー検査や真菌検査、皮膚生検などを行い、病気の正体を正確に突き止めることから始めます。
科学的根拠に基づく個別最適化治療
日本皮膚科学会などが定める最新の診療ガイドラインに準拠した、世界標準の治療を基本とします。その上で、お子様一人ひとりの年齢、症状の重さ、ライフスタイル、そしてご家族のご希望を十分に考慮し、最適な治療プランを一緒に考えていきます。
ご家族が納得できる丁寧な説明
病気が「なぜ」起こり、「どうすれば」良くなるのかを、ご家族が理解し、納得して治療に取り組めるよう、時間をかけて丁寧に説明します。お薬の塗り方から日々のスキンケアまで、ご家庭で実践できる具体的な方法を指導し、治療の主役であるご家族をサポートします。
常に最新・最良の治療を目指して
私たちは、常に皮膚科学の進歩に目を向け、より安全で効果的な新しい治療法を積極的に取り入れています。重症アトピー性皮膚炎に対する生物学的製剤や、他院では行っていない血管腫の治療、小手術など、専門クリニックならではの高度な医療を提供することに意欲的に取り組んでいます。
具体的な症状と年齢別の特徴
新潟の野山で見かける虫や魚が季節ごとに姿を変えるように、お子様の皮膚トラブルも成長段階に応じてその特徴を変えていきます。
新生児・乳児期(0~1歳)
羊水という無菌の水中環境から、乾燥と刺激に満ちた外界へと適応していく時期です。頭や眉に黄色いかさぶたができる「乳児脂漏性湿疹」、おむつ内の蒸れや刺激で起こる「おむつ皮膚炎」、そして「アトピー性皮膚炎」の最初のサインが見られるのもこの頃です。「いちご状血管腫」とも呼ばれる乳児血管腫が出現し、急速に大きくなるのもこの時期の特徴です。
幼児期(1~5歳)
行動範囲が広がり、保育園などで集団生活が始まると、感染症のリスクが高まります。掻きむしった傷から細菌が感染する「とびひ(伝染性膿痂疹)」、ウイルス性の「みずいぼ(伝染性軟属腫)」、夏に流行する「手足口病」などが代表的です。アトピー性皮膚炎は、ひじやひざの裏側など、関節のくぼみにできやすくなります。
学童期(6~12歳)
皮膚のバリア機能は成熟してきますが、活動はさらに活発になります。プールや体育館などでの肌の接触を通じて、ウイルス性の「いぼ(尋常性疣贅)」にかかりやすくなります。また、新潟の豊かな自然の中で遊ぶ機会が増え、虫刺されなども多くなります。
思春期(13歳~)
ホルモンバランスの変化が皮膚に大きな影響を与えます。「にきび」が最も大きな悩みとなる一方、アトピー性皮膚炎が再燃し、顔や首、上半身に症状が強く出ることもあります。
なぜ子どもの皮膚はトラブルが起きやすいのか?

お子様の皮膚がデリケートで、トラブルを起こしやすいのには、いくつかの明確な理由があります。
第一に、皮膚バリア機能が未熟であることです。冒頭の魚の粘液の話のように、皮膚の最も外側にある角層は、外部の刺激から体を守り、内部の水分が逃げないようにする重要なバリアです。お子様の皮膚は大人に比べて薄く、皮脂の分泌も不安定なため、このバリア機能が弱く、乾燥しやすく、アレルゲンなどの刺激物が侵入しやすい状態にあります。
第二に、皮膚の免疫システムが発達途上であることです。免疫システムは、異物を見分けて適切に反応する「学習」の過程にあります。そのため、本来無害なものにまで過剰に反応してしまったり(アトピー性皮膚炎など)、逆にウイルスや細菌に対する抵抗力が弱かったりします。
そして第三に、近年のアレルギー研究で最も重要視されている「経皮感作」というメカニズムです。かつて食物アレルギーは、食べたものが腸から吸収されて発症すると考えられていました。しかし、研究が進み、今では「アレルギーは皮膚から始まる」ことがわかってきました。湿疹などでバリア機能が壊れた皮膚から、ほこりや食べこぼしに含まれるごく微量の食物アレルゲンが侵入すると、皮膚の免疫がそれを「敵」と認識し、アレルギーの準備状態(感作)が成立します。その後、その食べ物を口にしたときに、本格的なアレルギー症状が引き起こされるのです。この「経皮感作」という発見は、アトピー性皮膚炎の治療の重要性を根底から変えました。湿疹をしっかり治し、スキンケアで皮膚のバリアを守ることは、単にかゆみを抑えるだけでなく、
将来の食物アレルギーを予防するための積極的な手段なのです。
さらに、私たちが暮らす新潟特有の環境も影響します。冬は冷たく乾燥した空気と暖房により、皮膚の水分が奪われ、乾燥肌や「しもやけ」が悪化します。一方、夏は高温多湿で汗をかきやすくなります。汗自体が刺激になったり、汗の管を詰まらせて「あせも」ができたり、アトピー性皮膚炎を悪化させます。また、夏はとびひなどの感染症や、山での虫、海水浴でのクラゲとの遭遇も増える季節です。
代表的な疾患と治療法
ここでは、お子様によく見られる代表的な皮膚疾患と、当院での治療法について具体的に解説します。
| 疾患名 | 主な特徴と症状 | 好発年齢 | 標準的な治療アプローチ |
|---|---|---|---|
| アトピー性皮膚炎 |
強いかゆみを伴う湿疹が、良くなったり悪くなったりを繰り返す。乾燥肌がベースにある。 |
乳児期〜成人 |
治療の三本柱:①炎症を抑える薬物療法(ステロイド外用薬、免疫抑制外用薬など)、②スキンケアによるバリア機能の補強、③悪化因子の対策。 |
| 乳児血管腫(いちご状血管腫) |
生後まもなく出現し、急速に赤く盛り上がる良性の腫瘍。自然に消える傾向がある。 |
0〜1歳 | 機能や見た目に問題を生じる可能性がある場合、内服薬(プロプラノロール)が第一選択。小さいものは外用薬やレーザー治療も。 |
| とびひ(伝染性膿痂疹) | 虫刺されや湿疹を掻き壊した傷に細菌が感染。水ぶくれや黄色いかさぶたができ、あっという間に広がる。 |
幼児〜学童期 |
抗菌薬の内服・外用。患部を清潔に保つことが重要。 |
|
みずいぼ(伝染性軟属腫) |
ウイルス感染症。光沢のある小さなドーム状のいぼができる。かゆみは少ないことが多い。 | 幼児〜学童期 | 自然治癒も期待できるが、拡大・感染予防のため専用のピンセットによる摘除や外用療法を行う。 |
| いぼ(尋常性疣贅) | ウイルス感染症。手足の指や足の裏にできやすい、表面がザラザラした硬い盛り上がり。 | 学童期〜 | 液体窒素による凍結療法が基本。その他、外用薬や内服薬、レーザーを併用することも。 |
|
おむつ皮膚炎 |
おむつが当たる部分の赤み、ただれ。刺激によるものと、カビ(カンジダ)によるものがある。 |
乳児期 | こまめなおむつ交換と清拭・洗浄が基本。刺激性の場合は保護軟膏、カンジダ性の場合は抗真菌薬の外用。 |